水面から飛び出した魚(1) 飛び魚と毒薬(13)|石田英敬
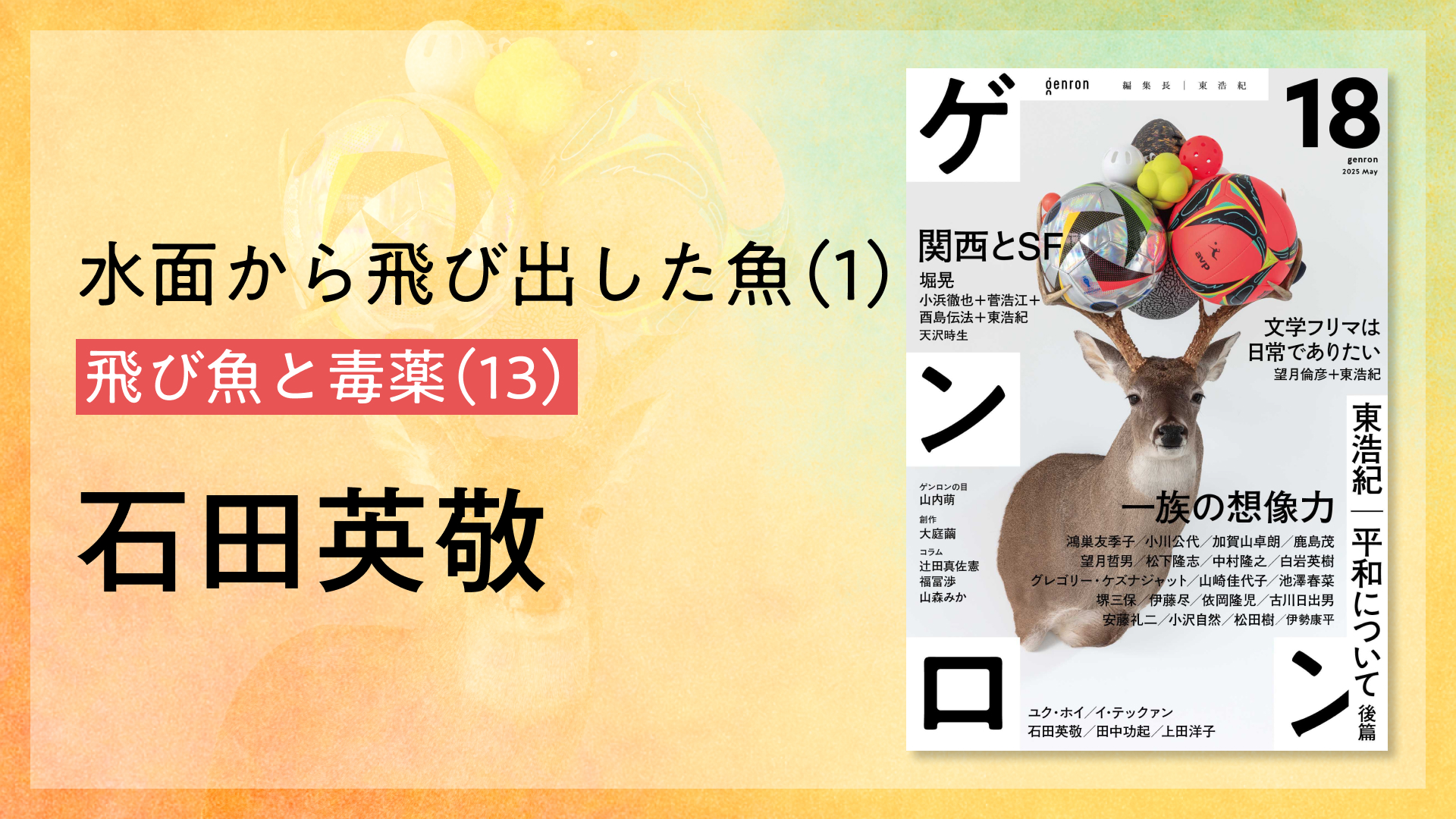
ぼくは独房のなかで深く思考した、水面から飛び出したトビウオのようだった。
「哲学が何であるかは、誰もすでに何等か知っている。もし全く知らないならば、ひとは哲学を求めることもしないであろう。或る意味においてすべての人間は哲学者である。言い換えると、哲学は現実の中から生れる。そしてそこが哲学の元来の出発点であり、哲学は現実から出立するのである」[★1]。高校生のとき父親の書棚から見つけて読んだ、三木清『哲学入門』の始まりの言葉だ。
すべての人間は潜在的に哲学者である。
だれもが、自分の裡に〈哲学者〉をヴァーチャルに秘めている。その潜在態にとどまっていた〈哲学者〉が、種から芽が出るように生長しある偶然がきっかけで現勢態に移行する。現に活動し始める。
哲学する、哲学者になる、とは、そういうことなのだ。
二つの現勢化
ここで現勢化と記すことにする言葉は、フランス語では、passer à l’acteという。潜在的な状態から現在の行為acteあるいは活動acteに移行するpasserという意味だ。
この言葉が、ベルナールが銀行強盗事件で逮捕されて入獄、独房のなかで哲学にめざめ哲学者になるまでの「現勢化」を告白した本のタイトルになっている[★2]。
passer à l’acte、潜勢態から現勢態への移行。
少しでも哲学を囓ったひとなら思い浮かべるのが、アリストテレスによる、「デュナミス」と「エネルゲイア」あるいは「エルゴン」という区別[★3]。潜在態から現勢態への移行のこと。三木清もそれを強く意識して書いている。それは、例えば、種子の状態にとどまっていたヴァーチャルな樹木が、現実の土壌に根を張り日の光を浴びて枝を拡げ葉を茂らせ実際の樹木として生育することだ。
ベルナールの場合、事態は急激かつ複雑で、幾つもの時代的・思想的文脈が折り重なって起こっている。それをこれから少しずつ読み解いていくことにしよう。
まず、彼の場合、二つの現勢化が劇的に起こった。あるいは、別様に言えば、ベクトルの異なる二つの〝現勢化〟が、相前後して起こった、と言うべきか?
というのも、passer à l’acteというフランス語の表現、じつは別の意味もあって(というか、こっちの方が普通の使われ方と言える)、実行する、決行する、そして、(精神分析や精神医学の意味では)衝動的な行動に及ぶ、あるいは、凶行に及ぶという意味もあるからだ[★4]。
銀行強盗という凶行に及ぶ第一のpasser à l’acteがまず起こった。それから、哲学者になるという、第二のpasser à l’acteが起こった。
二つの出来事が、時間的にとても近接して起こったことにも、注目すべきだと思う。
それらの間に、どのような関係があるかがここでのわれわれの関心事だが、そこには、原因→結果というような直接的な因果関係ではなく、「準因quasi-cause」、あるいは、「準因果性quasi-causalité」という、ぼくたちが人生の出来事を考えるうえで興味深く実践的にも大変役に立つ、特異な因果関係が介在していたのだ。これから、少し連載の回を重ねて、順序立てて述べていくことにしようと思う[★5]。
これから語ろうと考えているベルナールの物語の見取り図を予告しておくと、大きく三つの出来事のセリーになっている。
★1 三木清「哲学入門」。引用は青空文庫(URL=https://www.aozora.gr.jp/cards/000218/files/43023_26592.html)から。三木清はすごい哲学者なんだぜ。みんな読んだ方がいい。
★2 原著はBernard Stiegler, Passer à l’acte, Galilée, 2003.邦訳はベルナール・スティグレール『現勢化──哲学という使命』、ガブリエル・メランベルジェ、メランベルジェ眞紀訳、新評論、2007年。
★3 アリストテレスの「デュナミス」と「エネルゲイア」あるいは「エルゴン」という概念対は、英語やフランス語では、それぞれ、potentiality / actuality、puissance / acteという言葉が使われる。
★4 ベルナールのタイトルは、passer à l’acteをアリストテレスに遡って、語源的に捉え返していると理解すべき。日本語訳は『現勢化』を採用している。ちなみに英語訳はActing Outで、精神分析用語を採用している。Bernard Stiegler, Acting Out, Stanford University Press, 2008.
★5 ついでに言っておくと、わたし自身も、第10回で読んでもらったように、自分の悲惨な出来事を語ってきているのだが、そこにもまた、いかに人生の出来事を自分の必然として生き直すのかという、準因果性の問題系が絡んでいる。この連載を「クロス・バイオグラフィー」として書いている理由を分かってもらえたらうれしい。
★6 これらの順位は以下のサイトで検索できる。URL=http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=agregsecondaire_laureats
★7 以下を参照。URL=https://www.politproductions.com/gerard-granel
★8 フランスの大体の大学人が、最終的には自分が高等教育を受けた首都のパリに戻ってこようという〝帰巣本能〟(!)をもっていることは、日本の大学人が東京とか京都に戻ってこようとするのと同じだ。大学人は自分の生まれた川に戻ってこようとする鮭とかと同じなのだ。だけど、グラネルは違う。パリ16区という最もブルジョワな地区で生まれ、ルイ・ル・グランという超名門リセを出て高等師範学校にトップで入学した大秀才だけれど、自分はラングドックの薔薇色の古都トゥールーズに独自の知の根拠を築こうとした。偉いね!
★9 Gérard Granel, Le Sens du Temps et la Perception chez E. Husserl. Edition Gallimard, 1969.
★10 公式サイトは以下。URL=http://www.ter-editions-philo.com/
★11 グラネルの生涯と業績については、以下のWikipediaを参照のこと。URL=https://fr.wikipedia.org/wiki/Gérard_Granel
★12 グラネルは1959年にハイデガーの『思惟とは何の謂いか』を仏訳(Qu’appelle-t-on penser?, PUF, 1959.)。その機会にハイデガー自身と最初に面会している。「存在の問いへ」(原題 Zur Seinsfrage, 1956. 邦訳題「有の問いへ」、『ハイデッガー全集第9巻 道標』所収)は“Contribution à la question de l’être”のタイトルでHeidegger, Question I (Gallimard, 1968)に所収。この翻訳作業の時期とデリダとの交友は重なるから、そのなかで訳語は共有されていたのだろうと考えられる。その翻訳でAbbau(破壊、解体)がdé-constructionとフランス語訳されている(同書240頁)。
★13 Gérard Granel “Jacques Derrida et la rature de l’origine,” Critique 23, n° 246 (novembre 1967) et repris dans Traditionis Traditio (Paris, Gallimard, 1972).グラネルの論文がフーコー・デリダ論争の伏線となった経緯については、ディディエ・エリボンの『ミシェル・フーコー伝』(邦訳は新潮社、1991年)第2部第2章「書物とその分身」に詳しい。
★14 ドイツ在住でチリ出身の哲学者、ヴィクトル・ファリアスが1987年フランスで『ハイデガーとナチズム』(Victor Frarias, Heidegger et le nazisme, Verdier, 1987)を出版したことをきっかけに、フランスでは(ドイツではすでによく知られていたことだったが)ハイデガーのナチス時代の仕事、および彼の哲学とナチズムとの深い関係について、さまざまな論争が繰り広げられた。フランスの戦後思想界はハイデガーの強い影響下で発展したから、騒ぎは大きかった。グラネルはハイデガーのナチへの加担の過去については認めたうえで、それを裁くこととその問題を思想的に受けとめることとの違いを説き、思考することと時代との関係を深く考えようと諭している。Gérard Granel, “La guerre de Sécession Tout ce que Farias ne vous a pas dit et que vous auriez préféréne pas savoir,” Le débat, 1988 No48 janvier-février.
★15 このバンドの詳細は以下のWikipediaを参照。URL=https://fr.wikipedia. org/wiki/La_Souris_déglinguée グラネルが支援したアルバムは以下。URL =https://fr.wikipedia.org/wiki/As-tu_d%C3%A9j%C3%A0_oubli % C3 % A9 _ %3F
★16 だが、この件について証言を残しているかは、私の知る限り、不明だ。一般に、そういうことは公的には語らないと思う。それが分別ある人間の良識というものだ。
★17 Bernard Stiegler, Dans la disruption: Comment ne pas devenir fou?, Les Liens Qui Libèrent, 2018, p. 301.これまでの連載では、ラジオインタビュー番組からベルナールの自伝的事実を追うかたちで語ることが多かったが、思想的な経験については、最後期の著作などから内在的に追うことがこれから増えていくと思う。いかにベルナールにおいて哲学が「現勢化」していったのか、その軌跡を哲学的に捉え返すためだ。
★18 Ibid., p. 100.
★19 この節の見出し「〈読む〉という、この実践」はマラルメ『ディヴァガシオン』所収、「文芸の中の神秘」(Mallarmé, “Le Mystère dans les Lettres,” Divagations.)の、「Lire─[……]Cette pratique─」という一節から取っている。URL= https: // fr. wikisource. org/wiki/Divagations_(1897)/Le _ Mystère_dans_les_lettres
★20 Ibid., p. 301.
★21 Ibid., p. 100.
★22 Ibid., p. 302.強調は原文。
★23 フッサール『論理学研究』の第1研究「表現と意味」については、フッサールの当該巻を読むのが良いが、同時に、デリダの『声と現象』は、この第1研究「表現と意味」についての脱構築の出発点になった重要な考察だから一緒に読むと良い。そうするとデリダが思考や言語についてどのような問いから出発したかがすごくよく分かるはずだ。
★24 マラルメ「詩句の危機」。Stéphane Mallarmé “Crise de vers,” Divagations. URL=https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Mallarmé_-_Divagations.djvu/263ここでの訳文は石田による。
★25 Stiegler, Dans la disruption, p. 94.
★26 Ibid., p. 303.強調は石田。エリザベト・リガルÉlisabeth Rigal (1950-)は、ジェラール・グラネルの生涯の妻だった哲学者で翻訳家でもある。ヴィトゲンシュタインを専門とする。詳しい業績については、Wikipediaを参照してほしい。URL=https://fr.wikipedia.org/wiki/Élisabeth_Rigal
★27 Ibid., pp. 96─97.
★28 デカルト『省察・情念論』、井上庄七他訳、中公クラシックス、2002年。Kindle版より引用。
★29 Passer à l’acte, p. 30. 邦訳44頁に対応。


石田英敬
1 コメント
- TM2025/05/30 22:10
芽吹きの可能性、それに気が付き適切な栄養を導ける良き先生グラネルの存在がいかに大きいか、ひしひしと伝わってきました。 どんな可能性に満ちた芽吹きも出会いという外部要因の影響を強く受ける。ドラマだなと感じます。 また監獄が現象学の実験室になるといるのも環境をネガティブ色に染めきれないからこその発想かもしれません。実験室での思索の軌跡。次回も楽しみです!
飛び魚と毒薬
- 水面から飛び出した魚(2) 飛び魚と毒薬(14)|石田英敬
- 水面から飛び出した魚(1) 飛び魚と毒薬(13)|石田英敬
- 「亡命時代」(1) 飛び魚と毒薬(12)|石田英敬
- 道理の前で 飛び魚と毒薬(11)|石田英敬
- 1974.1.24 飛び魚と毒薬(10)|石田英敬
- ネオテニーの青春 飛び魚と毒薬(9)|石田英敬
- 日々の泡 飛び魚と毒薬(8)|石田英敬
- 農村の生活 飛び魚と毒薬(7)|石田英敬
- 1960年代の「想像力」 飛び魚と毒薬(6)──『ゲンロン16』より|石田英敬
- 想像力を権力に! 1968年5月20日 飛び魚と毒薬(5)|石田英敬
- 68年5月10日 飛び魚と毒薬(4)|石田英敬
- 68年5月3日 飛び魚と毒薬(3)|石田英敬
- 飛び魚と毒薬(2) 詩とアルコールと革命と|石田英敬
- 飛び魚と毒薬|石田英敬




