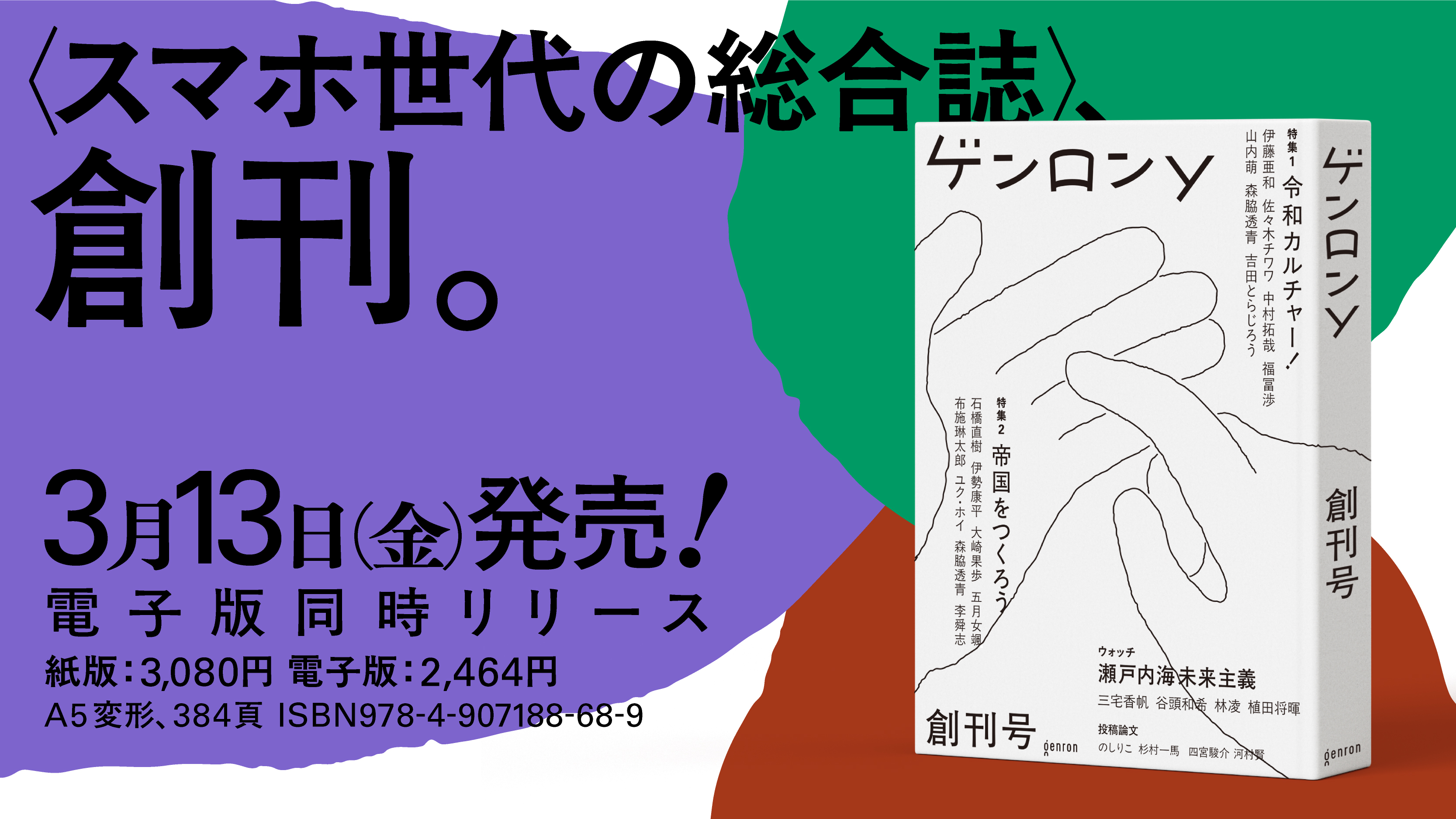記憶とバーチャルのベルリン(7) 2022年のベルリンと鷗外(後篇)|河野至恩

2年半ぶりのベルリンの風
2022年7月、私はフンボルト大学で開催される鷗外没後100年記念行事で講演を行うため、ベルリンに旅立った。成田発、経由地のチューリヒ行きの旅客機は、ロシアの領空を避け、大きく北極海側に迂回してヨーロッパへと飛行していった。到着したのは、従来のテーゲル空港に代わってベルリンの主要空港としてコロナ禍の最中に開港したブランデンブルク空港。旅客の急速な増加に空港職員の配置が追いつかないのか、飛行機が着陸してからスーツケースが現れるまでかなりの時間を要したが、それ以外は大きなトラブルもなかった。
ヨーロッパでは夏に水際対策が解除された。マスク義務も多くの場合に撤廃され、日本のニュースではヨーロッパの開放感あふれる映像が流れた。一方、日本では、入国時の制約は大きく緩和されたが、入国前72時間以内のPCR検査だけは残されており、これに陽性となる(あるいは陰性証明書を入手し損ねる)と帰国できずに滞在先で長期間の足止めをくらう、という状態だった。そのため私も、感染しないように極力注意するだけでなく、検査を受けた後、空港検疫の事前手続アプリに検査結果の文書をアップロードするなど、ひとつひとつのステップに神経を使うこととなった。帰国便の前日、入国審査のアプリがファストトラック(優先入国)許可を示す緑色に変わったときには、さすがに安堵した。
新型コロナウイルスの感染対策に振り回されたこの3年間、国境の水際対策もさまざまに変化していった。日本の対策を振り返ってみると、感染を食い止めた局面もあったかもしれないが、実際には、渡航する人々の都合を考えない施策が現場に押しつけられ、理不尽な状況が起こることが多かったのではないか。この夏に私が経験したのも、そうした混乱のうちのひとつだったように思う。
ともあれ、2年半ぶりに訪れたベルリンは格別だった。このコラムの読者にはくり返しになるが、ベルリンを訪れるのは、コロナ禍が本格化する直前の2020年1月以来となる。
今回の滞在中、ミッテ(ベルリンの中心地区)の森鷗外記念館近くのホテルに滞在していたのだが、到着した次の日、ふと散歩がしたくなり、ブランデンブルク門から国会議事堂を眺めつつシュプレー川を渡る橋を徒歩で渡った。橋の上でこのときばかりはと少しマスクを外し、夏とはいえ涼しい夜の風を肌で直接に感じた。また、日本にいる息子のために地下鉄の動画を撮ったり、インビス(軽食スタンド)でサンドイッチを食べたりという、普段の滞在ならば当たり前だったことも、新鮮に感じられた。

講演の場では、今回招待してくださったフンボルト大学の方々、そして、講演を聴きに来てくださった人々と、ビデオ通話の画面越しにではなく、実際に対面して言葉を交わすことの喜びがあった。短い滞在ではあったが、何人かの知人・友人に、久しぶりに会って旧交を温めることもできた。


河野至恩
記憶とバーチャルのベルリン
- 「移動」の文学について考え続けること──多和田葉子『雪の練習生』を読む 記憶とバーチャルのベルリン(最終回)|河野至恩
- 記憶とバーチャルのベルリン(9) ベルリンで思い出す、大江健三郎が残したもの|河野至恩
- 記憶とバーチャルのベルリン(8) 人生を通しての言語とのつきあい方|河野至恩
- 記憶とバーチャルのベルリン(7) 2022年のベルリンと鷗外(後篇)|河野至恩
- 記憶とバーチャルのベルリン(6) 2022年のベルリンと鷗外(前篇)|河野至恩
- 記憶とバーチャルのベルリン(5) 翻訳・多言語の街、ベルリン|河野至恩
- 記憶とバーチャルのベルリン(4) ライプツィヒ日本学とは何か(後篇)──空き家、西田幾多郎全集、そして学びの〈場〉|河野至恩
- 記憶とバーチャルのベルリン(3) ライプツィヒ日本学とは何か(前篇)──「なんでこうなったのか知りたい!」シュテフィ・リヒター『闘う日本学』を手がかりに|河野至恩
- 記憶とバーチャルのベルリン(2) ベルリンでパパ鉄──父と子で味わうドイツ・ベルリンの鉄道文化|河野至恩
- 記憶とバーチャルのベルリン(1) 移動できない時代の「散歩の文学」――多和田葉子『百年の散歩』を読む|河野至恩