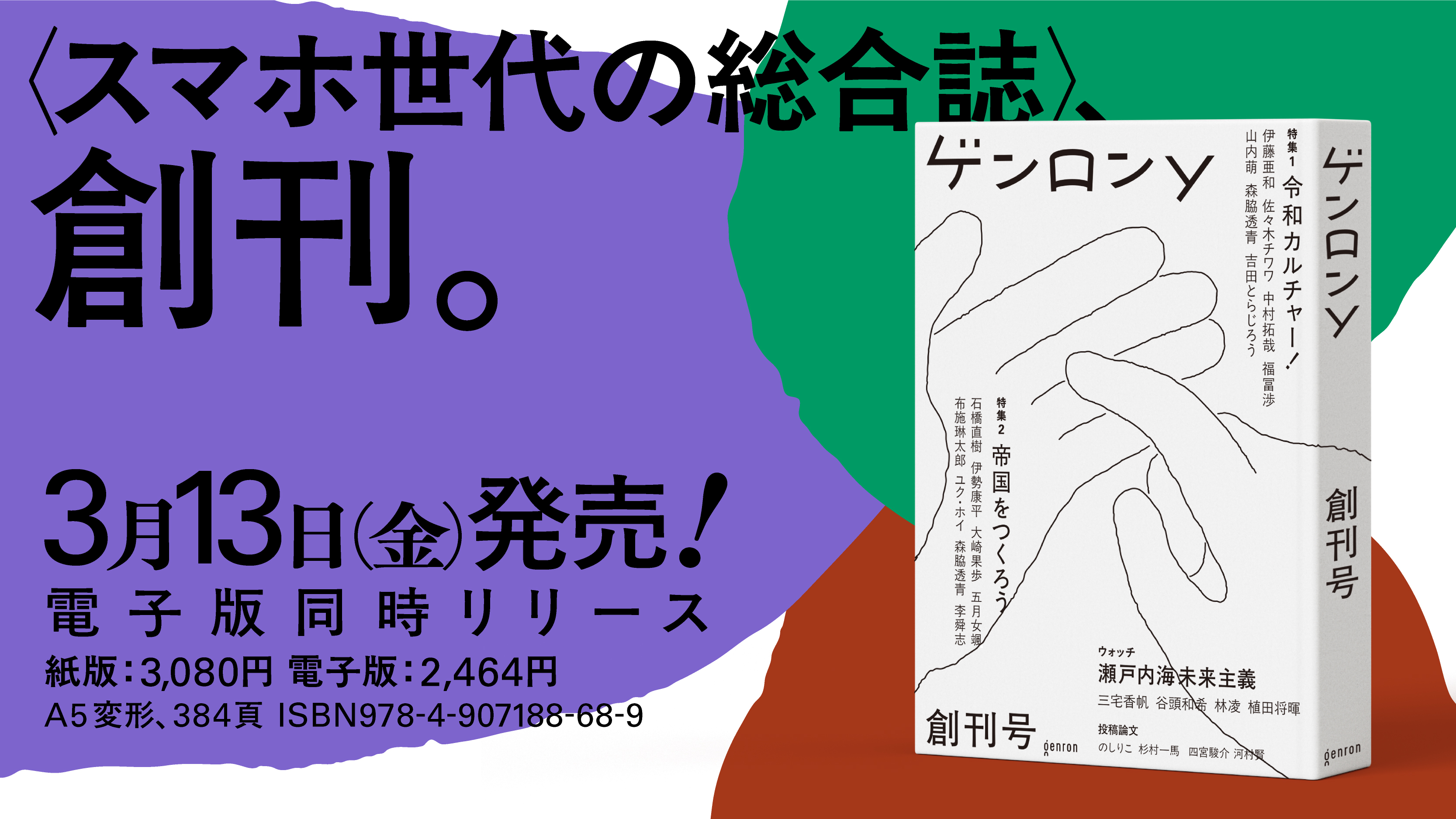記憶とバーチャルのベルリン(8) 人生を通しての言語とのつきあい方|河野至恩

初出:2023年4月18日刊行『ゲンロンβ80+81』
外国語を学ぶ人生
外国語を学ぶということは、他の趣味や勉強とは異なり、人生という長い時間のスケールの中で考えることをともなうように思う。
例えば、新しく外国語を学ぶ場合、そのきっかけには、この文章は何としても原典で読みたいとか、現地の人々と不自由なくコミュニケーションを取りたいとか、新しい仕事に必要だとか、それぞれに切実なものがあるだろうから、モチベーションは高い。しかし、学び始めてからある程度使いこなせるようになるまでには、それなりの時間と労力を投資しなければならない。そう思うと、これからそのような時間が取れるだろうか、と考えたりする。
外国語を学ぶために、人生のいつ、どれだけの時間と労力を投入するのか。それによってどのような恩恵を受けるのか。人によっては、それがその後の人生のあり方を変えることもある。言語とはそのように、人生の中で「つきあって」いくものなのだろう。
外国語とどうつきあうか。そのことを考えるうえで参考になるのは、文学者と外国語の関係性だ。文学研究をしていると、作家の人生と自分の人生のタイムラインを重ねて考えることがある。その結果、たいていの場合、若くして多大な業績をなした作家の偉大さに意気消沈することになるのだが、それでも、自分の人生を展望するのに、その道しるべにすることはできる。
私の場合、森鷗外の作品を長年研究してきたが、彼がドイツに留学した時期というのはよく意識する。1862年生まれの鷗外がドイツに渡航したのは1884年、22歳のときのこと。その後、5年間にわたって、主にライプツィヒ、ドレスデン、ミュンヘン、ベルリンの4都市で衛生学を学びながらドイツの文化を吸収していった。また、自分の部屋に戻ると文学作品を濫読したという。そうした活動の詳細は「独逸日記」に記録されている。
前回も書いたように、鷗外は幼少の頃からオランダ語を学び、ドイツ語は現代でいう小学生のときに集中的に教わるなど、特別な教育を受けていた。中でもドイツ語の世界で生きた20代の5年間は、若い鷗外のみずみずしい感性に強烈な印象を残しただけでなく、その後の文業の基礎になったといわれている。
一方、同じく文学の大家でありながら、鷗外とは対照的な留学体験をした人物に夏目漱石がいる。1867年生まれの漱石がイギリス留学に出発したのは1900年、33歳のときで、ロンドンで約2年間を過ごした。留学中に培った文学についての深い洞察がのちに『文学論』に結実したといわれるが、実際の生活では経済的に困窮し、心理的にも鬱々として部屋に引きこもりがちだったという。渡航前は英語教師をしていた漱石は、当然英語に堪能だったが、その留学体験は鷗外のそれとは対照的だった。
鷗外と漱石の留学体験にそのような違いが生まれたのには、それぞれの気質だけでなく、人生のタイムラインの中での海外生活のタイミングに違いがあったからではないだろうか。鷗外は、一人の学生として自由を謳歌し、時間をかけて学びに没頭することができたのに対して、漱石は社会人として、家庭人としての責任に耐えながら、学問を通して新しい境地を模索していた。どちらが良いかということではなく、人生のステージによって、外国語の中で生きることの意味あいは異なる、ということなのだろう。鷗外にとっての「ドイツ語」、漱石にとっての「英語」の、生涯を通じてのつきあい方、その人生における位置づけについて考えさせられる。
より最近の例でいえば、水村美苗が挙げられるだろう。12歳で渡米し、ティーンエイジャー時代から大学院までを英語の世界で過ごした彼女は、30代、プリンストン大学講師時代に書いた『續明暗』で小説家としてデビュー。以後日本語で執筆を続けている。氏にとっての「日本語」と「英語」への複雑な思いは、有名な『日本語が亡びるとき』だけでなく、その他のエッセイにも多く語られている。氏の公式ウェブサイトに、自らを指して「日本語で日本近代文学を書く小説家 A novelist writing modern Japanese literature in the Japanese language.」[★1]と書かれているのには、水村の作家としてのアイデンティティに言語がいかに深く結びついているのかを、よく表している。英語に囲まれて生きていた人生を転換し、日本語で書く作家となる道を選び取ったその経験は、自伝的な小説『私小説 from left to right』からうかがい知ることができる。


河野至恩
1972年生まれ。上智大学国際教養学部国際教養学科教授。専門は比較文学・日本近代文学。著書に『世界の読者に伝えるということ』(講談社現代新書、2014年)、共編著に『日本文学の翻訳と流通』(勉誠出版、2018年)。
記憶とバーチャルのベルリン
- 「移動」の文学について考え続けること──多和田葉子『雪の練習生』を読む 記憶とバーチャルのベルリン(最終回)|河野至恩
- 記憶とバーチャルのベルリン(9) ベルリンで思い出す、大江健三郎が残したもの|河野至恩
- 記憶とバーチャルのベルリン(8) 人生を通しての言語とのつきあい方|河野至恩
- 記憶とバーチャルのベルリン(7) 2022年のベルリンと鷗外(後篇)|河野至恩
- 記憶とバーチャルのベルリン(6) 2022年のベルリンと鷗外(前篇)|河野至恩
- 記憶とバーチャルのベルリン(5) 翻訳・多言語の街、ベルリン|河野至恩
- 記憶とバーチャルのベルリン(4) ライプツィヒ日本学とは何か(後篇)──空き家、西田幾多郎全集、そして学びの〈場〉|河野至恩
- 記憶とバーチャルのベルリン(3) ライプツィヒ日本学とは何か(前篇)──「なんでこうなったのか知りたい!」シュテフィ・リヒター『闘う日本学』を手がかりに|河野至恩
- 記憶とバーチャルのベルリン(2) ベルリンでパパ鉄──父と子で味わうドイツ・ベルリンの鉄道文化|河野至恩
- 記憶とバーチャルのベルリン(1) 移動できない時代の「散歩の文学」――多和田葉子『百年の散歩』を読む|河野至恩