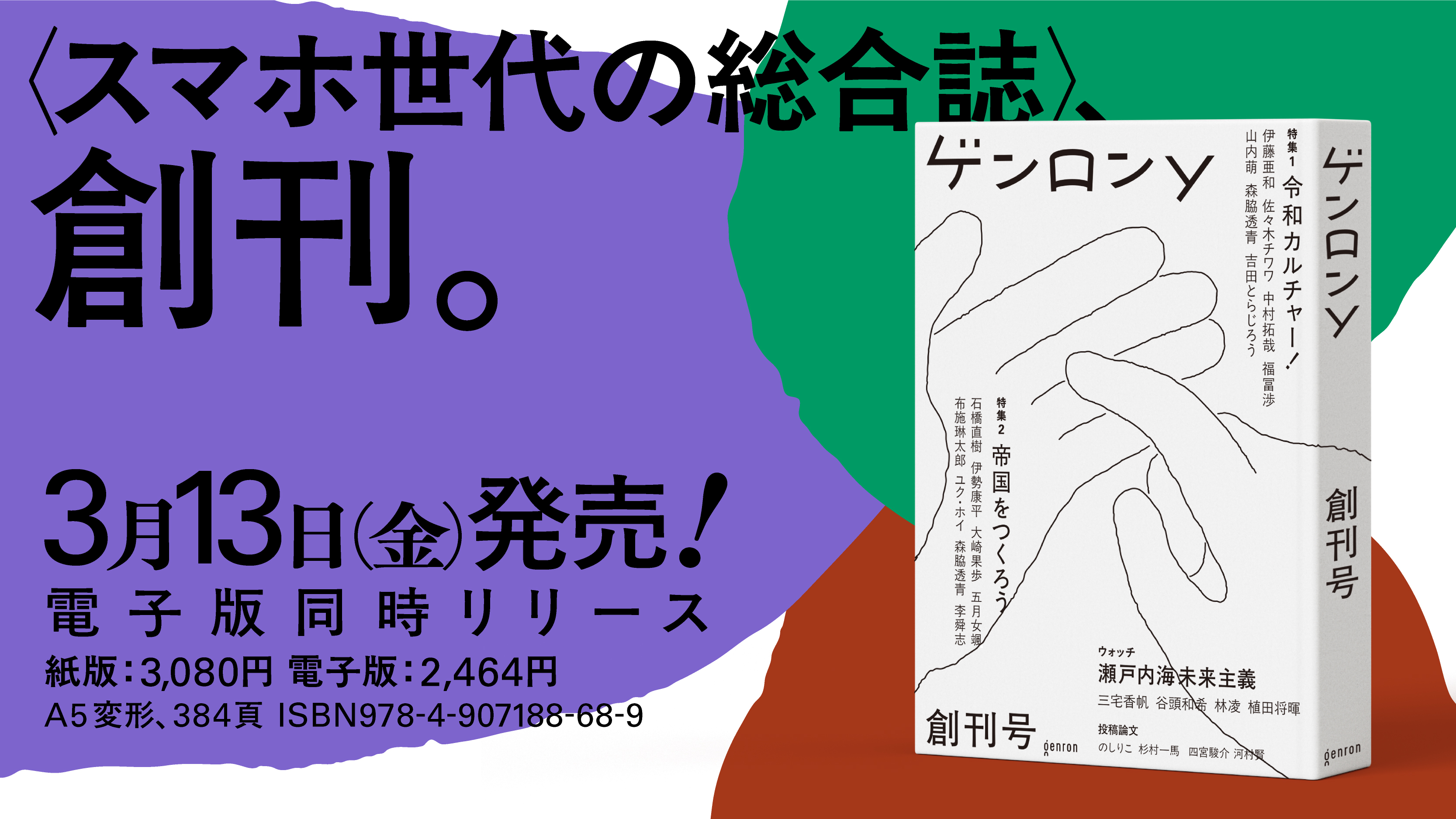制作者のまなざしを探る──カサヴェテス、三宅唱、映画学 じんぶんアジール(2)|堅田諒

日本の大学で映画を研究しているわたしは、2024年の3月に博士号を取得した。博士論文は、アメリカの映画監督であるジョン・カサヴェテス(1929-89)を対象にしたものだった。簡単に言うと、映画学の専門家として認められたということになる。
そう書き出してみたものの、正直な思いをしるせば、「研究」や「映画学」といった言葉には映画を見る楽しさからはかけ離れた堅苦しさを感じてしまう。わたしが所属しているのは、大学を中心としたアカデミックな映画学/映画研究の世界なのだが、そのまえに大前提として映画というのはビジネスでありエンターテイメントでもあるからだ。
当たり前の事実だが、映画が実際につくられなければ、研究者の「研究対象となる映画」も存在しない。研究という世界の、映画の物語を解釈したり映画にまつわる歴史的な事実を実証したりする営み(もちろんそれが映画学のすべてではないが)にのみ身をおいていると、これまでに映画を制作してきた人たちの実践や葛藤からどんどんと遠ざかっていくような気になってしまう。
学部生時代は、映画サークルに所属して映画をつくったこともあった。そして大学院に進学し、カサヴェテスを研究対象に選んだ。カサヴェテスは「インディペンデント映画の父」と呼ばれ、映画のなかでもとくに俳優の演技を重視したことで知られている。カサヴェテスの『こわれゆく女』(1974年)をはじめてみたとき、何がすごいかわからないが俳優たちから発されるエネルギーに圧倒され、それまで自分が見ていたアメリカ映画とは違うということだけは直感的にわかった。
しかし、大学院でカサヴェテスについての研究書や論文を読んでもどこか腑に落ちず、「自分」と「映画」のあいだに埋められそうにない「距離」を感じてしまっていた。たとえば、カサヴェテス研究の第一人者であるレイモンド・カーニーは「ジョン・カサヴェテスとは、アメリカの官僚主義的な映画製作の恐るべき環境にあって、とりわけ想像力の自由と表現の自由をめざすアメリカン・ドリームを活性化させ続けようとしたアメリカン・ドリーマーなのである」[★1]なんて言っているけれど、こういった言葉が、自分がカサヴェテスの映画をはじめてみたときの気持ちを解き明かしてくれるものではなかった。研究を続けるなかでも、「研究する自分」と「映画」との関係がよくつかめないという感覚がずっとあった。
そんな居心地の悪さを感じつづけてきた一方で、わたしは、現在進行形で活躍する映画の制作者たちへのインタビューを同じ研究室のメンバーとともに継続的におこなってきた。このエッセイでは、わたしが感じていた映画との距離が、映画の制作者たちへのインタビューをきっかけに、じょじょに変わっていった経験について書いてみたい。
インタビューのきっかけ
これまでにわたしたちがインタビューをしてきたのは、三宅唱(1984-)、真利子哲也(1981-)、今泉力哉(1981-)、小田香(1987-)の四人の比較的若い世代に属するフィルムメイカーたちだ[★2]。とある映画批評家は、近年の日本における若手監督たちの躍進について、「日本映画の第三の黄金時代を築く」[★3]と述べているが、彼らもその一角を担っている存在だ。
ここでは最初の取材対象であった三宅監督について語ることにする。札幌での三宅監督のトークイベントの際に言葉を交わす機会があったことや、インタビューをおこなった2020年の時点で、三宅監督が長編映画デビューからちょうど10年という節目に当たるタイミングであったことが、彼への依頼の決め手となった。
三宅監督は、瀬尾まいこの小説を原作とし、松村北斗と上白石萌音の二人が主演をつとめた『夜明けのすべて』(2024年)や、聴覚障害を持つプロボクサーを岸井ゆきのが演じた『ケイコ 目を澄ませて』(2022年)などの作品をこれまでに制作していて、国内で多くの賞を受賞しているのみならず、海外の映画ファンからも高く評価されている。三宅作品の大きな特徴は、言葉では捉えきれない俳優たちの微細な感情が、映画鑑賞後の観客に確かな感動となって残るという点にある。同じく俳優の感情表現を重視したことで知られるカサヴェテス作品への愛を三宅監督はところどころで口にしており、わたしは両者のつながりをどこかで感じていた。
三宅監督本人からも快く取材の許可を得ることができたが、映画監督へのインタビューの経験などまったくないわたしは、「さあどうしたらよいものか」と頭を悩ませたことをよく覚えている。とにかく準備をするしかないと三宅作品を繰り返し見直し、資料を読み漁った。
三宅唱監督の「映画の倫理」
インタビューでは、撮影現場や映画を編集する段階で制作者たちにはどのような試行錯誤があり、個別のシーンの演出や表現を作りだしていったのかを聞きだすことに焦点をしぼった。逆に、「この映画で言いたいことは何か」といったような抽象的な問いかけは徹底的に廃した。
たとえば、三宅監督の場合であれば、ホラー作品である『呪怨:呪いの家』(2020年)で物語の舞台となる「家」はどのような基準で選んだのか、あるいは、「家」の外観や内部を登場人物や幽霊と関連させて、どのように「恐ろしい」ものとして見せる工夫をしたのかを質問した。
三宅監督は、前者に関して、人物が侵入するための大きな窓や、幽霊が出現する屋根裏部屋がある物件が条件であったこと、また作品が要請する世界観のために「個性のなさ」を特徴とする「家」を探したことを答えてくれた。また後者については、登場人物のPOV(主観ショット)のほかに、誰の視点かわからないPOVを混ぜて、「一体誰が見ているんだ?」とのちに起こる恐怖を予告するような編集で映画を作りあげたことを語ってくれた。
ときに脚本を持ちだして当時のことを思いだしながら取材を受けてくれた三宅監督の寛容さと誠実さに感動したのを覚えている。そのやりとりによって、研究だけでは知りえない具体的な制作手法や知恵を多く学んだ。
だが、それ以上に得られたものがある。それは、制作の過程から、その監督に固有の「映画づくりへの態度や姿勢」が見えてきたことだ。少し長くなるが、三宅監督の言葉の一部を引用しよう。
映画を作るとき、基本的にはすべて作り物としてゼロから作るわけですが、低予算映画になればなるほど、目の前にすでにあるものを利用することになります。その時、それをどう利用するか。どういう距離と角度に立つのか。それが倫理ではないでしょうか。[……]色々な考え方、実践があると思いますし、もちろんひとつの決まった正解はない。それに、結局いくらそれが「正しい」と訴えても、映画としての面白さや驚きがなければ意味はありません。実社会の規範とは微妙に違う、誤解を恐れずに言えば、「映画の倫理」というものがあると思います。映画を作ることとは、当人が意識するにせよしないにせよ、その瞬間その瞬間自分の倫理が試されるものです。[★4]
三宅監督は引用箇所の直前で、「何でもカメラで撮れるようになった時代だからゆえに、カメラの暴力性に無自覚か、あるいは麻痺してしまっていると思うことがたまにあります」[★5]と、現代の撮影をとりまく環境にある種の危惧をしめしている。
そのうえで三宅監督は、目の前の被写体(ここでは主に俳優が想定されている)に対してカメラを向けることは自分の倫理が試される行為であるのと同時に、そこに「映画としての面白さや驚き」がなければ意味はないとも言う。撮ることの暴力性を自覚しつつも、「正しい」だけでなく映画的に「面白さや驚き」のあるものをつくること。それを「映画の倫理」という言葉でいい表している。
ここには、現場での具体的な試行錯誤に根ざしつつも、それを超えた、三宅監督独自の映画づくりへの鋭い問題意識が存在している。その問題意識は、単なる技法の探求にとどまらず、映画という表現が持つ本質的な可能性を考え直すものだった。このような三宅監督の映画づくりに対する根本的な姿勢に触れることは、自分自身の映画への向き合い方にも大きな変化をもたらした。なぜなら、映画監督から直接話を聞くことは、単に作品の裏側を知ること以上に、制作者の視点=まなざしを通じて映画を別の角度から捉え直す、新たな視座を得る経験となったからだ。それは、映画を「完成された作品」として消費するのではなく、制作の過程や作り手の思考の痕跡を読み取る行為へと変えていくものだった。
このような経験を重ねるなかで、「映画」と「研究」は次第に自分のなかで重なり合うようになっていった。やがて、映画を研究すること自体が、映画をつくる行為と地続きのものであるという感覚が芽生えはじめたのである。

カサヴェテス『トゥー・レイト・ブルース』のラストシーン
すでに書いたように、わたしはアメリカの映画監督ジョン・カサヴェテスの研究を進めてきた。博士論文では、もともと自身も俳優だったカサヴェテスによる「俳優たちを重視した映画制作」とはいかなるものであったのかを検討した。
たとえば、監督第2作『トゥー・レイト・ブルース』(1961年)は、彼が「インディペンデント映画の父」としての歩みを本格的に始めるまえに、ハリウッドで雇われ監督として撮ったもので、ジャズ・ミュージシャンたちを題材にした映画だ。映画の中心的な人物は、ピアニストのゴースト(ボビー・ダーリン)、歌手のジェス(ステラ・スティーヴンス)、ゴーストをリーダーとするグループのメンバーたち。ゴーストとジェスが恋人になり、彼女が歌手としてグループに加入していく過程と、ゴーストがグループから脱退し、ジェスとの関係も終わりをむかえるストーリーが語られていく。
しかし、映画のラストでは曖昧な宙吊りの結末がまっている。グループともジェスとも決別したゴースト。だが、ゴーストはジェスと再会して、そのうえ酒場で演奏をしているグループのメンバーたちとも再会する。ゴーストはグループに過去の身勝手な行動を謝罪するが、メンバーたちは受け入れず、その場から去るようにいい返す。だがゴーストはその場に直立したまま居つづける。
グループは中断していた演奏を再開するが、ジェスはグループの演奏とは別の曲、かつてゴーストも含めたメンバーで演奏した曲を突然歌唱しはじめる。ジェスの声が響きはじめると、ステージから一人のメンバーが降りてきて、彼女の歌にあわせサックスを吹きはじめる。グループは困惑するも、すぐに彼女が歌っている曲へと演奏が変更される。
そんななか、かつてのリーダーであるゴーストはその様子を直立で見つめつづけている。演奏は続くが、あるときジェスはふいに歌唱をやめる。少しの時間があり、カットが変わると、その場にいた人物たちが引きのショットで捉えられ、そのまま映画は終わる。
一度は破綻してしまった人物たちの関係性が新たにやり直されるのか、それともそうではないのか。その判断は留保され、わたしたち観客の想像力にゆだねられる。わたしは見るたびにこのラストシーンの人物たちの立ち姿や互いにまなざしを投げかける様子に胸を打たれる。
このシーンの強度は、どのような実際の試行錯誤のうえに生まれたものなのだろうか。しかし、その真意を故人であるカサヴェテスに尋ねることはできない。
マーガレット・ヘリック・ライブラリーでの脚本の調査
2022年の6月、わたしはアメリカのロサンゼルスにある映画図書館、マーガレット・ヘリック・ライブラリーで『トゥー・レイト・ブルース』の脚本の資料調査をおこなった。同ライブラリーは、毎年アカデミー賞(オスカー)を授与しているアメリカ映画芸術アカデミーが運営する、ハリウッド映画にまつわる膨大な一次資料をアーカイブした図書館だ。
当時はまだコロナ禍がおさまっておらず、渡米と帰国に煩雑な手続きが必要だったこと、図書館のスタッフにコロナ罹患者がでたことでアポイントメントの一部がキャンセルになったことなど、トラブル続きだったが、脚本の調査では思ってもみない成果が得られた。『トゥー・レイト・ブルース』の脚本を調べてわかったのは、何度も改稿された脚本の各バージョンや、さらに脚本最終稿と実際の撮影のあいだですら、さきほどしるしたラストシーンの結末とそれにともなう俳優たちへの演出が段階的に変化していったことだった[★6]。

最終稿を含むいくつかのバージョンでは、ジェスをその場から立ち去らせて、ゴーストにそれを見つめさせるという演出が想定されていた。それに対して、実際の作品のラストシーンでは、上述のとおりジェスやゴーストをその場にとどまらせて、人物たちの行末を曖昧にさせ、映画を終わらせるという演出が選択されていた。まず、この選択が簡潔明瞭な展開や結末を是とする当時のハリウッドのあり方にあらがうことを意味するのは明らかで、のちに本格的にインディペンデント映画へと進むカサヴェテスのあり方を予告するものだと言える。
ただ、それよりも重要なのは、この選択にカサヴェテス固有の映画に対する態度=俳優重視の映画づくりの姿勢が現れていることだ。脚本から撮影の段階にともなうこの変化は、人物を立ち去らせ、それを別の人物に見つめさせるというエンディングではなく、人物たちをその場にとどまらせ、その場に立っている人物の立ち姿や他の人物たちを見ているまなざしの双方向的な力学を重要視してスクリーン上に残す選択であったと整理できる。
物語の明確な結末によるカタルシスではなく、その場に残された人物たちのまなざしや身振りからにじみ出る、曖昧で解決し得ない感情を観客の心に残し続けること。この点にこそ、「人間のありのままの絶対的な感情的真実」[★7]を映画で描こうとしたカサヴェテス独特の映画づくりの姿勢が反映されていると、わたしは考える。もちろん、人間的な情緒を小気味よいカットとアクションによって断ち切っていく手法も、アメリカ映画が築いてきた魅力のひとつである。しかし、カサヴェテスはそれとは異なる道を選んだ。その選択の痕跡は、脚本という制作の記録に明確に刻まれていた。
つまり、カサヴェテス独自の「映画づくりの姿勢」は、脚本執筆や撮影の紆余曲折に色濃く表れており、その過程で生じた試行錯誤や決断の痕跡が、残された資料のなかに刻まれている。そして、それらの資料を読み解き、「制作者のまなざし」を探ることで、彼が映画をどのように構築し、何を描こうとしたのかが浮かび上がってきたのだ。このようにして、アメリカでの調査は、カサヴェテスの映画への理解をあらためて深める機会になり、『トゥー・レイト・ブルース』のラストシーンに漂う独特の感触を捉え直す契機となったのである。
制作者のまなざしを探る
それにしても、日本での制作者たちへのインタビューの経験がなければ、この『トゥー・レイト・ブルース』論のようなアプローチには行き着かなかったのではないかと思う。作品が作りだされる過程にさかのぼることで、そこにどのような固有の「映画づくりの姿勢」があったかを見いだす。
いま振り返れば、三宅監督へのインタビューと『トゥー・レイト・ブルース』の脚本の調査は明確な線となって自分のなかでつながっている。脚本の調査は、わたしにとってあたかもすでに亡くなっているカサヴェテスにインタビューするかのような経験であった。プロであっても、制作者たちには実際の撮影現場や編集段階でさまざまな躊躇いと決断がある。それらがどのように絡まりあい、最終的にひとつの映画作品として完成したかを問いかけるというインタビューでの試みは、自分の研究手法にも大きな変化をもたらした。
このことによって、自分と映画のあいだにかつてあった埋められない距離は、むしろポジティヴで喜ばしいものへと変わった。いまでは、その距離は埋められるべきものではなく、その距離を探り、確かめ、考えることが、研究者としてのわたしなりの(おおげさに言えば「固有の」)映画への向き合い方なのだと感じている。いまでもカサヴェテスの映画を見ると、何がすごいかわからないが圧倒される気持ちは変わらない。でも、カサヴェテスたちが見るものを圧倒するエネルギーとエモーションを作りだすために、さまざまなトライ&エラーを重ね、その果てに映画をつくっていたことが、少しはわかるようになった。そして、そのプロセスを愚直に記録し言葉にすること、つまり「制作者のまなざしを探る」ことこそが、研究者としてのわたしがすべきことなのだ。
映画を見る多くの人は、実際の映画制作者ではない。しかし、映画がどのようにつくられたのかという「制作者のまなざし」を持って映画を見ることはできる。そして、そのような視点で映画を見ることは、単に映画の内容を解釈するのとは異なる次元で、自らの映画体験そのものを更新する豊かな行為となるはずだ。
制作者と観客を出会わせること、あるいは別の形で再び出会わせ、新たな視点を生み出すことは、人文学の研究者の重要な役割のひとつでもある。このエッセイや今後の研究が、多くの観客や読者のそのような経験に寄与できるならば、これ以上の喜びはない。
★1 レイモンド・カーニー『カサヴェテスの映したアメリカ』、梅本洋一訳、勁草書房、1997年、ⅷ頁。
★2 過去におこなったインタビューの書誌情報は以下の通りである。黄也、堅田諒「撮ることの倫理──三宅唱監督の一〇年間の映画製作をめぐるロング・インタビュー」、『層──映像と表現』、北海道大学大学院文学研究院 映像・現代文化論研究室編、Vol. 13、2021年、4-32頁。URL= https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/81017/1/torukoto.pdf)
堅田諒、黄也「暴力と映画的真実──真利子哲也監督インタビュー」、『層──映像と表現』、北海道大学大学院文学研究院 映像・現代文化論研究室編、Vol. 14、2022年、4-22頁。URL= https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/84711/1/14_01_4-22.pdf
堅田諒、黄也「誰も見ていない時間と映画の温度──今泉力哉監督ロングインタビュー」、『層──映像と表現』、北海道大学大学院文学研究院 映像・現代文化論研究室編、Vol. 15、2023年、33-62頁。URL= https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/88604/1/15_02_p33-62.pdf
堅田諒、三浦光彦、黄也「忘れられた記憶、現実の拡張──小田香監督インタビュー」、『層──映像と表現』、北海道大学大学院文学研究院 映像・現代文化論研究室編、Vol. 16、2024年、4-25頁(URL= https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/91413/1/16_01_P4-25.pdf
これまでともにインタビューをおこなってきたのは、現在は浙江伝媒学院電影学院講師の黄也さんと、北海道大学大学院文学院博士後期課程の三浦光彦くんである。二人にあらためて感謝申し上げます。
★3 蓮實重彥、濱口竜介「さいわいなことに、濱口さんも役者が好きなんです」、『ユリイカ』2018年9月号、青土社、45頁。
★4 黄也、堅田「撮ることの倫理」、11-12頁。
★5 同前、11頁。
★6 この資料調査をもとにした論考を発表しているので、詳細は以下を参照していただきたい。堅田諒「立ち去りと留まり──ジョン・カサヴェテス『トゥー・レイト・ブルース』におけるラストシーンの生成過程とその演出について」、『層──映像と表現』、北海道大学大学院文学研究院 映像・現代文化論研究室編、Vol. 15、2023年、244-255頁。URL= https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/88618/1/15_13_p244-255.pdf
★7 Ray Carney, ed. Cassavetes on Cassavetes. London: Faber and Faber, 2001, p. 159.


堅田諒