【ZEN大学共同講座】理系的「アヴァンギャルド」へ向けて──加藤文元×三宅陽一郎×中澤俊彦「果てしない数学の世界」イベントレポート
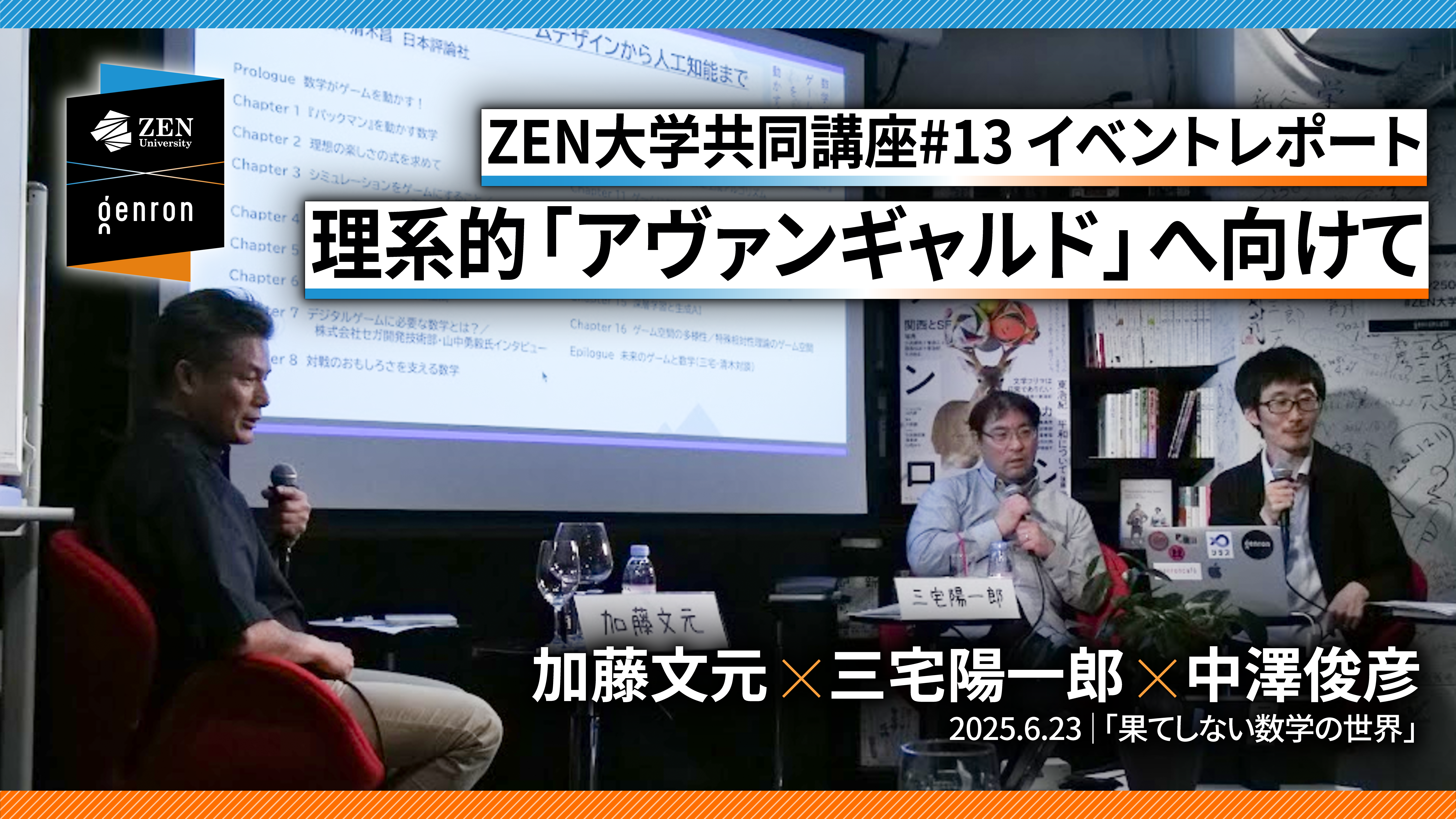
2025年6月23日、ZEN大学とゲンロンの共同公開講座の第13弾がゲンロンカフェで開催された。数学者の加藤文元と、ゲームAI開発者の三宅陽一郎を迎え、ZEN大学スタッフの中澤俊彦が聞き手を務めた。
テーマは数学とゲーム開発。世間では「なんの役に立つのか」と言われることも多い数学だが、じつはゲーム制作になくてはならない存在だ。これから歴史を変えていくようなゲームは「数学のセンス」から生まれるかもしれない……。議論はゲームの最前線から数学の最前線へと展開し、さらにはベルクソンや道元の哲学にまで及んだ。この記事ではそんなアツい議論の一部をレポートする。
加藤文元×三宅陽一郎 司会=中澤俊彦 果てしない数学の世界──人工知能、ゲーム、そして新たな数学へ
URL = https://shirasu.io/t/genron/c/genron/p/20250623
数学は役に立つのか
2025年5月に『数学がゲームを動かす!』を刊行した三宅。数学者である加藤はとても興味深く読み、すぐにX上で反応をしたという。とはいえゲーム制作というと数学よりもプログラミングが思い浮かび、「数学がゲームを動かす」と聞いただけではどういうことかピンとこないひともいるだろう。使われている場面を想像しやすいプログラミングに対して、数学のほうは抽象的なイメージがある。プログラミングの背景に数学の論理があるのだとしても、「数学がゲームを動かす」と言われると少し違和感を覚える方もいるかもしれない。司会の中澤も、「このタイトルはほんとうにゲーム制作者の実感なのだろうか?」と思ったという。
けれども三宅によれば、「数学がゲームを動かす」は制作者としての実感が込められたタイトルだという。たとえば、高校や大学で数学を学んだ方なら触れたことがはずの「行列計算」は、ゲーム制作でとても重要な操作なのだそうだ。さらに『数学がゲームを動かす!』では、ちょっとしたダンジョンを作るための数学的仕組みが紹介されていたりする。むかし攻略したあのダンジョンの裏には数学が潜んでいたかもしれない……。そう考えると、数学にすこしずつ親近感が湧いてきそうだ。
数学が「現実」を作り出す?
もし数学がゲームを動かしているなら、ゲームのなかの「現実」は数学が作り出していることになる。当たり前のようだが、これはすごいことだ。加藤は『数学がゲームを動かす!』を読んで、ゲームの世界が数学で作られているなら、この現実世界も数学によって作られているのではないか、と思ったほどだという。
もちろん、ゲームの世界と現実の世界はちがう。そもそも数学は、わたしたちが生きるこの世界を抽象化して記述するために生まれた学問だ。ゲームの世界においてはたしかに「数学があって現実がある」けれど、この世界においては逆に「現実があって数学がある」。
それでも、ゲームの中のあのフィールドやあの風景はたしかに数学によって作られている。数学にはひとつの「現実」を作る力があるのだ。だとすると、ここでひとつ疑問が湧いてくる。数学に「現実」を作る力があるなら、わたしたちの生きる現実世界とはまったくべつの「現実」をゲームの中に作ってみてもいいのではないか……? たとえば3次元のユークリッド空間ではなくて、空間がよじれたような非ユークリッド的なゲームがあってもいいのではないか……?
ゲームのアヴァンギャルドと数学の「センス」
三宅がゲーム会社に入ったのは、まさにこの「現実とはちがう現実」を表現するゲームを作るためだったという。ところが当時もいまも、ゲーム制作は「3次元の空間で剣を振る」というような現実的なフォーマットを基本にしていて、実験的なゲームはなかなかつくれない。その理由について三宅は、ゲーム制作環境いるが3Dゲーム制作に特化して、ゲーム制作者のスキルが制作環境上に固定化している、ゲーム制作者に高度な数学的知識を有した人材が多くない、などの要因があると語った。現実とはちがう世界を想像するためには「数学的センス」が必要なのだ。逆にゲーム制作のスキルは低くとも数学のスキルがあれば新しいゲーム空間を作り出すチャンスがある。
ここでピンと来た方がいるかもしれない。そう、三宅の目指すゲームは芸術に近い。なかでも、絵画における抽象画や音楽における無調のような「アヴァンギャルド」を目指していると言えるだろう。抽象画も無調音楽も、それまであたりまえとされてきたルールから逸脱することで生まれた。三宅にとって数学はまさに、ゲームの「あたりまえ」から逸脱するための道具箱なのだ。
デジタルゲームの歴史はまだ浅い。絵画や建築と比べると、100分の1、1000分の1ぐらいだろう。けれども、だからこそゲームにはいろいろな未知の可能性がつまっている。これからのゲームは4次元空間を描くようになるかもしれない。ゲームがわたしたちの生きる現実にとらわれる必要はまったくないのだ。
数学のアヴァンギャルドと「汚い数学」
三宅の言う「新しいゲーム」の実験の一方で、数学それ自体も更新される必要があるのではないか。そんな「新しい数学」の可能性をさぐったのが、加藤の新刊、『数の進化論』だ。加藤はそのなかで、新しい数学は「汚い数学」になるのではないか、と語っている。どういうことだろうか。
数学というと、「美しい方程式」とか「きれいな数式」といった、美的なフレーズをイメージする方も多いのではないだろうか。どうやら数学には、複雑な現実を正確に、スパッと、美しく表現することが求められているらしい。であれば、数学が「汚くなる」のは望ましいことなのだろうか。中澤もこの点について加藤の真意を追及する。
だが数学の世界と異なり、現実世界は人間の感じる「美しさ」のためにはできているわけではない、と加藤は言う。山や川はゴツゴツしていたりクネクネしていたりして、とてもなにかひとつの「美しい」法則にしたがっているようには見えない。もしゲームと同じように数学にも「アヴァンギャルド」がありえるとしたら、現実の複雑さやあいまいさ、つまりは「汚さ」を受け入れることから始まるのかもしれない。
数学、時間、ベルクソン、そして道元
議論はここから哲学的な方向へ進んでいく。加藤は、たとえば人間の感じる時間も「汚い」現実のひとつだという。そしてフランスの哲学者アンリ・ベルクソンの時間論を例に出して、「人間はひとつの線的な時間にただしたがっているわけではなく、じぶんで能動的に、主観的な時間をつくりだしているのではないか」と語る。ある出来事にずっとむかしの記憶がとつぜん結びついたりして、思い出し笑いをしたり恥ずかしくなったりするのは、まさにこの主観的時間のせいだ。
三宅はそこにかさねて、そうした主観的な時間こそが人間の知能の本質なのではないかと語る。いまのAIはまだ線的な物理時間のなかでプログラムされている。でも、もしAIがじぶんで主観的な時間をつくれるようになったらどうだろう。そのときにこそ、AIは人間の知能に近づいて、ひとつ上の段階に行けるのではないか。そのためには、あいまいな主観的時間をモデリングできる「汚い」数学が必要になるのではないか。
イベントではさらに哲学的な話題が盛り上がり、道元の時間論の話にまで広がった。終盤には三宅が人間の主観的時間の仕組みをホワイトボードに描き出したりと、たいへんアツいトークが繰り広げられた。数学とゲームと哲学が超次元で合体する、ここでしか聞けない「逸脱」にあふれたトークは、ぜひアーカイヴ動画を視聴していただきたい。(田村海斗)







