【ZEN大学共同講座】トランプ2.0から考える、これからの大学のあり方──西田亮介×三牧聖子×山本圭「トランプ2.0と民主主義」イベントレポート
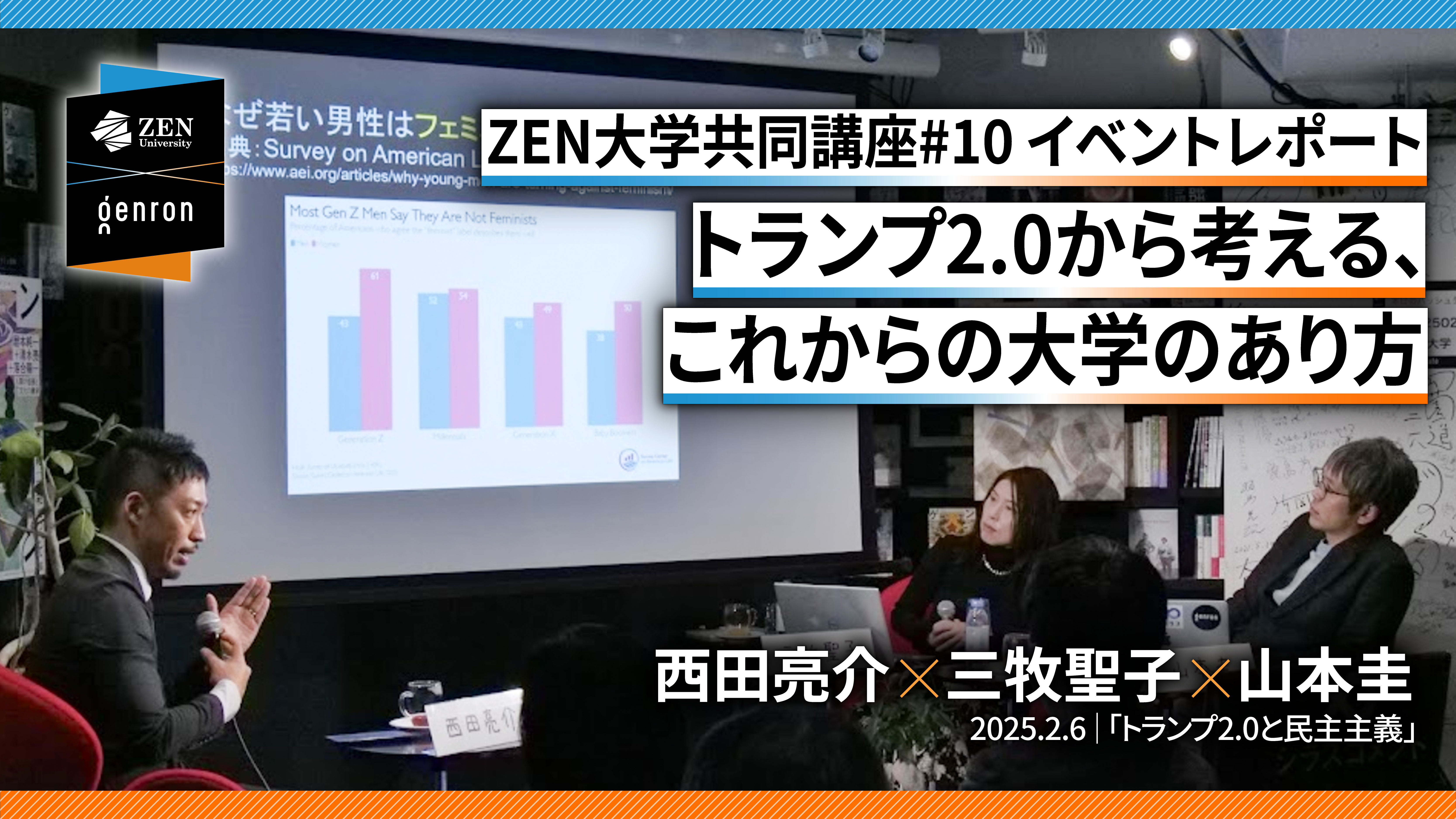
2025年2月6日、ゲンロンカフェに国際政治学者の三牧聖子、政治学者の山本圭、そして社会学者の西田亮介を迎え、ZEN大学とゲンロンの共同公開講座の第10弾が開催された。議論のテーマはついに2期目が始まったアメリカのトランプ政治と現代の民主主義である。いまはバイデン政権下で自明とされていたリベラル的価値観が崩れ、民主主義とはなにかという共通理解が失われていくかのように見える。しかし、実際のところはどうなのだろうか。共和党の反DEI政策やイーロン・マスクの動向についての議論が盛り上がるなかで、最終的に話題の中心になったのは、意外にもこれからの大学のあり方についてだった。本稿ではその一部をレポートする。
西田亮介×三牧聖子×山本圭 トランプ2.0と民主主義──2025年、選挙と政治は変わるのか
URL= https://shirasu.io/t/genron/c/genron/p/20250206
トランプ2.0、DEI、そして大学批判
イベントは三牧によるここまでのトランプ2.0、つまり二期目のトランプ政権の要点の確認から始まった。トランプ2.0は、「常識の革命」を掲げている。トランプは前任のバイデンが推進していたジェンダーや人種に基づくダイバーシティ政策を批判し、そのような政策ではなく、「完全な実力主義」を実行することこそが公平な社会を作り上げるのだと主張している。
トランプだけではない。副大統領のJ・D・ヴァンスはジェンダーや人種に関する理論を教える大学を厳しく批判する。そこでキーワードのように扱われ、批判されている概念がDEI(Diversity, Equity, Inclusion=多様性・公平性・包括性)である。
DEIは、歴史的に差別を被ってきたマイノリティの公平な扱いやその社会包摂を求めるイニシアティブである。この考え自体は、おそらく多くの人が同意できるものだろう。だが、トランプやヴァンスら共和党員に言わせれば、この理念こそが現在の米国の分断の原因なのだ。
たとえば、現代のアメリカの大学で教えられている「批判的人種理論(Critical Race Theory)」は、「人種的な差別はいま目の前で起きているものだけではなく、社会を形作る制度や法律に歴史的に埋め込まれているものなので、そうした制度的で一見気づきにくい差別も意識し、改善していかねばならない」とする理論である。しかし、共和党は、このような理論は白人の子どもに罪悪感を植え付けることになるとみる。なぜなら、彼らは過去の人種差別的な制度や法律の設計や採択には直接関わっていないのに、白人に生まれたというだけでその責任を背負わされるからだ。
DEIや批判的人種理論は、マジョリティとマイノリティを切り分け、前者に一方的に責任を負わせることで、アメリカ市民を属性ごとに分断させていやしないか。共和党はそのように問うているのだと三牧は分析する。そして、そのようなDEIや批判的人種理論を先頭に立って教えている大学やその教授は、米国にとっての「敵」なのである。
大学はほんとうに市民の「味方」になれているのか?
トランプ政権の大学敵視を象徴し、世界の研究者たちを騒がせたのが、政権の圧力のもと、アメリカ国立科学財団が、GenderやRacismといったDEIに関わるキーワードが入っている研究について助成対象に値するかの調査を始めたというニュースだった。今後、事態がどのような展開になるかは予断を許さず、三牧や山本は、このようなキーワードを含む研究が今後公的な支援を受けられないとすると、かなりの研究が止まってしまうのではないかと危惧する。三牧の紹介するDEIのキーワードのリストには驚くべきものも入っている。その詳細はぜひアーカイブ動画でご覧いただきたい。
トランプもヴァンスも、大学は国家の敵であると主張している。しかしその一方で、大学や教授は「味方」なのか、じっさいに大学で教えている立場として、三牧と山本はどう感じているのかと西田は鋭く問いかけた。大学は社会において、過去に担っていたような「権威」の役割をもはや担えていない。むしろYouTuberのほうが知的権威を担っているのではないか。
三牧はこれについて、たしかに西田の言うとおり、アメリカの大学ではリベラルであることが当然視され、教員や学生が政治的・宗教的に保守的な議論を提起すると、多様性として尊重されるのではなく「あなたはわかっていないのだ」と一蹴されてしまう傾向があると指摘する。保守的な教員や学生にとって大学は「味方」になりづらい。
山本も、昨今日本では社会から大学に注がれる目線が厳しくなりつつあると指摘する。しかし一方で、大学教授は人気商売ではないのでYouTuberなどの人気を基盤にした知的権威とは別物なのではないか、大学には別の役割があるのではないかと応答した。のちに再び触れるが、本イベントでは新たな大学人像を探る西田と古典的な大学像に可能性を見出す山本のあいだの対立軸がさまざまな場面で明らかになった。
ポピュリズムではなくプレビシット主義?
では山本は、トランプ2.0、ひいては21世紀の民主主義についてどのように考えているのだろうか。トランプ政治はしばしば「ポピュリズム」であると言われる。だが、山本はトランプ2.0をポピュリズムと捉えないほうがよいと語る。いったいどういうことだろうか。
政治学の世界では、ポピュリズムはたしかに批判されることが多い。けれどもあくまで政治の中心は人民(people)にある。究極的には、ポピュリズムにおいても政治を変えるのは人民なのだ。だが、二期目のトランプ政治の中心にいるのは人民だろうか。むしろ民衆は、トランプの大統領令の承認やイーロン・マスクのXでのポストに拍手を送って称賛するだけの存在になってしまってはいないか。
このような政治のあり方を、山本は「プレビシット主義」と呼ぶ。プレビシットとは人民投票という意味だが、プレビシット主義は、より広く言って「指導者による決断や提案に、民衆が人民投票や喝采を通じて承認を与えること」を指す。ここで政治の中心に立つのは、もはや人民ではなく、さまざまな権限を巧みに用いて政治を進める指導者である。そこでは市民は指導者の決定に拍手を送って承認を与えるだけの存在にすぎない。
このように考えたとき、トランプ2.0はまさにプレビシット主義と言える。そしてプレビシット主義は、政治を変えるのは市民ではなく指導者であるという点で民主主義とは相性が悪い。さまざまな定義の仕方があるものの、民主主義とは一般市民の声が政治の中心にあるべきだとする考えだからだ。この点でプレビシット主義はポピュリズムよりもさらに後退した民主主義の形態であると山本は述べ、危機感を隠さない。
大学はどうすれば市民の「味方」になれるのか?
後半では、このようなトランプ政治やプレビシット主義、さらには日本政治についての熱い議論が交わされた。だが、意外にも最終的に話題の中心になったのは、登壇者それぞれの大学観だった。変わりゆく民主主義において大学のありかたを問うのは、三人がいずれも大学人であるからのみならず、教育が社会に果たす役割に重きを置いているからだろう。
さきほども述べたように、現代の民主主義では、大学がかつてのような知的権威を担えなくなり、むしろ批判の対象になってしまっている。それはトランプ2.0においても、日本においても当てはまる。
西田はYouTubeやポッドキャストといったメディアが知的・政治的な議論の中心になりつつあると語り、そのことに大学の研究者はほとんど気づいていないのではないかと指摘する。このような変化に対応できていないからこそ、大学は過去のような知的権威としての役割を失い、トランプやヴァンス、あるいは市民による批判を許しているのではないか。
大学や知識人も市民に信頼されてはじめて機能する。しかしその信頼は失われてしまった。活字もなかなか読まれない。だからこそ、大学人はYouTuberにも学んで、自分たちのほうから市民に近づいていって、信頼を取り返さなければならない。西田はそう語る。
これに対して山本は、政治メディアの変化に大学人がついていけていないという危機感には共感する一方で、自分は西田とちがって、やはりオールドな大学のあり方に執着があるのだと語る。ふたりの議論を受けて三牧は、YouTube的な新しいメディアに関わろうとする大学人も大事だが、活字文化を守ろうとする大学人もおり、両者ともに重要なのではないかとまとめた。
このように、今回のイベントでは図らずも大学人たちの大学観のちがいが明らかになった。トランプ2.0のなかで激しい批判にさらされる大学はいったいこれからどこに向かっていくのだろうか。たとえば本イベントの共同開催であるZEN大学は、「日本初の本格的なオンライン大学」という形で、これからの新しい大学のあり方という問いに答えようとしている。こうした最先端の動きも踏まえたうえで、本イベントは政治に関心のあるひとだけでなく、大学に携わるひとや、これから大学に入ろうとしているひとにとっても大変重要な内容になっている。ぜひアーカイブ動画を購入いただき、全編を視聴していただきたい。(田村海斗)

西田亮介×三牧聖子×山本圭 トランプ2.0と民主主義──2025年、選挙と政治は変わるのか
URL= https://shirasu.io/t/genron/c/genron/p/20250206





