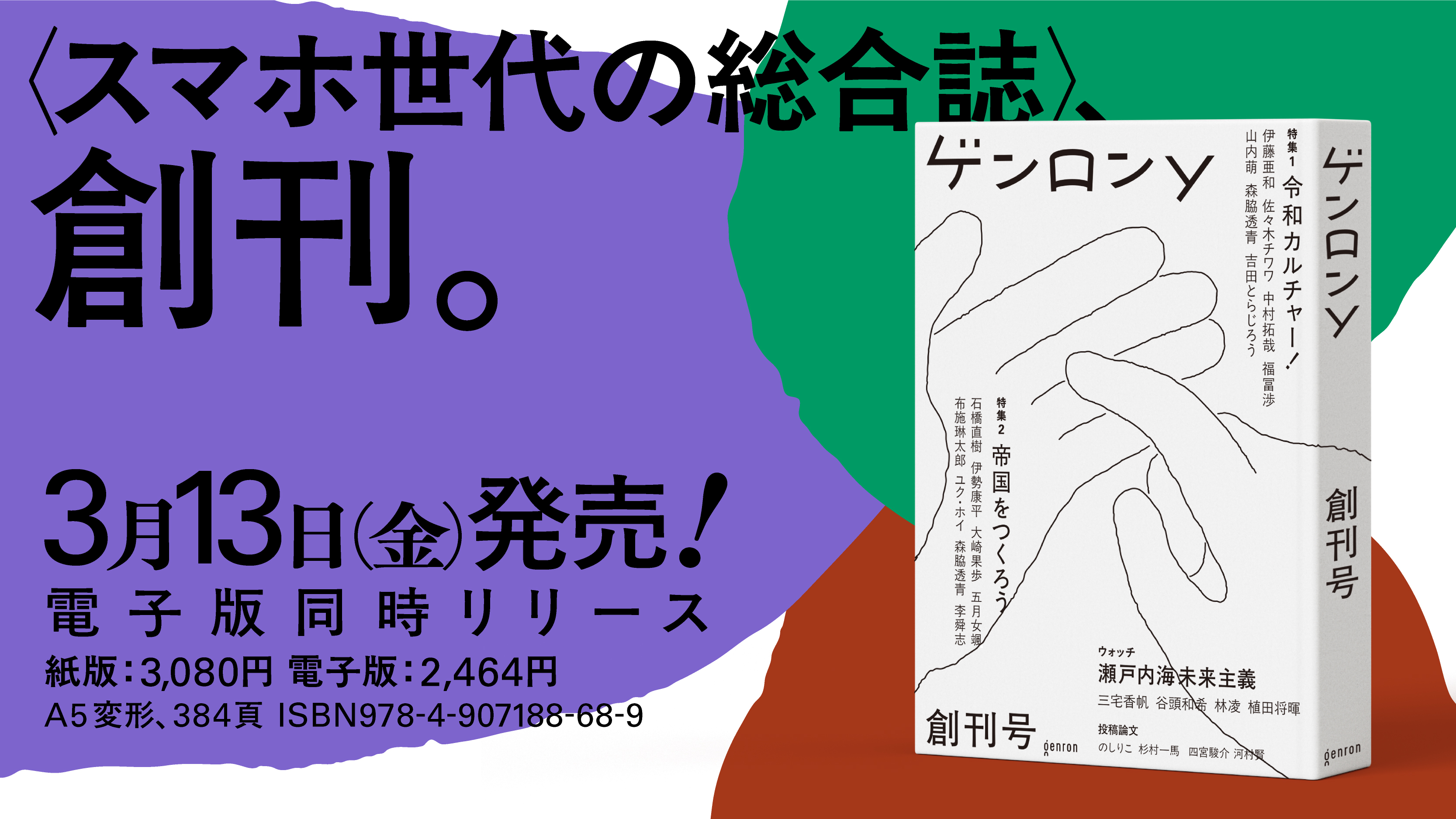虚体、死体、そして〈外〉へ ── 21世紀のダンスの理念に向けて|鴻英良

鴻さんは、知的な喜びを味わうことに貪欲で、ジャンルも年齢も関係なく、面白い試みを評価するひとでした。鴻さんに学んだり励まされたりした演劇人、研究者、批評家は少なくないでしょう。わたしも、思想や作品を丁寧に追い、熱く語る鴻さんの姿に、人間にとって知とはなにか、そのあり方を学びました。
それだけでなく、鴻さんはさまざまな身体を動かすワークショップへの参加や、ギリシア劇の舞台を巡る旅など、言葉にとどまらない知のあり方を探っていました。ドイツの国際演劇祭ラオコオンの芸術監督を務めるなど、国際的に活躍しながらも、在野を貫いた知識人です。演劇だけでなく、タルコフスキーやカバコフら、ロシア文化にも造詣が深い方でした。
鴻さんの熱さと思考が、この論考を通して読者に伝わり、新たな思考を導くことを願います。鴻さん、安らかにお休みください。(上田洋子)
私にとつてのレーニンは、彼の希求する「国家の死滅」を「彼自ら」が強化した「党」そのものによつて阻止してしまつた自己矛盾に対する「見せしめ」のため、赤い広場の前に無残に「曝される」ことになつた悲劇のひとにほかなりません。そして、古い世代である私は、暗い悲哀感と名状しがたい憤懣につつまれながら、こう記せざるを得ませんでした。「党の自己否定のテムポこそ革命完成のバロメーターとなる──。」(『革命の意味』)
──埴谷雄高[★1]
嘔吐、このような感覚がいまも世界の根源的なところに存在している、これこそが20世紀の基本理念であると考えていたのは、「自同律の不快」という言葉を残した日本戦後文学の巨匠、『死霊』を書いた埴谷雄高(1910年生)、あるいは『ラ・アルヘンチーナ頌』を踊った舞踏家の大野一雄(1906年生)と同年代のフランスの哲学者・文学者のジャン・ポール・サルトル(1905年生)らであった。
このような感覚をどのように表明するかによって、この3人はまったく同じであったとは言えないまでも、共通の自己認識を持っていたのではないかと私は疑いはじめている。これらの現象が起こったのは偶然かもしれないが、それは、世界的に見ても、1930年代から1950年代のこと、つまり、第二次世界大戦が終局した1945年を挟んでのことであった。ということは、第二次世界大戦の前後に彼らが考えていたことが彼らの表象には刻印されていると、ひとまずは想像されうるのだ。
いま、われわれが、21世紀へと突入せざるをえないという現実について考えなければならないときに、20世紀総体は改めて歴史的展望の中で位置づけられる必要があり、埴谷雄高や大野一雄たちが提示してきた身体に関する表象はきわめて大きな意味を持ってくるのではないか。私はそれを、「虚体、死体、そして〈外〉へ」という幽霊的身体と密接にかかわるテーマ系に引き寄せつつ、日本の戦後演劇、むしろ、日本の戦後のダンス、舞踏を中心に据えて考えていきたいと思うのである。
重力と虚体
前述のような問題系が私の前に立ちはだかりはじめたのは、比較的最近のことである。それはつまり、数年前に横浜のBankART Studio NYKで川口隆夫のダンス『大野一雄について』を見たのがきっかけだった。そのとき川口隆夫はローラースケートに乗り、空き缶やらなんやら、全身に大量のガラクタを身に纏った姿で観客が蠢くホールのなかにさっそうと出現し、観客たちのあいだをすり抜けながらやや不器用に動いていた。川口隆夫は、そのオブジェたちとともに巨人のような存在感を放散していて、その姿は空間を圧倒していた。そこには騒々しくも猥雑な、と同時に、戦後の廃墟のような記憶が、いや廃墟そのものがどよめいているような感じがして、それはまさに、大野一雄が生きた戦後の匂いのなかにわれわれを引きずり込むといったようなダンス・パフォーマンスだった。
やがてわれわれ観客は別のホールに移動させられ、先ほど、疾風のように観客の前から姿を消した川口隆夫がふたたび登場するのを待っていた。すると川口隆夫は、今度は大野一雄が『ラ・アルヘンチーナ頌』で着ていたような純白のドレス姿で登場してきた。そして、大野一雄に捧げる形でダンスを踊りはじめたのであった。川口隆夫は大野一雄を正確になぞるために無数の資料に当たったのだという。そして、大野一雄について、大野一雄のように踊りつづけようとしたのであった。このようなダンスのことを俗にコピー・ダンスと言うのだそうだが、そこで行われたコピー・ダンスは私には、私が知っていた大野一雄のダンスとはかなり違って見えた。
川口隆夫のダンスがその終局を迎えようとするころ、私はひとり心のなかで重力という言葉をつぶやいていた。それからしばらくして、〈虚体〉という言葉が浮かんできた。そして、ある光景が思い出されてきたのである。
ふむ、それは或るビルディングの六階だった。時刻は夕方で、暮れかかっていた。薄紫色から濃い鼠色へ移ってゆく宵闇が窓際から這い寄っていた。[……]その事務所は、他で開催されている或る大会の連絡場所になっていたので、時々、電話のベルが鋭く鳴った。おお、そのときの情景を僕ははっきりと憶えている。僕は、彼が何を望んでいるか、を訊いたんです。薄闇のなかで、彼は口端をちょっと歪めたっけ。ふむ、それは、それが突拍子もない夢想で、真面目に受けとられなくても好い、という印しだった。窓の外の拡がった闇を眺めながら、彼はいったんです。
「この窓の外が、引力のない真空の拡がりだとして、身を投げたらどうなるでしょう?」
「落ちないことは確かだね」
「すると──どうなるんです?」
「ふむ、永遠に……或る一点に止っているだろう」
「おお、貴方は……貴方自身はそうしていますか」
「いや、僕は動くよ」
「動く……? 何によってです?」
「ふむ、つまり、僕自身の傾向と重みによって──」
「そう、私もそんなふうに自身を調べてみたかったんです」
僕達は窓の外の深い闇を眺めつづけていた。下の街路から何とも知れぬ騒音が聞えていた。遠くの広告燈が忙しげに明滅していたっけ。僕は、瞬間眼を閉じると、直ぐ見開いてみた。涯も知れず拡がった漆黒の闇が、この薄暗い部屋の窓際に佇んでいる小さな二人の人物を凝っと見据えているような気がしたんです。僕には、そのとき、或る想念が非常に明瞭になってきたっけ。[★2]
これは埴谷雄高の『死霊』の断片である。精神病院の岸博士に対して、そこの患者である矢場徹吾の飛躍的な思索方法について、矢場の友人の首猛夫が語ったエピソードなのだが、私はこのエピソードを思い浮かべつつ、その窓ガラスの向こう側に投げ込まれた人間は果たしてどのようになるのだろうかと考えていた。そしてそこで蠢いているものを凝視していたのであった。するとやがてそこで蠢いているものが、それほど多い回数ではなかったが、かつて幾度か見たことのあった大野一雄の舞踏のように思えてきた。そして、「引力のない真空の拡がり」という言葉を「重力のない」と読みかえつつ、ダンスにとって重力がないとはどういうことかと考えたのである。
舞踊において使われる主要な運動単位は、歩きぶりと跳躍と回転であり、腕と脚と頭と胴部の身振りである、とは舞踊の教科書にある言葉だが、旋回し、跳躍するとき、どれだけ早く回転し、どこまで高く舞い上がることができるかはダンスの美の根幹をなしている。それはいかにして重力に逆らって飛翔するかということであり、逆に言えば、ダンスの身体の美を形成しているものが重力、もしくは重力との拮抗関係だということなのである。だから、身体の重みもまた、多くのダンサーたちによって身体の美を逆説的な形で生み出す重要なエレメントとされてきたのだ。
しかし、引力のない真空の拡がりのなかに私が幻視した物体のように、軽やかに舞いながら空間を浮遊する大野一雄の動きは、そのような意味での旋回でも飛翔でもなく、そこには重力への抵抗もそれとの拮抗関係も存在していない。むしろ重力の不在を感じさせるのである。跳躍し飛翔するのでも、重力に逆らって舞うのでもなく、重力の不在のなかで漂うこと、そのようなことが大野一雄の動きによって実現されているように私には思える。そのとき大野一雄の身体もまた重みを失い、その動きは、実在そのものを感じさせることのないもの、つまり実体を欠いたものとして出現してくる。それをわれわれはひとまずは、幽霊的身体と名づけることにしよう。
大野一雄の幽霊的身体
それにしてもなぜそのような存在となることが目指されたのか。それこそが大野一雄の舞踏の本質にかかわることなのだが、このことを考えるために、まずは、大野一雄の舞踏に対するこうした私の印象がそれほど特異なものではないということを確認すべく、幾つかの発言を挙げることにしよう。
次に引用するのは2010年6月1日の大野一雄の死に際して、写真家の細江英公によって読み上げられた弔辞「大野一雄先生へのお別れのことば」からの一節である。少し長くなるがそのまま引用する。
1995年の12月のことです。埴谷雄高さんは病床でご自分の創作『死霊』九章の最終執筆の最中だったのですが、大野一雄さんの来訪を快く受けてくださり、お話をして下さいました。この事は、『死霊』九章の“〈虚体論〉大宇宙の夢”という壮大な宇宙論を展開する文学者と身体と「胎児宇宙」を表現する舞踏家との歴史的な接触といっていいかと思います。そのあと、埴谷雄高さんの枕元で大野一雄さんが即興の舞踏を捧げられましたが、舞踏のあと、埴谷雄高さんが“大野さん、あなたは、舞台に立ったとき、何もないところから、さらなる何もないところへ、誰もやったことのない未来に向かって第一歩を踏み出しています”と話されたことがとても印象的でした。[★3]
大野一雄の体の軌跡がこのように記述されるとき、大野一雄の体そのものもまた、何もないものとして宙を舞いながら、重力のない世界を漂うものとしてわれわれの前に現れてくるということが了解されてくる。そして、さらに言えば、埴谷雄高のこの感想は、『死霊』九章の津田老人の次のような独り言と相応するのであり、その同一性はきわめて興味深いものだ[★4]。
そこには次のようなエピソードが綴られている。「永遠から永遠へ真白なものが飛ぶように、あちらの側へ飛び移ってしまい」、いつの間にか掻き消えながらも、ふたたびやってきたものたち、黒服と青服の男と呼ばれる津田老人が幻視するこの幽霊的な存在によれば、あちらの入り口には、「汝、重さをもつことあらざるべし」と書かれているらしい。そこでは際限なく独語が続けられ、それがやむのは言ってはならない自己告白をうっかりしゃべってしまうときだという。なぜなら、人はそのとき、他者との対話がはじまる可能性を手にするからである。そして、「そこからはじめて[……]まったく他の何ものかからさらに他の何ものかへと超えつづけてゆくところの自己の尽きせぬ非自己から虚自己へ向って飛ぶ無限化がはじめてはじまります」[★5]というのである。
われわれは埴谷雄高と大野一雄をつなぐ細江英公の証言の内実を、『死霊』のこのようなエピソードによってさらに強固な形で確認することができる。つまり、私は埴谷宅で起こったことはまるで『死霊』のなかのエピソードそのもののように見えると直感したのであり、またそれゆえに、大野一雄の舞踏が『死霊』の世界と同一の思想と構造を持っているのではないかと主張しようとしているのである。後に私はこの思想と構造の同一性は何を物語るのか、どこから来たのか、どのような歴史的、文化的状況とかかわっているのかなどについて問題にしようと思っている。
建築家の磯崎新もまた、「はじまりから遊離した影のようだった」という文章のなかで、大野一雄は「俗の世界に人をかき分けても出てくるような人とは無関係で、私には虚焦点のような存在に思えていた」とその人柄を讃えたあとで、次のように書いた。
[……]みずからを影にしてしまう舞踏家は大野一雄さん以外知らない。見たことがない。日本語の古来の用法からすれば、影とは分身のことで、実体から遊離しているから、ぼんやりしたり、気配だけになったりする。大野一雄さんは舞台のうえで、そんな影になっていたのだ。[★6]
このような印象は、埴谷の生み出した〈虚体〉という概念、そうした身体的なあり方を大野一雄がその舞踏において実現していたのではないかと想像させるものであり、そこには幽霊的身体とでもいうべきものが出現していたと言い換えることができるかもしれない。そしてまた、ここでいう幽霊的身体とは、『死霊』のなかで語られている「理性的幽霊」の身体なのだ。「理性的幽霊」とは、「非人間的な幽霊」の言い換えであり、このような幽霊は、人間世界の幽霊とは違って、「人間の匂いがしないというばかりでなく、人間的な思考方法をとらないということ」だと『死霊』には書かれている。それは「怨恨的幽霊」でもなく、「なんだか血なまぐさい怨恨しか知らぬ、愚昧な、女性的な、東洋的幽霊」でもないのである[★7]。埴谷、細江、磯崎らの発言に依拠するならば、大野一雄の舞踏を見ているとき、われわれ観客はそのような幽霊との対話をしているとも言えるし、また大野一雄自身、そのような対話をしながらみずからの舞踏を踊りつつ、みずからもそのような気配として、みずからの身体から離脱していっているのだとも言えるかもしれない。
こうしていま、われわれは大野一雄の身体と〈虚体〉との関係の考察へ少しずつ近づきつつあるが、その前に、私もまた、大野一雄の舞踏を見ながら体験したひとつの思い出を最初に語っておくことにしよう。『ラ・アルヘンチーナ頌』をニ度目に見たとき(1986年、関内ホール)、私は二階席の最前列に座っていた。一階席に座っている観客たちの頭が、私には奈落に浮かぶ黒ずんだ浮きのように底知れず沈んでいくように思えた。私はどこか深い谷底に引きずり込まれていくような眩暈を感じながら、大野一雄の動きを目で追っていた。すると、遠くに見える大野一雄の体が、遠く奥深いところから薄暗い大きなホール全体へかけて、永遠から永遠に向かって飛ぶ真っ白なもののようにさっとかすめすぎながら、私に近づいてきたように思われた。その幻影の去り際、私はすぐ目の前の手すりにしがみつき、その真っ白なものの動きに引きずり込まれないように必死でこらえていた。眩暈がした。脚はすでに床を離れて浮遊していた。すでに制御不能の状態に投げ込まれた私の体は、恐怖と陶酔とに引き裂かれて行き場を失っていた。私もまた、多くの観客たちとともに、大野一雄の舞踏の特異性を感じていたのであった。だが、問題はそのような感覚を多くの人たちに呼び起こすような大野一雄の舞踏は、どのような経緯から生み出されてきたのかということにあるのではないだろうか。
虚体・幽霊・自同律の不快
まず、虚焦点のように虚自己へ向かう幻影のような感覚を、目撃者たちの身体のなかに呼び起こすこと、そのようなことが実現されるための方法的な契機についての推測からはじめてみよう。大野一雄は、最晩年の埴谷雄高の自宅に訪れた後、約1年後の丸地守によるインタビュー「宇宙論──埴谷雄高へ」のなかで、かなり早い段階から埴谷に興味を抱いていたと語っている。そこで、「埴谷さんの本は、ずっと以前読んだことがあって大変心惹かれたものです。1960年に、現代思潮社から『虚空』という本が出ていますが、その中の『標的者』と題されたエッセイが載っていて、そのエッセイの序詞の中に、印象深い詩があります」[★8]と語っているから、さらに早い時期に『死霊』を読んでいた可能性がある。私はその時期を特定する資料や論考を見つけることができていないが、しかし、大野一雄が1960年刊行の『虚空』に引きつけられたという発言は重要である。というのも、その数年後の1962年6月、大野一雄は土方巽作・演出のレダの会発足第一回公演に元藤燁子とともに出演するのだが、その公演を埴谷が見にきているからである。この公演について埴谷が雑誌『世界』(1962年8月号)で触れたことがきっかけとなって、埴谷と土方とのつながりが1962年にはじまる[★9]。つまり、翌年(1963年)と翌々年(1964年)の正月2日、埴谷は土方宅での宴会に呼ばれるのである。そうした関係のなかで、大野一雄が埴谷と話す機会があったかどうか、私は不明にして知らない。公演当日の打ち上げで何があったのかも私は知らないし、そこに誰が残っていたのかも私は知らない[★10]。ともあれ、大野一雄が埴谷の作品に関心を持っていたということは事実であり、だとすれば、『死霊』で展開されているさまざまな特異な概念について、埴谷の文章とともに考えたことは疑いえない。つまり、〈虚体〉とか〈自同律の不快〉といった概念についてである。
〈虚体〉と大野一雄の舞踏の身体との関連はなんとなく理解できるだろう。しかし、もうひとつのキー概念〈自同律の不快〉はどうだろうか。そもそもこれはどのような概念なのか。それは『死霊』では次のように説明されている。
彼が少年から青年へ成長するにつれて、少年期の彼を襲ったその異常感覚は次第に論理的な形をとってきた。彼にとって、あらゆる知識の吸収は彼自身の異常感覚に適応する説明を索める過程に他ならなかった。それは一般的にいって愚かしいことに違いなかったが、⦅俺は──⦆と呟きはじめた彼は、⦅──俺である⦆と呟きつづけることがどうしても出来なかったのである。敢えてそう呟くことは名状しがたい不快なのであった。誰からも離れた孤独のなかで、胸の裡にそう呟くことは何ら困難なことではない──そういくら自分に思いきかせても、敢えて呟きつづけることは彼に不可能であった。主辞と賓辞の間に跨ぎ越せぬほどの怖ろしい不快の深淵が亀裂を拡げていて、その不快の感覚は少年期に彼を襲ってきた異常な気配への怯えに似ていた。それらは同一の性質を持っていて、同一の本源から発するものと思われた。彼が敢えてそれを為し得るためには、彼の肉体の或る部分をがむしゃらにひっつかんで他の部分へくっつけられるほどの粗暴な力を備えるか、それとも、或いは、不意にそれがそうなってしまったような、そんな風に出来上がってしまう異常な瞬間かが必要であった。
俺は俺だと荒々しくいい切りたいのだ。そして、いいきってしまえば、この責苦。[★11]
自同律とは論理学の用語で、同一原理(principle of identity)とも呼ばれる。思考原理のひとつで、「AはAである」の形式で表現される。ある概念はその思考過程においてひとつの同一の意味を保持しなければならない。「俺は俺だ」と言い切れないのはなぜか。それはそもそも主辞の「俺」が一体何であるのかが定義できていないからである。主辞の「俺」が不明であるのに、それがなんであるかを賓辞によって特定することはできない。にもかかわらずそれを特定してみようとすると、必ず失敗し、俺がなにものであるのか特定できないことによる不快、苛立ち、吐き気、嘔吐、そういったものが起こってくる。それが自同律の不快である。このような不快はそれほど特異な感覚ではないとも言える。しかし、これを異常なまでに意識しつづけること、それこそが異常なのである。そして、自同律という論理構造への異常な執着、「俺は俺である」と言い切れないことへの不快感、そこから生み出されてくるヴィジョンの探求、あるいは新たなその構築への試みが、ときとして開始される。つまり、俺とは何か、それを特定することのできるモデルはないのか、そのような探求のなかで構想されたのが、『死霊』の主人公のひとり、三輪与志による〈虚体〉という概念なのだ。
したがって、大野一雄の舞踏のなかに〈虚体〉を幻視したとしても、そこから〈自同律の不快〉へと遡行することができるかどうかは、差し当たりは不明である。だが、埴谷の構想において、〈虚体〉は〈自同律の不快〉と大きくかかわるのであり、その思考の推移がどのようなものかをまずは確認し、そののちにそれが大野一雄の舞踏の出現、もしくはその推移とどのように関係しているのか、あるいはしていないのかについて検討してみたいと思う。
『死霊』が言ってみれば小説形式による〈虚体〉論の展開であるということは、それがほぼ冒頭近くから、少なくとも書き残された最終章(九章)にいたるまで、明示的に議論されていることからもはっきりしている。この作品の主要な登場人物たちの多くが一堂に会する××風癲病院で交わされる会話から、われわれはまず次のようなことを了解することができるであろう。
三輪与志の〈虚体〉論は、ある現状認識、社会構造の把握の仕方を踏まえて構築されている。社会にあるのは絶えざる強制であり、そこで行われているのは、ある観念からの特別の行動しか生じなくさせる過酷な訓練である。それにどのように応答するのかがそこで議論されることになる。そのような状況のなかで、ひとつの観念(あるものにとって固有とされるもの)は、外へ向けて逸脱し、まったく別の異質なもの、つまり幽霊的存在へと変貌を遂げるべきであり、みずから想像するこの不可能な意識、“俺でない俺”へと絶え間なく変貌していくことによってはじめて〈自同律の不快〉から逃れることができると、三輪与志は考える。逆に言えば、三輪与志はわれわれの世界は幽霊屋敷ではないのだと考えているのであり、つまり、〈一つの観念──一つの意志の原型に似た観念〉のなかに閉じ込められているというのである。この不快から逃れようとするならば、そのとき何を構想すればいいのか。そこに必然的に到来するのが〈虚体〉という理念なのだ。
そしてこの〈虚体〉を構想するものの原動力、幽霊的存在とは何かが、そこに乱入してきた首猛夫、三輪与志の兄高志の棒組み(かごかきのなかま、相棒)との議論のなかでより明瞭になっていく。君はその相手の幽霊に対してどう挨拶するのかという、首猛夫の三輪与志への問いに三輪与志は黙して答えないが、その代わりに××風癲病院の岸博士が「三輪君は……つまり、相手の幽霊の立場にあることを欲してるんですよ」[★12]、と解説するのである。岸博士は、三輪与志は彼がそうなりたいと願う幽霊なのではなく、幽霊の立場にあることを欲しているのだと言っている。つまり重要なのは、三輪与志は幽霊ではないということなのである。だからこそ、そこに何らかのヴィジョンを、あるいは理念を構想し、その実現のための戦略をねらなければならない。そこで構想されたものこそが〈虚体〉なのである。
〈虚〉であると同時に〈在〉であること
そのような経緯からすると、〈虚体〉の実態というものはいまだ不明瞭のままだと言わざるをえないが、にもかかわらず、このような推移のなかでわれわれは『死霊』の冒頭のエピグラフを改めて思い浮かべ、幽霊的なものの本質について思いを巡らす。そしてそうした思考の流れに、大野一雄もまた身を委ねたであろうことが推測される。
『死霊』のエピグラフはこうである。
悪意と深淵の間を彷徨いつつ
宇宙のごと
私語する死霊達
このように、埴谷は『死霊』において、三輪与志がそうなることを願い、首猛夫がたとえそれが理性的なものであったとしても理想的ヴィジョンにはなりえないと考えた幽霊的なものに登場人物たちを見立てていることは明らかである。そして、大野一雄にあっては、舞踏家はその理想的な形態において幽霊でなければならないのである。大野一雄が稽古のときに語った言葉が録音され、起こされて一冊の本になっているので、どのようなことをしゃべっていたのか、われわれはかなり詳しく知ることができる。あるとき彼は次のように語った。
そうではなくて今日は、ダンスっていうのは幽霊だと私は思っているわけだ。幽霊でなくちゃだめだ。形があるようで形がないようで形がちゃんとある。私の心のなかに、鳥も住んでいる、獣も住んでいる、何も住んでいる。幽霊でなくちゃだめだ。こういう稽古をね、それ以上のことは今日言いませんから。幽霊ダンス。ということを自由にやってみたらどうか。要するにお化けになるための稽古をやってるんですよ。[★13]
死んだ霊が舞踏のなかに出てくる、かつて死んだ人、亡霊的なもの、そうした人物を演じる、そういうダンスや芝居はもちろんある。しかし、大野一雄がここで幽霊ダンスと言っているのはそうしたものではない。
[……]そうでなくてもっと、私は死者の恩恵をつぶさに受けて、ともに生きている、歩いていくっていうような、そういう気持ちで踊りたい。真似だけじゃとてもダメだ。真似以上にもっと実体として、あたかも実体があるようにして、想像力、人間がものを考えて、ってことも、自分が考え出してやるということでなくして、死者の恩恵によってやる。それが想像力だと思っている。自分のなかで頭働らかせて考えてこうするのは、想像力とは私には考えられない。[★14]
これらの発言において大野一雄が幽霊という言葉を使うとき、それがどのような存在を指しているのかについてはさまざまな議論が必要とされるであろう。だが、少なくとも次のようなことは言えるはずだ。つまり、それは「形があるようで形がないようで形がちゃんとある」ものであるということだ。それが具体的には何のことであるのか、具体的に示すのはもちろん容易ではないが、ともかくも、このようなものを特別な用語で言い表した言葉が『死霊』のなかには出てくるのである。それは〈虚在〉という言葉だ。〈虚在〉というこの聞きなれない用語は、虚ろな存在を意味すると思ってしまいそうであるが、埴谷が、あるいは、『死霊』の登場人物がこの用語を使うとき、この言葉はそのような意味をまったく持っていない。〈虚在〉とは、〈幽霊的身体〉を〈虚体〉へとつなげる特別な理念を表している。それはつまり、〈虚〉であると同時に〈在〉でもあるなにものかであり、そのようなものは次のようにして出現してくるとされている。
[……]ほーら、果てもない果ての果てまで攪拌に攪拌されつづけて「苦悩する存在」と「苦悩も怠屈すらもまるで示さぬ沈鬱な虚無」を、鉄色の大海のなかの小さなコルク玉として浮遊せしめ、また、沈めつづけているところの隠れた本源こそは、君が、師と弟子の相矛盾する言葉を並べたときからすでにきまっている。つまり、自身の影を自分自身のなかへ向ってとりこんでいる一種逆向きの曖昧で薄暗い単一語でいいきってしまえば、それは、虚在、さ。[★15]
この〈虚在〉が、「ある」と「ない」を巧妙に使いわけ、存在が存在自身までを瞞着しつづけてきた誤謬の宇宙史を転覆し、これまでの存在宇宙のまったく知らない未出現宇宙をひきだす創造的虚在となって、そのなかに潜み蹲ることになるのだという。そして、この創造的虚在を一語に縮小して言うとき、それを〈虚体〉と呼ぶのである。だがそれは、そもそものはじまりにおいて解きがたい問題として横たわっていたものの帰結なのであって、さらに言えば、〈虚体〉はひたすら創造するものであり、そのような場所では、あるものもないものもひとつの同じものとして創造される。これまでの宇宙にはかつてなく、これからの宇宙にも決してない何かを白い空虚のなかに創造してしまえるのが、つまり、創造的虚在であるところの〈虚体〉であるというのである。つまり、〈虚体〉は未生のものとして構想されてあるものなのであり、そこへ向けて世界が反転するとき、いかなる世界が現れるかが問題なのだ。しかし、このようなダイナミズムを身体表現はどのように実現しうるのか。それが大野一雄にとっての課題でもあったことは、先に引用した稽古場の言葉からも明らかだろう。
この創造的虚在を巡る議論は、1986年の『群像』九月号に発表された『死霊』八章の中心におかれるものだ。1977年から1996年にかけて、大野一雄が稽古場で語った言葉の録音テープから起こされた個々の言葉が、いつのものかが特定されていないので、右の引用が、『死霊』八章刊行以前のものか以後のものかは私にはわからない。だが、〈虚在〉とは、あらぬと同時にあるものであり、この概念は、まさに大野一雄が幽霊的なものとして定義したものとまぎれもなく合致するのである。これが偶然の共振関係のようなものかどうかについての議論は今後を待たねばならないが、そのような共振関係が大野一雄の舞踏と埴谷の仕事とのあいだには無数と言っていいほどあるのだ。
大野一雄とジャコメッティ
いずれにしても舞踏家大野一雄は、このような理念をまさにみずからの身体とともに実現しなければならない。そのとき決定的に重要な役割を果たしたテキストが、埴谷の一連のテキスト以外にも、もうひとつあったのではないかと私は最近思うようになった。もちろん、何事につけ幾つもの重要なモメントがあるだろう。たとえば、『ラ・アルヘンチーナ頌』の出現にとって、中西夏之の作品が決定的な役割を演じたことは本人が幾度も語っていることであり、多くの人によって指摘されてもいる。それが重要な動因であったことは間違いないのであろうが、埴谷との共振関係から眺めたとき、もうひとり重要な人物がいたらしいのだ。それはジャコメッティである。
國吉和子の論考「暗黒舞踏登場前夜──戦後日本のモダンダンスと大野一雄」[★16]には「A・ジャコメッティからの示唆」という節があって、そこには大野一雄とジャコメッティについて、きわめて興味深い事実が紹介されており、またそれを巡って論者による魅力的な分析がなされている。なによりも、大野一雄がジャコメッティに深い関心を抱いており、その関心がどのようなものであったかを事実でもって証明しているところに國吉論文の重要性がある。論文によれば、大野一雄が所蔵する1959年の『みずゑ』1月号「ジャコメッティ特集」に載っている矢内原伊作の「ジャコメッティ 人と作品Ⅱ」には、多くの下線が引かれ、またそこにはさまざまな書き込みがあるという。ジャコメッティにとって現実は、存在を彼から無限に引き離す恐るべき虚無、事物が硬直し麻痺して意味を失う危機的な真空状態にほかならないこと、ジャコメッティのオブジェにリアリティを保証しているのが、明徹の意識の果てで自己が失われるという追いつめられた孤独の苦悩であったこと、そうしたことに大野一雄が興味を持ったことが下線により示されていた。
矢内原はジャコメッティが、絶えずぎりぎりのところに追いつめられて動きが取れなくなった自分を感じていると書いているが、そのようにして追いつめられること、それはその年の4月25日の大野一雄モダンダンス公演『老人と海』の特質をなすものであったと國吉は言う。よく知られるように、針金のように細いジャコメッティの彫像は、矢内原によると、「現実に存在するものを見えるがままに実現する」彫刻を作ろうとしたものであり、統一のとれた「緊密な全体」を捉えようとすると、彫像は次第に小さくなっていくのだという。つまり、追いつめられ、さらに抽象的オブジェとしてではなく、現実を捉えようとするとき、ジャコメッティのあの空間が生み出されたということである。このようなことに興味を抱きつつみずからの作品を作ろうとしたとき、大野一雄の舞踏の形ができていったのだと、國吉は言うのである[★17]。
そして、あのジャコメッティの線の流れは、私には直ちに大野一雄の舞踏の動きの軌跡を思い出させるし、また、埴谷の〈虚体〉の空間的実現の姿を幻視させる。おそらく、埴谷の『死霊』の言語的な世界をジャコメッティの空間世界を媒介にして変換すると、埴谷の言う〈虚体〉の実現のような大野一雄の舞踏の動きが生まれるのではないか。「暗黒舞踏登場前夜」に引用された、大野一雄の下線が引かれたジャコメッティの文章と、そして國吉の分析を読みつつ、私は大野一雄と埴谷のより深いつながりを幻視したのである。実際、「今夜不正確な雲の中、重さのない靄の中に消えた女をさがしてまた会うこと。女は空間の中でくずれ去った[……]ありうる出会いのために。行ったと思う間もなく、女は、千の柵と千の溝の反対側にいる。彼女のすべてがぼくにとって未知の中へと再び沈んでゆき、彼女自身の上で閉じていった」、あるいは、「彼らは動く。それから横になって眠る。あるいは時には死ぬこともある。1人が時々、ストン、落ちる、虚ろの中に。/むしろ空間もまた、ない」などといった書付がジャコメッティの手帳や紙葉のなかには散見され、この3人の世界認識や作品の相同性は深まるばかりである[★18]。
さらに、ジャコメッティの次のような言葉に触れるとき、この3人の作品の持つ意味合いにも、大きな変容が生じるのではないかと思える。そして、それとの関係において彼ら作家たちの現代芸術における、いやはっきり言って、21世紀芸術における新たな重要性が浮上してくると思うのである。
すべてを歪曲する恐るべきブルジョワ根性、これと戦うこと、いつどこでも、いかなる代価を払っても。革命のために。
1934年頃[★19]
このような言葉が、「あらゆるものの限りを知らぬ空しさ。/そして神秘は、すべての上に、すべての内に存在する。/いつも人間は芸術において、世界をどう捉え考えるか、を表明してきた。哲学よりももっと直接に」[★20]と書いた芸術家によって書きつけられるということ、そのようなことをわれわれは埴谷においても体験しているのである。
埴谷雄高の転向
埴谷の転向に関してはしばしば言及される。そして、『死霊』は転向後の小説である。思想の科学研究会編『共同研究 転向(上巻、戦前編)』(平凡社、1959年)には、「虚無主義の形成」と題した鶴見俊輔の埴谷論が載っている。ちなみに、中巻は戦中編、下巻は戦後編である。埴谷は1910年に台湾で生まれ、1923年に東京に移転、学生時代にアナーキズムからマルクス主義へと転身した。それはレーニンの『国家と革命』における国家の死滅の理論に衝撃を受けたためだと言われている。そして1931年、21歳の春、日本共産党に入党し、地下生活を送るようになる。こうしたことはよく知られた事実である。1932年3月には逮捕され、5月には豊多摩刑務所に送監、刑務所でドイツ語の勉強のため読んだカントの『純粋理性批判』に衝撃を受け、マルクス主義を捨てたと言われている。これがいわゆる埴谷の転向である。1933年、懲役2年執行猶予4年の判決を受けて出所し、1939年に同人雑誌『構想』を創刊、そこに『洞窟』を発表、さらに『不合理ゆえに吾信ず』を連載するなど作家活動をはじめる。そして、敗戦。敗戦後、1946年1月の『近代文学』の創刊にかかわり、そこに連載したのが『死霊』である。
この『死霊』は未完のまま、第一巻が1948年に真善美社から刊行され、この巻がその後、さまざまな形で出版され、多くの読者を獲得していることもよく知られた事実である。そして、登場人物たちの多くが地下運動にかかわり、かつ獄中生活を体験していることなど、きわめて政治的な色彩が濃いにもかかわらず、『死霊』はむしろ、難解な哲学的作品として高く評価されることが多い。〈自同律の不快〉や〈虚体〉が何を意味するかを巡る議論は難解を極め、それらの議論は政治的現実からいよいよ遠ざかっていく傾向すらあるが、ジャコメッティの例に倣うならば、「転向」の内実と小説の表現との関係もまた、深く探求・考察されなければならないだろう。実際、『死霊』未完のまま長い年月が流れるが、そのあいだ、埴谷は多くの政治論文を書き、そのなかには、『死霊』と密接にかかわるもの、あたかも『死霊』論であるかのようなものもある。
なかでも、1958年の『中央公論』11月号に掲載された「政治のなかの死」は、松田道雄編『現代日本思想体系一六巻 アナーキズム』に収録されていることにおいても興味深い。松田道雄は、日本のアナーキストを代表する幸徳秋水や大杉栄らの論文のあとに、今日のアナーキストとして三好十郎と埴谷の二人を選んで載せたのである。つまり、埴谷は学生時代にアナーキズムからマルクス主義へと移行し、1933年頃の多くのマルクス主義者らとともに転向し、敗戦後再結成された日本共産党へと復党した多くの知識人、あるいは逆に保守化した者たちとは違い、カント主義者として活動したとされるが、その政治的信条はむしろアナーキズムであったと松田には判断されたのである。実際、「政治のなかの死」で主張されているのは、権力関係と支配構造の一切がなくなることであり、重要なのは権力者による非権力者の支配がなくなることだと埴谷は考えつづけていたのである。
たとえば、「階級社会を反映した組織の枠内に必ず起る精神の三位一体」、つまり、「傲岸、卑屈、執念」、「満足した指導層、絶えず目を動かし聞き耳をたてて情勢とともに揺れている人物層、および永遠の不満者の層に、これらの精神内容はほとんど照応するが、さて、第四の層ともいうべき沈黙者たちも、短い時の流れのなかにさえ少数の批判者たる位置にとどまれず、上記の三層のそれぞれへいつしか踏みこんでしまうことを思えば、これらがなければ政治の秩序が保ってゆけないと思われるほどである」と「政治のなかの死」には書かれている。そして、「政治の意志」とは数千年のあいだつねに同じであり、それは「やつは敵である。敵を殺せ」であり、「いかなる指導者もそれ以上卓抜なことは言い得なかった」とも書かれている。こうした主張は、「政治が生活の集約であり、戦争が政治の集約であるかぎり、戦争にはまた生活にあるすべてのものがある」という判断へといたる[★21]。そして、それらのすべてが否定されるべき事実として確認され、次のような歴史認識が導かれるのである。
[……]歴史は必ずしも真実を語らない。死者についての真実を決して歴史は語らない。[……]そこでは、殺した側に栄光と正義と未来があって、殺された側には蓋ふたをあけられることもない小さな秘密の墓と、そして、蓋をあけてもついに何物も発見することのできない永遠の空虚がある。[★22]
たとえば、『死霊』の首猛夫が組織を離脱し、一匹狼として活動することになるのは、このような政治の仕組み、階級を廃絶するために戦う党において、皮肉なことに一層強化される権力構造を容認している人々、それに無自覚な人々を拒否しようとしてのことであり、首のこのような主張を巡っての議論は随所に出てくる。やがて1975年、第四章の途中まで書かれたまま未完となっていた『死霊』の続きが書きはじめられ、『群像』7月号に第五章「夢魔の世界」が発表されるが、そこには山中に籠った過激派集団のスパイに対する査問委員会での激論と、スパイ処刑の様子が詳細に描かれている。それは1972年のあさま山荘事件に帰結する妙義山中などでのリンチ、殺害事件を彷彿とさせ、1949年の『近代文学』11月号で中断するまでの四章分が、戦前の地下活動の様子を思わせるのと同様に、『死霊』が執筆当時の現実の政治的、社会的状況とも密接にかかわる形而上学的な作品であることが理解されるのである。
つまり、「悪意と深淵の間を彷徨いつつ宇宙のごとく私語する死霊達」がさらにさまざまな幽霊たちを呼び出し、あるいはその訪問を受け、多くのエピソードを綴っていきながら、最終的には〈虚体〉を構想することを目指すこの宇宙論的小説世界は、一方においてきわめて政治的な作品であり、また他方では過去の事実を呼び起こし検討する、歴史的な考察の試みであり、1948年10月に刊行された『死霊』第一巻は、スターリン批判以前に書かれたレーニン主義の挫折の物語でもある。そしてこの作品は、〈虚体〉という仮構されたヴィジョンにおいて大野一雄の舞踏につながり、ジャコメッティの政治と空間との関係にもかかわるのである。大野一雄、埴谷、ジャコメッティというこの三角形を凝視するとき、大野一雄の戦争体験、その政治的な性格と大野一雄の〈虚体〉的な舞踏との関連もまた想起される。
大野一雄は埴谷邸を訪れてから約一年後の1996年11月11日、前出の丸地守によるインタビュー「宇宙論──埴谷雄高へ」のなかで、『死霊』について、また戦争について幾つかの発言をしている。「大人になってから、〈死と生〉の問題に深く関ったということはありませんか」という丸地守の問いに対して、大野一雄は次のように語りはじめる。
戦争体験ですね。戦争というものは、殺すか殺されるか、勝つか負けるか。といった狂気そのものですからね。中国大陸、ニューギニアへと足かけ八年も行っておりました。中国にいたときのことですが、交代で休みのとき兵隊が町へ流れていくでしょう、そのとき兵隊が狂ったように銃を発射したりするんです。ときには中国人が二十人ぐらい倒れて呻いていたりするんです。恐怖の顔、死んで青ざめている顔が一緒に重りあっているんです。機関銃で、ダダッーとやってしまったんですね。兵隊たちはすでに狂人になっていたんです。戦争は、つねに自分の方が正しい、大義名分がある。──そう思い込んでいます。そこに狂気が加わってそういうことが起こる。狂気は意外性を生んだり、人間の一つのエネルギーだけれども、人間はそういうものをさらに濾過し、宇宙もそうですけれども愛の理念で生きなければいけませんね。[★23]
関連図書の年譜によれば、大野一雄は1938年、32歳のとき召集を受け、師団司令部情報将校の任につき、陸軍大尉として華北・ニューギニアに従軍した。そして、1945年の敗戦のあと、1年間捕虜生活を送り、1946年に復員したと書かれている。ニューギニアでの体験については多くを語っていないとされているが、大野一雄と幾度も対談をしている詩人の吉増剛造によれば、そこでの体験が幾つかの舞踏のなかに反映されているのだという[★24]。しかし、中国での戦争体験について語った直後に、大野一雄は、次のようにも語っている。
そうです。現実を超えたところまで行って、現実を描く。現実を表現していると思っても現実の本当のところを表現し得ないことが多い。[……]身体によって表現し得ないものは無踏の世界に存在してはならない。身体を持たない幽霊さえも、身体によって表現しなければならないと思っています。そういうなかで、また新しい何かが生まれてくる。埴谷さんは、『死霊』でそのようなことを語っているのだと思います。私が埴谷さんを尊敬しているのは、そういうところです。[★25]
戦争における残虐行為が愛の理念の希求へと反転するとき、あるいは転向が宇宙論的な〈虚体〉のヴィジョンへと反転するとき、そこで何が起こっているのか。そのとき重要なのは、そのような新たな生のあり方が、過去に引き戻され、そこから亡霊、幽霊たちを呼び起こし、かつまた幽霊との合一をも果たそうとするという、不可能への挑戦として実践されているということではないだろうか。「──薔薇、屈辱、自同律──つづめて云えば俺はこれだけ。」という埴谷の『不合理ゆえに吾信ず』に書き込まれた言葉を取り上げながら、鶴見俊輔は、「手裏剣をなげるようにして三つの単語で定着した体験は、まず第一にバラ色のイリュージョンとしての日本共産党参加、それからの屈辱的な脱落としての転向、バラ色の幻想から脱落した孤独な自我によって完全に自己同一律的な統制される行為としての思想、の三点によってかこまれている」[★26]と書いたが、まさにこのような包囲網からどのように脱出するかが、『死霊』を書きつづけることの目的であったのである。そして、大野一雄もまた、ジャコメッティに方法的な示唆を受けつつ、さらには『死霊』における埴谷の悪戦苦闘を目の当たりにしつつ、1959年に手に取った『みずゑ』のなかのジャコメッティ論とともにモダンダンスから離脱し、長い活動休止期間を経て、18年後の1977年の『ラ・アルヘンチーナ頌』において幽霊的身体としての舞踏を実現することができたのだ。
あるいは、磯崎新の言葉を思い出しながら、なぜみずからを影にしなければならなかったのかと問うてみればいい。ここにもニューギニアの影が私には感じられる。つまり、嘔吐感は影化の中に実体化していたのではないのか。ニューギニアでの体験については語らず、中国での日本軍の残虐行為について語りつつ、自分を無害な場所に配置した大野一雄は、しかしその舞踏においてはみずからを空洞の中に投げ込み、根拠をまったく剥奪された人間として提示するのであった。それゆえにお母さんや愛の純粋さは、嘔吐の逆説的な形象として、空間化そして身体化されているのであり、影は実体を想起させてはならないのである。実体は自同律の不快として存在する。でなければ埴谷雄高に深く捉えられていくはずはない。
革命の挫折か、戦争の敗北か、いずれにせよ「戦争と革命の世紀」と呼ばれた20世紀における芸術の本質に深くかかわるところで、2人の作品は共振関係を結んでいたのである。
■
舞踏の創始者で、『ラ・アルヘンチーナ頌』など大野一雄の舞踏の演出も多く手掛けた土方巽は、1945年、日本が敗戦を迎えたときは高校を卒業したばかりの17歳で、戦前の転向や戦争の従軍などとはかかわりがないが、彼の舞踏に対する定義はあまりにも有名である。それは「舞踏とは命がけで突っ立っている死体である」というものである。言うまでもなく舞踏の沈み込むような身体は、飛翔と旋回によって空間を満たす華麗な動きではなく、深く重力によって吸引されている。それが大地との接触なのか、それとも大地の呪縛なのか、接触ならばなぜ命がけで立たなければならないのか、そうした議論もまた必要とされているが、私が興味を持っているのはむしろ、東北が日本の植民地だという土方巽の発言である。植民地としての東北は日本に四つのものを供出させられていた。それは馬と米、そして、男と女である。馬は軍馬のことであり、男は兵隊、そして女は女郎である。ここからどのような舞踏論を展開すべきかは興味深いところだが、別の機会に譲りたい。
戦後、空洞のようなところへ投げ込まれた人々は、そこから再出発するために自らを死体として認識し、あるいは、虚体を構想しようとした。しかし、世界のもうひとつの崩壊の形を準備しつつあった20世紀の終りを前にして、監禁され、収容された身体は、内破しつつ、かつ逸脱の試みを妄想していた。そのような文脈の中で、最後に舞踏家・室伏鴻の舞踏における〈外〉の思考、そのエイリアン的な特質について、問題を提起しようとするならば、それが1980年代に具体的に実を結んだということの意味について考えなければならないだろう。

1998年、私は田中泯が主宰している山梨県での夏のダンス・フェスティヴァル「ダンス白州」で、室伏鴻の野外ソロ・パフォーマンスを見た。そして、公演後、室伏が近づいてきたとき、思わず、エイリアンの身体みたいですね、と私はつぶやいたのであった。これはそのときの、とっさの思いつきであったが、しかし、川口隆夫のダンス『大野一雄について』を見て、〈虚体〉という言葉が浮かんできたときのように、私にとっては重要な事件であった。エイリアンの身体とは何か。それは内部が皮膚の外へと飛び出すような身体のことである。もちろん、実際に内臓が外に飛び出して散乱するなどということはありえない。しかし、室伏の身体の異様な歪みと変容は、体の内部が外に流出しているかのような印象を与え、その噴出に引きずられるように体が動いているのか、それとも室伏の意志によって白州の緑に包まれ、畑に囲まれた空間のなかを動き回っているのかは定かではなかった。この外見上の印象は、やがて彼が企画するプロジェクトの名称によって、その意味をきわめて明確に示したのであった。
2013年、横浜の赤レンガ倉庫において、現代舞踏の現在について考える上演とシンポジウムなどが展開されたが、その6日間にわたる企画を、室伏は『〈外〉の千夜一夜』と名づけていたのであった。言うまでもなくこの命名は、モーリス・ブランショを論じたミシェル・フーコーの1966年の論考「外の思考」(豊崎光一訳、『パイデイア』1970年春季号)に示唆されたものだが、私はこのタイトルを見て、エイリアンの身体という命名は、特別の意味を持ちうるのではないのかと思ったのだった。その企画には、芥正彦と室伏の2人による舞踏パフォーマンス『アルトー二人』なども含まれていて、エイリアンの身体とともにアルトーの「器官なき身体」や、焼け焦げたような皮膚に覆われた人間のデッサンなどを私に思い出させたのである。内臓が剝き出しになったような崩壊する皮膚と、絶え間なく幾度も幾度も転倒する身体、あるいは有機体の調和的美の失墜、そうしたものは一方において新たな生命力の台頭を予感させもするが、同時に世界の終焉と人間の死をも思わせる。この企画は20世紀末の現実を、身体的な瓦解として生きようとする舞踏家たちが存在することを示したのであり、それはつまり、敗戦後の日本文化の空洞のなかで、〈虚体〉というヴィジョンとともに埴谷雄高が世界の〈外〉を構想したように、また、大野一雄がみずからの舞踏を〈幽霊ダンス〉と命名したように、20世紀の終わりを前にして、崩壊する皮膚とともに〈外〉へと向けて内破し、エイリアンの身体として生きようとする、さらに下の世代が登場してきたことを物語ってもいた。
すでに述べたように、20世紀は「革命と戦争の世紀」と呼ばれていた。そしていま、やがて「革命なき戦争の世紀」と呼ばれることになるだろう21世紀、そのはじまりにあたって、室伏が試みようとしたことは、外へと流出するエイリアンの身体をどのように仮構するかということである。それはフーコーが言うところの、「その本質を露呈することはけっしてない」〈外〉、「実質的な現存として[……]は提示されえず、ただ単に不在として、[……]提示されるにすぎない」〈外〉[★27]、つまり、まるで『死霊』の〈虚体〉のように、到達不可能性として存在する〈外〉、そうしたものを志向するエイリアンの身体を生きることによって、「革命なき戦争の世紀」を転覆しようとすることなのである。
少なくともわれわれは、〈外〉と、空虚、バキューム、〈虚体〉といったものがどういう形でつながり、1950年前後の〈虚体〉と、1980年代からの〈外〉がどのようなものかを考える、とば口に立つことはできた。これからは、エイリアンという80年代、90年代の〈外〉というようなものの出現の精神史的な意味を詳細に検討していくこと、さらに21世紀に入ったいま、〈外〉へ向けてのどのような戦略が立てられうるかを問題にすることがきわめて重要になってくるであろう。そのためには芸術活動全体を歴史性のうちに、あるいは社会構造や精神史との関係のなかで大幅に見直していく必要があるだろう。そのような形で、舞踏に限らず表現における身体の中核へと迫らなければならない。モーリス・ブランショは次のように書いている。
[……]最初の著作からして、フーコーは、ずっと以前からつねに哲学に属している諸問題(理性、非理性)を扱っているわけであるが、しかしそれらを歴史と社会学の角度から扱っているのである──歴史において或る種の非連続[……]を特権化しつつも、その非連続を断絶とするわけではなしに[……]。[★28]
写真提供=室伏鴻アーカイブ
★1 埴谷雄高「政治と文学と・補足──吉本隆明への最後の手紙」、『埴谷雄高──新たなる黙示』、河出書房新社、2006年、68頁(初出は『海燕』1985年4月号)。なお、文中に引用されているエッセイ『革命の意味』は『埴谷雄高作品集 3』(河出書房新社、1971年)などに収録されている。引用部分は、作品集では228頁。初出は『中央公論』1959年11月号。
★2 埴谷雄高『死霊 Ⅰ』、講談社文芸文庫、2003年、118–119頁。
★3 『現代詩手帖』2010年9月号、思潮社、25 – 26頁。この号の特集は「大野一雄──詩魂、空に舞う。」。
★4 『死霊』九章の「《虚体》論──大宇宙の夢」は、『群像』1995年11月号に発表されており、大野一雄は12月の埴谷宅訪問のときすでに九章を読んでいた可能性がある。1996年11月11日の丸地守の大野一雄へのインタビュー「宇宙論──埴谷雄高へ」(大野一雄ほか『大野一雄』、書肆青樹社、1997年、29頁)のなかで、大野一雄は「『死霊』九章というと最近のものですね。私も読ませていただきました」と言っており、訪問の前かあとかは特定できないが、そのころ『死霊』を読んだことは確認できる。細江英公が「最終執筆の最中」と言っているのは、『死霊』はさらに書きつづけられる可能性もあり、この発言は、『群像』に発表されたものは九章の途中までだと細江英公が考えていたということを物語るのかもしれない。いずれにせよ、『死霊』はその後、断片が幾つか書き残されたまま、埴谷の死とともに、中断、もしくは完了した。
★5 『死霊 Ⅲ』、講談社文芸文庫、2003年、337–338、341頁。
★6 磯崎新「はじまりから遊離した影のようだった」、『現代詩手帖』2010年9月号、27–28頁。
★7 『死霊 Ⅰ』108–109頁。
★8 「宇宙論──埴谷雄高へ」、24頁。
★9 埴谷雄高「土方巽のこと」、『アスベスト館通信』第1号、1986年10月。
★10 果たして、埴谷がこの公演を見るきっかけとなったサド裁判の被告、澁澤龍彥はそこにいたのだろうか。そして澁澤龍彥と一緒に、埴谷も打ち上げに残ったのだろうか。なお、埴谷がこの公演のチラシを手にしたのはサド裁判が行われていた東京地方裁判所玄関の真向かいにある日比谷公園であり、埴谷自身、サド裁判の弁護人であったということを参考までに付け加えておこう。ちなみに、埴谷がサド裁判の証人として出廷したのは1962年2月28日である。
★11 『死霊 Ⅰ』、162頁。
★12 同書、108頁。強調は引用者。
★13 大野一雄『大野一雄──稽古の言葉』、フィルムアート社、1997年、76頁。
★14 同書、53頁。
★15 『死霊 Ⅲ』、280 – 281頁。ここで弟子とされているのは、「あらぬものはあるものに少しも劣らずにある」と言ったデモクリトスだと思われる。君とはエトナ火山の火口に身を投げたエンペドクレスのことだが、師についてはよくわからない。
★16 この論考は2007年、明治学院大学で開催された「大野一雄国際シンポジウム2007」のドキュメント『大野一雄・舞踏と生命』(岡本章編、思潮社、2012年)に収録されている。
★17 國吉和子「暗黒舞踏登場前夜──戦後日本のモダンダンスと大野一雄」、『大野一雄・舞踏と生命』、71–74頁。
★18 ジャコメッティ『エクリ』、矢内原伊作・宇佐見英治ほか訳、みすず書房、1994年、207頁、225頁参照。
★19 同書、275頁。
★20 同書、209頁。
★21 埴谷雄高「政治のなかの死」、松田道雄編『現代日本思想大系一六巻 アナーキズム』、筑摩書房、1963年、426–427頁。初出は『中央公論』1958年11月号。
★22 「政治のなかの死」、428–429頁。
★23 『大野一雄』、22頁。
★24 詳細については『現代詩手帖』2010年9月号での大野慶人、樋口良澄との鼎談「火炉の傍らに立つこの巨人」参照。さらにここで吉増剛造によって読み上げられる大野一雄のニューギニアでの体験談は、1999年の『FRONT』8月号(シンコーミュージック)での吉増剛造と大野一雄との対談からのものだそうだが、筆者は未見。
★25 『大野一雄』、26頁。
★26 鶴見俊輔「虚無主義の形成──埴谷雄高」、思想の科学研究会編『共同研究 転向 上』、平凡社、1959年、296頁。
★27 M・フーコー「外の思想」(豊崎光一訳)、『パイデイア』7号、1970年、37–38頁。
★28 モーリス・ブランショ『ミシェル・フーコー──想い出に映るまま』、豊崎光一訳、哲学書房、1986年、14–15頁。


鴻英良