フランツ・ファノンをカリブ海哲学に読み戻す|中村達
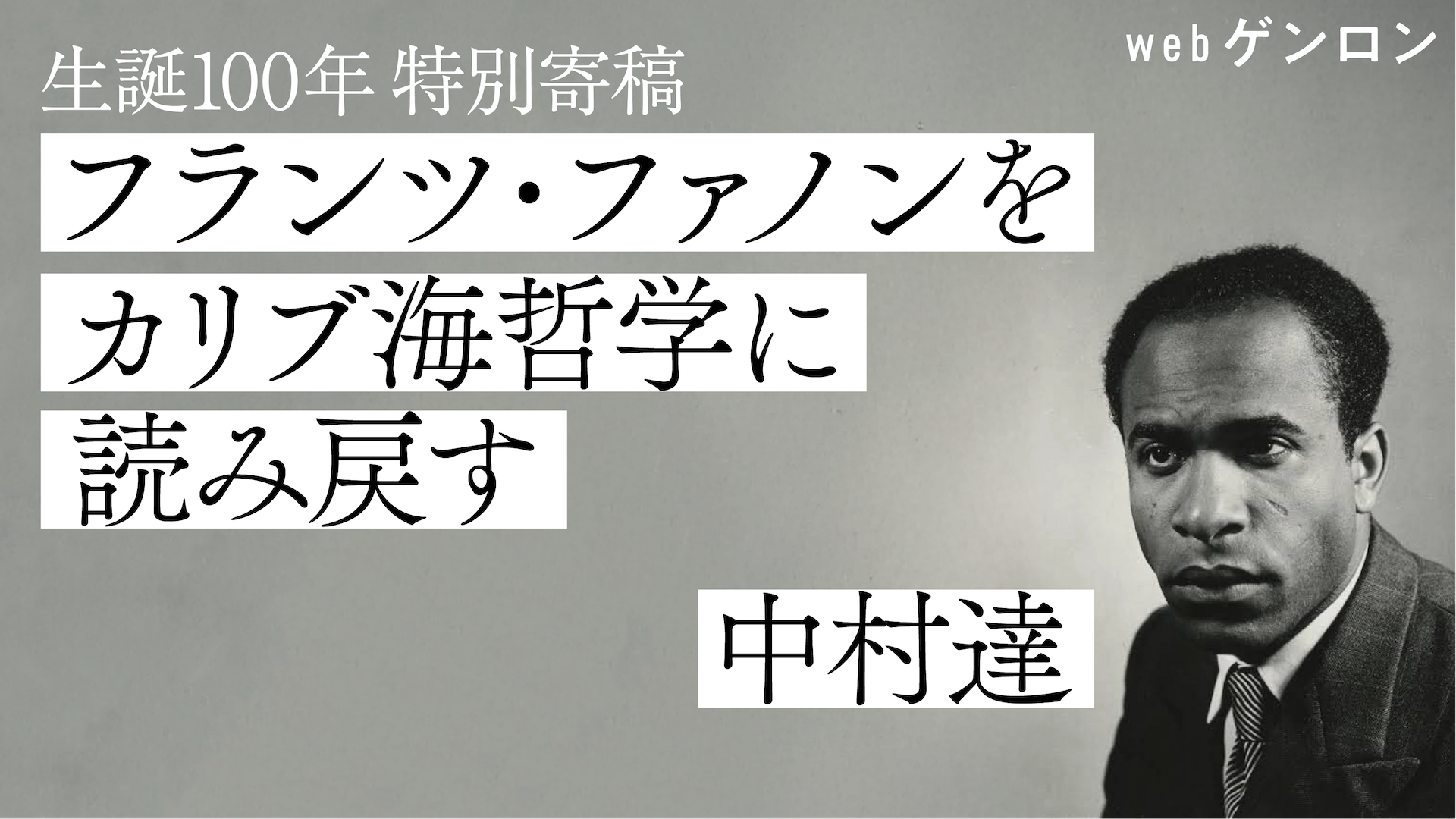
ファノンはしばしば、「その形成期を過ごしたカリブ海の文脈とは切り離されて理解されている」[★1]。
カリブ海哲学研究の金字塔『キャリバンの理性』(2000年、未邦訳)において、アンティグア出身の社会学者パジェット・ヘンリー(Paget Henry)は、ファノンの扱われ方についてそのような不満を表明してから、フランツ・ファノン論を書き始めている。この指摘は、日本における受容の歴史を振り返っても、決して無縁なものではない。
1925年月20日、カリブ海に浮かぶフランスの植民地、マルティニーク島に生まれたフランツ・ファノン。アルジェリア独立戦争にも大きな影響を与えたその思想家は、日本では比較的早い時期から、海老坂武や鈴木道彦という優れた紹介者・翻訳者の存在もあり、「第三世界」の闘士として迎えられた。
『黒い皮膚・白い仮面』や『地に呪われたる者』、『アフリカ革命へ向けて』といった彼の名著は、1960年代から80年代の日本において、解放と闘争のバイブルとして読まれていた。その後はポストコロニアリズムの潮流の中で、サイード、バーバ、スピヴァクと並ぶ「必読理論家」となり、本橋哲也の『ポストコロニアル』(岩波新書、2005年)のように、教科書的に紹介されるようになった。さらには竹村和子が『フェミニズム』(岩波書店、2000年)で指摘したように、フェミニズム批評の射程において、ファノンの男性中心主義、異性愛主義、同性愛嫌悪が厳しく問われるようになった。
現在も森元斎『死なないための暴力論』(インターナショナル新書、2024年)が示すように、彼の暴力論は現代思想の重要な参照点である。また、河野哲也『アフリカ哲学全史』(ちくま新書、2024年)ではアフリカ哲学の一部として位置づけられている。しかし、これだけ長い受容の過程を通じても、ファノンの思想を彼が生まれ育ったカリブ海の文脈で読む試みは、なかなか見られない[★2]。
そのような中、『キャリバンの理性』から四半世紀を経た2025年、岩波書店の雑誌『思想』がファノン生誕100年の記念特集を組んだ。多様な研究者が寄稿し、ファノンのこれまでの受容と今後の展望を提示したが、やはりそこにも「カリブ海」の視座は希薄であった。
特集の中核となる中村隆之、崎山政毅、岡真理による対談では、中村が欧米経由によるファノン理解を批判したのに対して、崎山が「西欧やアメリカを通して受け止めるのとはまた別のルート」は見いだせるはずだし、「日本に紹介されてきた経緯を考えても、ファノンへたどり着くための『直行便』があるはずだ」と応じている[★3]。
しかし、もしそうであるならば、ファノンの生誕地であるカリブ海からその「直行便」は出ていないのだろうか。たとえば岡は、ファノンが「私から見れば近代西洋主義者」とし、彼を論じたところでにわかに西洋近代中心の知の構造が脱構築されるとは思えないと主張するが[★4]、その指摘からファノンの知をめぐるカリブ海の文脈に本格的に踏み込むことはない。
『黒い皮膚、白い仮面』において、ファノンは一般的な「黒人」の経験を包括的に論じているように見える。しかしその一方で、彼の議論が最終的に見据えているのは、自身の出自であるカリブ海という特定の世界なのだ。ファノンは、人種差別や植民地主義がもたらす疎外感という普遍的なテーマを提起しながらも、その具体的な立ち現われ方や経験、そしてその解決を、カリブ海を背景にした個々の歴史や文化に照らして示している。同書の序文で、ファノンは「人間」の新しい未来像の重要性を論じてみせる。だが、その末尾では一般論から後退し、カリブ海という特定の焦点に戻り、こう述べる。「この未来とは宇宙の未来ではない。そうではなく、まさしく、私の世紀、私の国、私の現実の生の未来なのだ」[★5]。
このようにファノンの思考は、「普遍的人間」をめぐる問いを一度は立ち上げながらも、最後にはそれを自らの地域的出自の文脈に引き戻してしまう。彼にとって普遍的人間の問題は、抽象的な理念ではなく、カリブ海の現実を通してこそ具体化されるものなのだ。そう考えると、彼が『黒い皮膚、白い仮面』に書きつけた次の言葉が持つ重みもいっそう明瞭になるだろう。
アンティル諸島出身であるがゆえに、私の考察と結論は、アンティル人に対してのみ──少なくとも、うちにいる黒人に関しては──価値を持つのだ。[★6]
果たして、ファノンを読んできた我々のうち何人がこの一文に立ち止まり、その意図を考えたことがあるだろうか。少なくとも初期のファノンは、常にカリブ海を見据えているのだ。
本稿の試みは、ファノン受容に対するヘンリーの批判に倣い、フランツ・ファノンを「カリブ海哲学」という特定の文脈に位置づけるというものである。
その目標は、植民地期に形成されたカリブ海哲学の歴史的発展とその内在的問題を検討し、そこにファノンがなした複雑な貢献と限界を訪ね、私たちが読んできたフランツ・ファノンの文章をカリブ海哲学史の伝統の一部として「読み戻す」ことなのだ。
ファノンとともに、カリブ海哲学の水脈の中に、私たちも深く潜ってみるのはいかがだろうか。
カリブ海哲学と「対話的枠組み」
先のパジェット・ヘンリーによれば、カリブ海における思想潮流は、クリストファー・コロンブスによる「発見」以来、ある種の「対話的枠組み dialogical framework」によってかたどられてきたという[★7]。
ひとつが、「ヨーロッパ側からの対話 European layers」である。
これは、クレオール・ナショナリスト(植民地生まれで自治を求める人たち)とロイヤリスト(宗主国の権力と王室に忠実で自治に反対する人たち)、奴隷制継続派と奴隷制廃止派といった、ヨーロッパ人作家や宗教家、弁護士や政治家たちの間の内部対立から発生してくる対話のことだ。彼らはそれぞれの立場から植民地統治のあり方や奴隷制、人種、自治の是非など様々なテーマでカリブ海を語っている。
スペイン領ではフランシスコ・デ・ビトリア、ゴンサロ・フェルナンデス・デ・オビエド、アントニオ・デ・エレーラ・イ・トルデシリャスらが、スペインがカリブ海を統治する権利を論じる一方で、バルトロメ・デ・ラス・カサスがスペイン人による先住民への残酷な扱いを告発したり、ホセ・アントニオ・サコやアントニオ・バチレル・イ・モラレスが、先住民の抵抗やアフリカ人奴隷制といった問題を深く掘り下げたりした。
イギリス領では、エドワード・リトルトン、リチャード・ライゴン、エドワード・ロングらが、植民地社会の構造やアフリカ人奴隷の文化・アイデンティティについて記述を残した。その一方で、ジェイムズ・ラムゼイやウィリアム・ウィルバーフォースのような人物が、奴隷制の非人道性を訴えた。
フランス領では、シャルル・ド・ロアン゠ロシュフォールやジャン・バティスト・ラバのような作家が、植民地の歴史や地理、その習慣などを書き残す間に、モロー・ド・サン=メリーやイリアール・ドーベルテュイユらが、植民地社会の法制度や文化を論じ、ヴィクトル・シュルシェールが奴隷解放に決定的な役割を果たした。
もうひとつが、「アフリカ側からの対話 African layers」である。
この対話は奴隷制廃止と独立運動の高まりの中で、19世紀後半からアフリカ系のカリブ海知識人たちによって生み出されたものだ。ロバート・ラヴ、エドワード・ブライデン、マーカス・ガーヴェイ、そしてヘンリー・シルヴェスター゠ウィリアムズがその代表である。彼らは元奴隷、もしくはその子孫であるアフリカ系住民の権利を擁護し、アフリカ文化の価値を再評価することで、普遍的価値観を標榜するヨーロッパ中心思想に対抗する言説を形成していった。
しかし、その言説は哲学理論探究というよりも、自治権の獲得やアフリカ系の人々の地位向上のための闘争に向けた政治思想としての性格が強かった。したがって彼らの言説も、依然としてリベラリズムやナショナリズム、社会主義など西洋の思想的枠組みに依存せざるを得なかった。
そのような双方からの「対話」が交差した出来事として、たとえばこんなことがあった。
1888年、まずはヨーロッパ側からの対話として、イギリスの歴史家・評論家ジェイムズ・アンソニー・フルードが、旅行記『西インド諸島の英国人 The English in the West Indies』を出版した。そこでフルードは、自身が視察を行なったカリブ海地域に対して極めて人種主義的かつ植民地主義的な見解を展開していた。彼はアフリカ系住民が自治には生来不適格であり、怠惰であるがゆえに自分たちがもたらした文明を維持できないと描き、イギリスによる統治の継続を正当化した。
それに対して、アフリカ側からの対話として、トリニダード人言語学者ジョン・ジェイコブ・トマスが『フルーダシティ Froudacity』(1889年)を出版する。トマスはフルードの事実誤認や人種主義的な偏見をつぶさに指摘し、現地の実態を示しながら、西インド諸島の社会でのアフリカ系市民の勤勉さや自治能力を強調して反駁した。そして、トリニダード社会の停滞は、むしろイギリスの搾取的な植民地経済、そして教育・政治制度の不備にあると論じたのである。
しかしながら、トマスのようなアフリカ系知識人による対話は、あくまでもヨーロッパ側の対話に見られるアフリカ人たちの不平等な誤表象への批判的応答に留まっており、カリブ海独自の哲学的言語を獲得するには至らなかった。そしてまた、アフリカ側からの対話も、ヨーロッパの言語で行わなければならない状況にあったのである。
このような思想的状況を引き継いだのが、20世紀カリブ海の哲学者たちである。20世紀になると日本でもよく知られているフランツ・ファノンやC. L. R. ジェイムズだけでなく、クライヴ・トーマス(Clive Y. Thomas)、ジョージ・ベックフォード(George L. Beckford)、ノーマン・ガーヴァン(Norman Girvan)といった錚々たるカリブ海系知識人たちが、カリブ海の知をめぐる活動に従事していった。
だが、彼らが引き継いだこの「対話的枠組み」には、あるタブーが埋め込まれていたとヘンリーは指摘する。
我々にとってとりわけ重要なのは、哲学は「原始的な」人間が従事するような実践ではないという理由でアフリカ哲学が被った、完全なる排除(the complete disenfranchisement)である。ヨーロッパの言説が自らに課した最も強いタブーのひとつに、彼ら自身の部族的な、あるいは原始的な過去を公然と認めることに対するタブーがあった。この「原始的」と「文明的」という強力な二項対立は、カリブ海の思想的伝統がヨーロッパから受け継いだものである。このふたつの間には、埋めがたい溝がある。[★8]
プランテーション経済を基盤にした植民地世界において、カリブ海地域の哲学は、ヨーロッパ側からの支配を正当化するための言説と、それに対するアフリカ側からの抵抗的言説という「対話的構造」の中で形成されていった。
しかし、その「対話」は対等なものではなく、実際には国家権力の側に立つヨーロッパ側こそが常に優位であり、哲学として「適切」なものとされていた。ヨーロッパ側の言説が帝国の権力によって制度的に支えられ知的権威を蓄積していったのに対して、アフリカ側の叡智は、野蛮な営みとして描かれ、その体系から疎外され続けたのだ。
不均衡な対話的構造の中で、カリブ海哲学は、ヨーロッパ的な合理主義や普遍主義を利用しながら、野蛮なアフリカ人を文明化するというイデオロギー生産の道具となることを余儀なくされた。それはカリブ海哲学のなかで、ヨーロッパこそが「文明」でありアフリカは「未開」であるという二項対立が固定化されることを意味していた。つまりカリブ海において哲学は、ヨーロッパによる植民地支配の正統性を支えるための「補助的知」として「文明/未開」、「理性/非理性」という二項対立を維持するイデオロギー装置となり、そこでアフリカの哲学的伝統は「未開」のものとして完全に排除され疎外されたというわけだ。
ヘンリーは次のように述べている。
この伝統の中では、「アフリカ的で文明的」や「ヨーロッパ的で原始的」という言葉は成り立たない。同じ理由で、「アフリカ的で哲学的」や「ヨーロッパ的で非哲学的」という表現も不可能である。[★9]
クレオールに哲学は含まれない
植民地支配がつくりだした不均衡な「対話的枠組み」と「アフリカ哲学の完全なる排除」。それゆえ、その構造を抱え込んでしまったカリブ海哲学においては、文学や音楽とは異なり、クレオール化が進まなかった。
「クレオール」とは、カリブ海において、当初「旧世界に起源を持ちながら、新世界で生まれた人々」を指すために用いられた言葉である。その語源は、ラテン語のcreare(育てる、生み出す)に遡り、スペイン語criolloに由来する。つまり端的にいえば、カリブ海に展開された植民地に生まれたヨーロッパ人たちのことを意味していた。
「クレオール」という概念は植民地主義の残酷な歴史と切り離すことはできない。スペイン植民地では当初、「クリオーリョ」(現地生まれのスペイン系)と「ペニンシュラーレス」(本国スペインから渡来した人々)が厳格に区別されていたが、やがてその線引きは曖昧となり、白人・黒人を問わず植民地生まれの人々が「クリオーリョ」と総称されるようになった。17世紀には、英領では「クリオールcreole」、仏領では「クレオールcréole」が同様に使われ、やがて言語や人間だけでなく、現地で形成された文化や慣習全般を指すようになっていく。
バルバドス出身の詩人で歴史家、カマウ・ブラスウェイト(Kamau Brathwaite)は、さらに「クレオール」という言葉の語源を掘り下げ、criolloが「育む・養う」を意味するcriarと、「植民者」を意味するcolonに結びついていると分析する。つまりブラスウェイトの定義によれば、クリオーリョとは「引き返す場のない入植者」、すなわち「先祖代々の土地ではなく植民地に生まれ、その土地と同一視される人々」のことなのである[★10]。
ブラスウェイトが指摘したのは、ジャマイカの黒人奴隷たちが「奴隷主と同じぐらい有意義で確かな文化的生活」を営んでいたという事実だった[★11]。
彼の「クレオール社会論」にもとづく理解によれば、奴隷制社会にはヨーロッパとアフリカという「ふたつの偉大な伝統」が持ち込まれ、それらがカリブ海で出会うことにより「正真正銘の地域的な慣習」が育ち、結果として「奴隷の『民族』のあいだでアフロ・クレオールという小さい文化」が生まれることになった[★12]。こうして形成されたのが、カリブ海特有の混成的文化である。
そのような混成的文化を説明するための概念が「クレオール化」である。ブラスウェイトにとってクレオール化は、カリブ海に運ばれた異なる文化が、ただ並存するのではなく、歴史的な人種混淆を反映しつつ新たな文化へと変容していく過程を指す。
したがってこの概念は、「中間航路 Middle Passage」がアフリカ文化を完全に消し去った」という奴隷制の過去をめぐるよくある見方を拒否するものだ。むしろ彼にとって「中間航路」とは、「黒人をアフリカから切り離す破壊的経験」ではなく、「アフリカの伝統とカリブ海の新しい現実を結びつける水路」なのである[★13]。
さらに彼はクレオール化を二重の過程として説明する。第一の過程として「文化変容 acculturation」がある。これは権力や威信によって一方の文化(ヨーロッパ)が他方(アフリカ奴隷)を結びつけ支配する関係のことだ。しかしその抑圧的結合からは、第二の過程である「文化相互作用 interculturation」も派生してくる。これは非計画的で相互浸透的な文化交流のことを意味している。
ブラスウェイトは、ヨーロッパがアフリカ文化を根こそぎ奪ったとする旧来の「プランテーション社会論」の前提を退け、むしろ両者の相互作用からカリブ海独自の文化が生まれたと考える。そして、この文化的な相互作用こそがアフリカ系住民の主体性を示すものだと強調する。ブラスウェイトが「クレオール社会論」として捉える彼らの「文化的行動」が、アフリカの伝統を生き延びさせると同時に、それがヨーロッパから移植された文化や生活をもつくりかえていったのだ[★14]。
ところが、カリブ海において発生していたこのクレオール化(文化相互作用)に、哲学は含まれていなかった。音楽や宗教、言語、そして文学などではクレオール化が進んだ一方で、哲学は依然としてヨーロッパ思想が独占する領域とされ、アフリカ哲学は体系的に排除され続けたのである。
カリブ哲学のこのような状況を引き継いでしまったのが、ファノンを含めた20世紀のカリブ海知識人たちだった。
非存在の地帯
ファノンは幼少期から、植民地世界における西洋哲学優位の価値観の影響を受け、その内部に深く取り込まれていた。
そのことを象徴するひとつの例が、マルティニークで学生だった頃、ファノンが「ベルクソン」というあだ名で呼ばれていたというエピソードだろう[★15]。しかし彼はやがて、同郷の詩人エメ・セゼールから強い影響を受ける。セゼールは、黒人の文化や歴史を積極的に肯定し、西洋中心主義への抵抗として「黒人性」を掲げる思想運動「ネグリチュード」を提唱していた。植民地社会で劣等感を刷り込まれた黒人青年にとってネグリチュードは自己肯定を回復するための力強い言葉であり、ファノンもそこに共鳴し、「黒人であること」を積極的に肯定する必要を感じた一人だった[★16]。
だが、ファノンは黒人性を全面的に押し出すセゼールの枠組みをたんにそのまま受け入れるのではなく、そこからの思想的転回を模索しはじめる。たとえば『黒い皮膚・白い仮面』におけるファノンの目標は、外的な植民地制度の打破だけではなく、カリブ海のアフリカ系住民に植え付けられたコンプレックスから生じる実存的問題を克服し、「黒い皮膚の人間を、彼自身から解放するということ」に置かれていた[★17]。
ファノンがマルティニークでの自らの体験を手掛かりに描き出したのは、カリブ海の黒人に共通する心理的構造だった。それは単なる個人の問題ではなく、植民地支配の下で体系的に植え付けられ、白人優位の価値観を内面化することによって形成された集団的な劣等コンプレックスである。
黒人は自らの皮膚や文化を劣ったものと見なし、「白くなること」こそが人間性や尊厳を獲得する唯一の道だと信じ込む。ファノンが「乳白化」と呼ぶこの願望は、白人のまなざしを内面化し、そこに同一化しようとする心理的衝動にほかならない。この願望は言語や文化を通じて構造化されている。フランス語を話すアンティル諸島の黒人にとって、本国のフランス語を習得し、クレオール語を放棄することは単なる言語の選択ではなかった。それは「乳白化」の過程そのものであった[★18]。
ファノンはこう述べている。「アンティルの黒人は、フランス語を自分の国語とすればするだけ、よりいっそう白人に近づき、すなわち本当の人間に近づくと信じている」[★19]。学校ではクレオール語を話すことが軽蔑の対象となり、家庭でも使用は咎められる。こうした言語的同化は文化的帰属の問題ではなく、白人に承認されるために自分を作り替える心理的要請だった。流暢なフランス語を話すことによって、黒人は「白人の世界」に受け入れられると考えたのだ。
ファノンがこれらを「白い仮面」と呼んだのは、黒人が自らの存在を白人の価値観で覆い隠し、人間としての承認を白人に委ねてしまっている姿を示すためだった。
アンティル諸島では、学校で《われらが祖先ゴール人》を絶えず反復させられる黒人の子供は探検家や文明をもたらす教化者、野蛮人に審理を、純白の心理をもたらす白人に自己を同一視する。自己同一視があるのだ。つまり黒人の子供は主観的に白人の態度をとるのだ。彼は白人であるヒーローに自己の攻撃性の一切を託する[……]。こうしてアンティル諸島の子供のうちには、本質的に白人のものである、ある態度、物の見方、考え方が次第に形成され結晶化するのが見られる。[★20]
「白い仮面」は、文化の領域でも繰り返しその存在が露になる。映画や漫画の中でも黒人は常に野蛮で滑稽な、しばしば性的に逸脱した存在として描かれる。喝采を浴びるヒーローは白人であり、黒人はそのヒーローに自己を重ねることでしか、自分を「人間」であることを確認できない。こうして黒人は、文化に埋め込まれた白人を理想的人間像として提示する価値観に同一化し、結果的に深刻な自己疎外に陥っていく。ファノンは、それを「文化的強制」と呼ぶ。つまり、「アンティルの黒人はこの文化的強制の奴隷である。かつて彼らは白人によって奴隷にされた。今は自分を奴隷化する。ニグロは語のあらゆる意味において白人文明の犠牲者である」[★21]。
カリブ海社会のあらゆる側面が黒人に「白い仮面」を被らせる。だがファノンの議論は、単なる社会批評や文化批評にとどまらない。その「仮面」が剝ぎ取られる瞬間──自らが白人と同等の人間であるという虚構が現実によって否定され、黒人が「非存在の領域」に突き落とされる瞬間──にある実存的危機こそが、彼が明らかにするものだ。
ファノンはこの実存的危機の問題を「非存在の地帯 zone of nonbeing」として概念化した。そこは、自我が崩壊し、白人の視線によって固定され、主体としての力を失うおぞましい領域である。しかし同時に、その実存的恐怖を突破するならば、植民地化された人間にとって新たな主体の誕生が可能となる根源的地点でもある。
「驚くべきほど不毛で乾ききった地帯、極度にむき出しにされた丘の斜面、本来的なほとばしりはここに源を発するかもしれない」[★22]。このように「非存在の地帯」を描写するファノンが、フランスで「ニグロ」と呼ばれた自らの体験を通して書き記したのが以下の文章だ。
「ニグロ野郎!」あるいは単に、「ほらニグロだ!」。
私は事物に意味を担わせるつもりでこの世界に生まれて来たのであった。私の心は世界の根源に存在したいという欲求に充ち溢れていた。ところが私は他の数多くのもののうちのひとつにすぎぬ自分を発見したのだ。 この圧倒的なものとしての性質のうちに閉じ込められて、私は他者に哀願した。他者のまなざしは私を解き放つ。他者のまなざしを受けて私の身体は急に滑らかになり、失ったものと考えていた軽やかさを取り戻す。他者のまなざしは私を世界から不在ならしめることによって世界に私を返すのだ。ところが向こう側の斜面で私はつまずく。他者は身振りや態度やまなざしで私を着色(fixer)する。染料がプレパラートを着色・固定するように。私は激昂し、釈明を求めた……。なにをしても無駄だった。私はこなごなに砕け散った。[★23]
この経験からファノンは、黒人の「人間」としての自我がいかに崩壊するかを説明する。
カリブ海のアフリカ系住民は、白人のように話し、振る舞い、文化的コードを身につけることで、自らを白人と同等の人間だと信じ込む。しかし一度「白人の世界」に足を踏み入れると、彼は白人のまなざしにその黒い肌を晒され、「人間」としての存在を剥奪される。どれほど「白人である」と内面で信じていようとも、白人のそのまなざしはかれらの幻想を打ち砕き、外部からその虚構のアイデンティティを破壊する。黒人は白人の視線の中で対象化され、「白い仮面」を剝ぎ取られ、自らの身体が「黒い皮膚」という劣等の意味を帯びた記号として固定されるのだ。
皮膚そのものが逃れ得ない意味を負わされる──これが、ファノンの経験をもとにした「非存在の地帯」であり、そこで黒人を待ち受けるのは、「劣等感」どころか「非在感」なのである[★24]。
しかしこの自我の崩壊という体験は、「非存在」に晒される苦痛にはとどまらない。そこにはむしろ、「非存在の地帯」を超えて、「無限」へと広がっていく可能性への意識が垣間見えている。
私は自分の心が世界と同じ位広大なのを感ずる。真実、私の心は最も深い河と同じ位深いのだ。私の胸は無限に広がる力を持っている。私はこの世へのささげ物だ。だのにその私に不具者の謙譲さを勧めるのか……。きのう私は世界に目を開いたとき、空が顚倒するのを見た。私は身を起こそうとした。だが内臓を摘出された沈黙が翼もなえて私の方に逆流してきた。無責任に、〈虚無〉と〈無限〉に馬乗りになって、私はさめざめと泣きだした。[★25]
ここで示されているのは、「非在感」の恐怖に打ち勝ち、疎外の真っただ中から自己創造へと跳躍する可能性である。すなわち「非存在の地帯」は、自我が崩壊するおぞましい領域なのだが、それを超えた先には主体性が生まれ変わる無限の可能性も広がっている。これをファノンは、「真正な飛躍」と呼んでいる[★26]。
ファノンの独自性は、この極限の地帯を恐れることなく探究した点にあると言えるだろう。その探究を通じて、彼はアフリカ系カリブ海住民の実存的分析を新たな哲学的深度へと導くことができたのである。
まさしく黒人たちが直面してきた非存在の恐怖から、黒人の自我が立ち現れ、また黒人がみずからの存在を日常的に維持するために立脚しなければならない「地盤」が露わになった。ファノンが「本来的なほとばしり」と呼んだものは、まさにその、カリブ海の哲学が依って立つ根源的な思想的地平に他ならないのだ[★27]。
ファノンの貢献と限界
しかし意外なことに、ファノンは、カリブ海のアフリカ系住民はこの「本来的なほとばしり」へと至る権利を持っていないと断言する。「多くの場合、黒人は、真の〈地獄〉へのあの降下を実現する特権を有していないのだ」[★28]。
ヘンリーの言葉を借りれば、これはファノンが「アフリカ系カリブ海の伝統的な言説が、この領域に広がる困難な海を個人が進んでゆくことを可能にしなかった」という判断を下したことを示している[★29]。カリブ海の言葉はアフリカ系住人たちに「本来的なほとばしり」をもたらさないのだ。そのため、ファノンはアフリカ系カリブ海住民の実存的問題を探求するための言語と概念を、ヨーロッパの実存主義に求めざるを得なかった。
それゆえファノンは、ヘーゲルやアドラー、キルケゴール、ヤスパースを引用し、カリブ海のアフリカ系住民が経験する自己疎外と主体性の崩壊を語る。その語り口はまさに西洋の実存主義者のものである。たとえばファノンは次のように言う。
こうして即自―対自としての人間現実は、闘争においてのみ、また闘争が内含する危険によってのみ完遂されることができる。この危険は、私が自分自身の価値について抱いている主観的現実性を普遍妥当的な客観的真理に変えることにほかならぬ至高善へ向かって生を乗り越えるということを意味している。[★30]
ファノンは、アフリカ系住民の実存的経験を語りながらも、その言葉はヨーロッパ哲学に依拠していた。ヘンリーが言うように、ファノンにおいて「言葉はヨーロッパ実存主義のそれであり、経験はアフリカ系カリブ海のものなのだ」[★31]。
重要なのは、この借用が単なる模倣ではなかったということだ。ファノンは闘争の思想としてヨーロッパ実存主義を援用しつつ、それをアフリカ系カリブ海住民の経験に即して再構築した。
具体的に言えば、ファノンはサルトルの「無」にもとづく実存分析を、植民地主義が作り出した「黒人性の否定」という歴史的・文化的文脈に組み込み、さらに心理分析を加えることで、「精神分析的実存主義」とも呼べる独自の哲学を築いた。これによってファノンは、カリブ海哲学を西洋近代の閉じた合理的主体像から解き放ち、無限性に開かれたより動的な「人間」の主体像へと向かわせる原動力を与えるという貢献を果たしたのである。
しかし、ここにこそファノンの限界が潜んでいる、とヘンリーは指摘する。すなわち、彼はアフリカ伝統思想、とりわけ運命や宿命をめぐる「アフリカ的存在論」を、自らの理論に取り入れることはなかった[★32]。ヘンリーが注意を促すのは、ファノンの「バントゥ哲学 Bantu Philosophy」にファノンが示した消極的姿勢である。
バントゥ哲学とは、アフリカの世界観を「生命力」の概念を中心に体系化しようとする試みで、1945年にベルギー人フランシスコ会宣教師プラシード・タンペルが著した書物『バントゥ哲学』によってよく知られるようになった。その哲学においては、あらゆる存在が、単なる「物質」ではなく「力」として理解され、その相互作用の中に、人間や共同体、自然や祖霊、神々が位置づけられる。言い換えれば、存在論・倫理・宗教が分かち難く結びついており、そこで人間の目的は、生命力を高め、調和させることだと考えられるのだ。
『アフリカ哲学全史』(ちくま新書)の著者、河野哲也の説明を借りれば、「バントゥの叡智は、認識する「力」は神から与えられた力であり、真の知識は形而上学的(神との関係)であることの自覚からなっている。知恵と知識は、この存在=生命力についての知識に他ならない」[★33]。つまり、主体は孤立した「自己」としてではなく、共同体と霊的秩序の中で階層的に規定されるのである。
ファノンも『黒い皮膚・白い仮面』のなかでバントゥ哲学を参照しているが、ただし、その文脈は批判的であった。彼は南アフリカで黒人労働者が虐殺される現実を前にして、こう吐き捨てる──南アフリカで黒人鉱山労働者が撃ち殺されているときに、「バントウ族の存在論に関する思索にどんな意味があるというのか?」[★34]。
ファノンにとって、植民地支配は単なる文化的次元のものではなく、人種差別にもとづく暴力と制度による物理的・経済的支配にほかならなかった。それに対抗するためには、ヨーロッパの言説をも打ち破る力を持つ武器を与えてくれる、いわゆる「闘争の哲学」が必要だった。しかしながら、人種差別と植民地支配によって育てられ、大きく口を開けて待ち構える「非存在の地帯」を前にすると、バントゥ哲学の「生命力」の概念や霊的調和による自我形成の世界観は、対抗力を持たないようにファノンには感じられたのだ。
さらにファノンは、セネガルの歴史学者・人類学者シェイク・アンタ・ジョップがタンペルの『バントゥ哲学』に寄せた序文を引用する。いわく、
問われるべき問題は、黒人の精髄はその独自性をなすもの、すなわち、道徳の維持のために強制され容認されている人間性の歪曲ではなく、生命の幸福な尊厳との自然な調和であるところの、あの魂の若々しさ、人間および被造物への生来の尊重心、生きる喜び、平和といったものを涵養すべきであるかとどうかという問題である。[……]われわれにいえることは、革命的意志と考えられた文化という概念自体、進歩という概念と同じく、われわれの天性に相反するものだということである。[★35]
ジョップが示す、黒人哲学に見られる神々や祖先との自然な調和の称揚と、それによる「革命的意志」の否定に対して、ファノンはこのように言い放つ。
ちょっと待ってくれ! バントウ族の生存が非在の、不可測なものの次元に置かれているときに、バントウ哲学のうちに〈存在〉を見出すもなにもないだろう。もちろんバントウ哲学は革命的意志を基にして理解できるはずはない。だがそれはまさにバントウ族の社会は閉じた社会であるからして、そこでは〈諸力〉相互間の存在論的関係に搾取者が取って代る現象が見られないからこそである。ところが知ってのとおりバントウ社会はもはや存在しない。また人種隔離は存在論とはいかなる関係もない。無駄なおしゃべりはもう沢山だ。[★36]
ファノンがバントゥ哲学を放棄したのは、存在論というものそれ自体を否定していたからではない。むしろ、バントゥ存在論が現実の政治状況や人間の具体的な経験から切り離され、黒人から「革命的意志」を取り上げてしまうことへの憤りがあったからなのだ。
黒人が「非存在の地帯」に閉じ込められている状況で、革命ではなく調和を探求するバントゥ存在論をいくら語っても、現実の物事は何も変わらない。アパルトヘイトや人種隔離という大きく口を開けた「非存在の地帯」は、「存在論とはいかなる関係も」なく、そこにあるのは単純に政治的・身体的暴力と人種差別である。
そのようなファノンが重要だと考えたのは、「実存は本質に先立つ」というテーゼのもと、歴史は変わりうるという信念を出発点とする批判的実存主義のほうであった。存在の意味は、「黒人とは何か」という宗教的問いではなく、植民地的暴力のただ中で己の実存をかけて生きる闘争の経験に根ざして問われなければならない。
そうした意味で、『黒い皮膚・白い仮面』が目指していたのは、黒人を「非存在の地帯」に押し込める人種主義社会の現実に対して、解放の契機となる新しい存在論を切り開くことにあったといえる。ファノンが必要としたのは、「黒人には独自の存在論がある」と説き募る「無駄なおしゃべり」ではなく、現実の植民地主義と闘う革命的主体の創出することのできる「武器」だったのだ。
ファノンがとったこの戦略にヘンリーは一定の理解は示している。だがその結果、ファノンはカリブ海哲学における「ヨーロッパ依存」を強化し、文学や音楽、宗教が達成していたようなクレオール的融合を阻むことになったとも説明する。
文学や音楽はアフリカとヨーロッパの要素を結合させ、固有の表現形態を創出することに成功したが、哲学は依然として「ヨーロッパの周縁」にとどまり続けた。ファノンの思想は植民地主義批判の武器として決定的な貢献を果たしながら、それと同時に、その依存構造そのものを揺るがすには限界があったのである。
この点については、カリブ海の研究者からだけでなく、アフリカ研究の側からも指摘がなされている。たとえば中東・アフリカ地域研究者、キャロリン・ルーニー(Carolyne Rooney)は、ファノンが植民地的搾取に抗する闘争の哲学を求めるあまり、アフリカ伝統思想を無力なものとして切り捨てていると指摘している。ファノンのバントゥ哲学批判は、「全面的に修辞的で恣意的な身振りであり、アフリカ史への無知を示すと同時に、ファノン自身がアフリカの遺産を失い、フランス文化への同一化を得たことによる個人的な疎外感にもとづいているように見える。これはまた、黒人の子どもたちはヨーロッパの歴史だけでなく、自らの歴史についても教育されねばならない、というファノン自身の主張にも反している」と言うのである[★37]。
ファノンによるバントゥ哲学の切り捨ては、必ずしもアフリカ思想の可能性を公平に評価した上でのものではなく、むしろカリブ海出身の知識人であるがゆえの、彼自身のアフリカ由来のアイデンティティの断絶とヨーロッパ哲学への依存を反映しているのだ。
これまでの議論をここで確認する。
ファノンにとって、アフリカ哲学はその運命観、生命力の思想、調和性による存在論を誇るが、革命的意志を取り上げるその思想は、実際に目の前で展開されている植民地支配という暴力に対抗する武器にはなり得なかった。だからこそファノンは、西洋実存主義の権威を援用し、それを「闘争の哲学」へと転用しようとした。アメリカの黒人たちが闘っている一方でその闘争の意志すら奪われたカリブ海の黒人たちが、立ち上がり闘争を始めるための「武器」となる哲学を、彼は欲したのである。
しかし同時に、この選択はカリブ海哲学における「ヨーロッパ依存」を強化することにもなった。文学や音楽、宗教といった領域では、アフリカ的要素とヨーロッパ的要素のあいだに融合が進み、クレオール的な新しい表現が生まれていた。しかし哲学においてはそうした統合は起こらず、西洋哲学の周縁に「劣ったもの」や「野蛮なもの」として留まる構造が温存されてしまった。
ヘンリーが強調するのは、ファノンが「非存在の地帯」という実存の深層を恐れずに描き出した独自性は疑いえない一方で、それを表現するための言語と概念は依然としてヨーロッパの枠組みに依存していたという点である。すなわちファノンは、植民地主義批判の武器として決定的な貢献を果たした一方で、その根本的なヨーロッパ哲学優位の構造を揺るがすには至らなかった。ヘンリーにとって、この限界はファノン個人の失敗ではなく、むしろカリブ海哲学がその長い歴史を通して抱え込んできた構造的制約そのものの表れだったのだ。
ファノンと、その先へ
ヘンリーの議論が示すのは、このようなファノンの選択が、戦略的には理解できるものの、結局としては、カリブ海哲学のヨーロッパ偏重を温存することになってしまったという点である。
アフリカ的な存在論は、植民地以前の世界から培われてきた、「自己」と「共同体」、「人間」と「宇宙」を結びつける豊かな思想の体系を有していた。たとえば、バントゥー語群のングニ諸語に由来する「ウブントゥ」は、個人を常に共同体との相互関係において捉える概念である。ネルソン・マンデラが最も信頼を寄せた盟友であり、彼とともにアパルトヘイト撤廃運動の精神的支柱となったデズモンド・ムピロ・ツツ大主教は、このウブントゥの最大の提唱者として知られる。彼はこれをアフリカ伝統の共生意識として称揚し、和解の根幹に据えた。このようなアフリカ的存在論は、サルトルに代表される近代ヨーロッパ実存主義が「個人の孤独」や「不安」、「虚無」を問題としてきたのとは対照的に、他者との共生を追求し、存在を「力」と「関係性」の網の目の中で捉える、包括的で独自の哲学であった[★38]。
もしファノンがこのようなアフリカの知的伝統を自らの実存分析に積極的に取り込んでいたならば、カリブ海哲学はより独自の展開を遂げていた可能性がある。すなわち、彼の実存主義が「非存在の地帯」を、ヨーロッパ哲学的な「個の心理的崩壊」の契機としてのみならず、アフリカ哲学が編み出した「共同体的・宇宙的な再生の契機」としても捉えられていたならば、カリブ海哲学のクレオール化はさらに早く進んだかもしれなかった。
ところで、ファノンと同様に、タンペルのバントゥ哲学とベルギーによるコンゴ統治との共犯関係を痛烈に指摘していた一人に、エメ・セゼールがいる。セゼールは、タンペルによるバントゥ哲学を激しい言葉をもって切り捨てており、弟子であるファノンが後に展開する哲学的批判の先鞭をつけていたのだ。
セゼールは『植民地主義論』の中でこのように書く。
さらに御立派なのはタンペル神父だ。コンゴにおいて略奪が行われ、拷問が行われ、ベルギー人植民地支配者があらゆる富を強奪し、一切の自由を抹殺し、一切の誇りを圧殺し……心安らかであることを、タンペル神父は承認する。[★39]
セゼールにとって、ベルギー人のタンペルによる議論は、植民地支配を正当化し補完する言説にすぎず、その白人至上主義的な文化への価値づけ自体が植民地権力に奉仕するものだった。彼はこのように、端的にバントゥ哲学の問題点を指摘している。
バントゥー人の生命力の改装の頂点には白人が位置し、とりわけベルギー人が、さらに言えばアルベールやレオポルドが位置するのである。申し分のない結果だ。そしてこういうすばらしい結論が得られる。バントゥー人の神はベルギー植民地主義秩序の保証者であり、その秩序を侵そうとするバントゥー人はすべて瀆神者であると。[★40]
しかし、カリブ海の知識人であったセゼールやファノンの批判は、いずれもタンペル的アフリカ哲学の植民地主義的性格を摘発するという点では鋭利であったものの、それを超えてアフリカの哲学的資源を積極的に再発掘・再構築する方向には進まなかった。つまりは、カリブ海哲学の「対話的枠組み」におけるヨーロッパ偏重を是正することはできなかった。 セゼールは詩的言語によってアフリカ文化の創造力を讃え、ファノンはヨーロッパ実存主義によって主体の解放を理論化したが、いずれもアフリカ内部の思考体系を哲学として展開する姿勢は見せなかったのである。
この限界を突破しようとしたのが、ベナン出身のポーラン・ウントゥンジ(Paulin Hountondji)やカメルーン出身のファビアン・エブシ゠ブラガ(Fabian Eboussi-Boulaga)といった、次世代のアフリカ人思想家たちであった。
彼らは1970年代に、バントゥ哲学の営みを「民族哲学」(ethnophilosophy)と呼び、哲学ではなく民族学や人類学の延長にすぎないと断じた。いわく、民族哲学は西洋が他者として作り上げた「アフリカ像」を内面化し、その像を本質主義的に再生産するに留まっているのだ。こうした批判は急進的な転換をもたらし、アフリカ人が自らの経験と思考を哲学として語るための言葉を目指す、新しい出発点が形成された。
だが、これらが起きたのはアフリカにおいてであった。他方、カリブ海には、コロンブスの「発見」以降の入植やプランテーション経営のための奴隷制の展開の経験を通して、アフリカとはまた異なった歴史を有する世界が形成されていた。そこには、強制労働や伝染病によってほぼ絶滅した先住民に代わる労働力として、アフリカ大陸から膨大な数の人々が奴隷として強制移送された。植民地主義によって、かれらは言葉や信仰といった「祖先の地」とのあらゆる紐帯を暴力的に切断された存在である。現在では島々の人口の大多数をアフリカ系住民が占めるものの(トリニダードやガイアナのようにインド系年季奉公労働者の子孫がアフリカ系と並んで主要な構成層をなす共存社会もあるが)、そこには常に歴史的な「断絶」の深淵が横たわっている。
この、いわば「アフリカから切り離された」歴史を持つカリブ海において、セゼールとファノンによるバントゥ哲学批判は、植民地主義批判として不可欠な役割を果たしたものの、ウントゥンジやエブシ゠ブラガがアフリカ哲学において準備したような出発点にはならなかった。つまり、かれらのバントゥ哲学批判は、カリブ海におけるアフリカ内在的な哲学の再構築には至らなかったのだ。
ヘンリーが最終的に提唱する、カリブ海における「哲学のクレオール化」とは、まさにこのバントゥ哲学を含むアフリカ的思索を、植民地的偏見から解放し、ヨーロッパ思想との対等な混淆の中に位置づけ直そうとする試みである。
彼はカリブ海における哲学と他の文化領域を比較し、次のように述べている。
ヨーロッパ的アイデンティティが依然として持続していることを考えれば、ファノンの哲学が、ジョージ・ラミングやV・S・リード、ウィルソン・ハリス、サム・セルヴォンらの作品がカリブ海文学のクレオール化を導いたようには、カリブ海哲学のクレオール化につながらなかったのも不思議ではない。カリブ海哲学は、なお同様の変化を経験していないのである。[★41]
カリブ海哲学のクレオール化を後押しするために、日本ではいまだ知られていない英語圏カリブ海の知識人たちを紹介しておくことが有益だろう。
特に言及しておくべきは、先にも名前を出した、バルバドス出身の詩人で歴史家のカマウ・ブラスウェイトだ。彼は、カリブ海文化に見られる「ノンモ Nommo」という概念について思索を深めてきた。
「ノンモ」は、奴隷としてカリブ海にも多く連れてこられた西アフリカのドゴンの人々が描く宇宙観において、「言葉が世界を生成する力」を示す概念である。作家のヤンハインツ・ヤーンは、『ムントゥ──新アフリカ文化史概説』(邦訳は『アフリカの魂を求めて』、せりか書房、1976年)において、「あらゆる生命を産み出し、語《ワード》として「事物」に影響をおよぼすところの生命力」である「ノンモ」をこのように紹介している。
「ノンモとは」と、オゴトンメリはいう、「水と熱なのだ。語を担う活力は、水でもあり熱でもある水蒸気となって、口より発する。」したがってノンモとは、水と、火の輝きと、種子と、語とが一体となったものである。生命力であるノンモは、こういうものとして流動体であり、森羅万象に声明を賦与し、森羅万象に浸透し、森羅万象を生起せしめる精神的・物質的流動性の統一である。[……]そして人間は、語を支配し得る力を所有しているからして、この生命力に指図するのは人間である。語をつうじて、人間は生命の力を受けとり、ほかのもろもろの存在とその力を分有し、こうして人生の意味を達成するのである。[★42]
ヤーンによれば、アフリカ哲学において、言葉は、単なる道具や記号ではなく、現実を創造する生命原理を成している。それを意味するのが、この「ノンモ」という概念なのだ。
ブラスウェイトは、アフリカ文化がカリブ海文化にどのように生き残っているかを論じるなかで、「ノンモ」の実践について触れている。
「言葉(ノンモ、あるいは名)は秘められた力を宿していると考えられている」[★43]と彼は言う。アフリカ的宇宙観に根ざしたノンモは、カリブ海において言語やリズム、そして人々の記憶と深く結びついている。
たとえばブラスウェイトは、歴史家としての素養を生かし、イギリスの小説家マシュー・グレゴリー・ルイスが記録したジャマイカでの経験に、人々によるノンモの文化的実践を見出している。
ルイスは、自身が所有していたプランテーションがあるジャマイカを1815年から1816年にかけて訪れ、奴隷たちの間で見られたある特定の態度を記録している。たとえばある日、子どもが病気で病院に預けられていたアフリカ人奴隷の女性が、ルイスにその子の名前を「ルシア」から別のものに変えてくれるよう頼んできた。女性はそのとき、いまの名前のままでは子どもの状態が改善しないと確信していた、とルイスは記している。この記録は、アフリカ系の母親が子どもの生死にまで「名前の力」が関わると信じていたことを示している。ノンモの概念が単なるアフリカ的宇宙観ではなく、カリブ海の日常的な実践と信仰の中で具体的に作用していたことを証明しているのである。
ルイスの記述をもとにして、ブラスウェイトはこう述べる。
この言葉の概念と用法は、ブラック/アフリカ世界全体に見られるものである。それは現代アフリカ文学だけでなく、伝統的なアフリカ文学にも存在している。しかし、すでに議論したいくつかのアフロ・カリビアンの断片が持つ形而上学的かつ象徴的な性質が示すように、これだけにとどまらないのだ。言語は[……]生命に影響を与える力を持つものとして考えられるのである。[★44]
このようにブラスウェイトは、カリブ海における「ノンモ」というアフリカ文化的実践に注目し、言葉が世界や社会を変革する力を持つことを強調しているのである。その議論を通じて浮かび上がるのは、アフリカ系の人々がカリブ海において実践していた「クレオール化のプロセス」にほかならない。
ファノンがアフリカ哲学を闘争の武器にならないとして退けたのに対し、文学の領域において、ブラスウェイトはむしろ、カリブ海の日常生活においてアフリカ文化が残存していることに注目し、言葉と存在を結びつけるアフリカ思想の力をカリブ海文学に組み込んだのである。ふたりの対比は、カリブ海の英語圏と仏語圏、そして哲学と文学におけるアフリカ文化の創造的受容の差を示唆していると言えるだろう。
ファノン以後の世代がカリブ海において担うべき課題は、文学だけでなく哲学でもクレオール化を実現することだ。
現在では、本稿が導きとしてきたパジェット・ヘンリーだけでなく、ルイス・ゴードン(Lewis Gordon)、ジェイン・アンナ・ゴードン(Jane Anna Gordon)、アーロン・カムギシャ(Aaron Kamugisha)、ニール・ロバーツ(Neil Roberts)といったカリブ海哲学者たちが、ファノンの思想をカリブ海の経験に「読み戻し」ながら、この「哲学のクレオール化」プロジェクトを力強く推進している。そこでたとえばアフリカの運命観や生命力の思想、祖霊との関係性といった要素が再評価され、マルクス主義や実存主義、精神分析といった西洋哲学と交差されることで、カリブ海哲学は初めて、伝統的な「対話的構造」によって形成されたヨーロッパとアフリカの植民地的な二項対立を超え、「カリブ海自身の声」を獲得できるだろう。
ファノンが遺したのは、この課題に取り組むための道筋であった。ファノンを引き継ぎ、彼とともにその先へと跳躍してゆくことこそ、カリブ海哲学に携わる者たちの使命なのである。
★2 ファノンをカリブ海に位置付けた数少ない事例であり、貴重な資料として、実際にマルティニークに赴き現地を取材した海老坂武による『フランツ・ファノン』(みすず書房、2006年)を挙げることができる。
★3 岡真理、崎山政毅、中村隆之「〈討論〉人間の全的開放と暴力——ファノン再読のために」、『思想』1210号、岩波書店、2025年、36頁。
★4 同書、38–39頁、40頁。
★5 フランツ・ファノン『黒い皮膚・白い仮面』新装版、海老坂武、加藤晴久訳、みすず書房、2020年、36頁。
★6 同書、38頁。また、ファノンは同書の後半では、マルティニークのようなフランス植民地におけるアフリカ系たちに闘争の意志も術も欠けていることに対し「自分を嚙み他を嚙むべく運命づけられている」と表現する一方で、「アメリカではニグロは闘っている」という観点から「アメリカ黒人は別のドラマを生きている」と述べている(同書、239頁)。
★7 Henry, Caliban’s Reason, p.71.
★8 Ibid., p.77.
★9 Ibid.
★10 Edward Brathwaite, Contradictory Omens: Cultural Diversity and Integration in the Caribbean, Kingston, Jamaica: Savacou Publications, 1974, p.10.
★11 Edward Brathwaite, Development of Creole Society in Jamaica: 1770-1820, Oxford: Clarendon Press, 1971, p. 244.
★12 Ibid., p.309.
★13 Edward Kamau Brathwaite, Folk Culture of the Slaves in Jamaica, London: New Beacon Books, 1970, p.7.
★14 Brathwaite, Contradictory Omens, p.6.
★15 Nigel C. Gibson and Robert Beneduce, Frantz Fanon, Psychiatry and Politics, New York: Rowman & Littlefield, 2017, p.74.
★16 ファノンのネグリチュードへの姿勢にかんしては、以下を参照。中村隆之「フランツ・ファノンとニグロの身体──「黒人の生体験」再読」、『環大西洋政治詩学』、人文書院、2024年、237–274頁。
★17 ファノン『黒い皮膚・白い仮面』、31頁。
★18 同書、70頁。
★19 同書、40頁。
★20 同書、171頁。
★21 同書、206頁。
★22 同書、30頁。
★23 同書、129頁。強調は原著者。
★24 同書、16頁。
★25 同書、165頁。
★26 同書、247頁。強調は原著者。
★27「本来的なほとばしり」という言葉については、以下の論考でもカリブ海の「マルーン」という経験に照らし合わせて言及している。中村達「カリブ海の記憶と逃走/闘争する奴隷たち──ポスト西洋的な「自由」概念としてのマルーン化」、webゲンロン。URL=https://webgenron.com/articles/article20240319_01
★28 同書、30頁。
★29 Henry, Caliban’s Reason, p.81.
★30 ファノン『黒い皮膚・白い仮面』、236–37頁。
★31 Henry, Caliban’s Reason, p.82.
★32 先の対談で岡は、「近代西洋の男性中心主義を脱構築していくということは、この『ウブントゥ』を思想として語るような実践であるはずですが、しかしアカデミアにおいては、アフリカの土着の思想は、人間の普遍的な思想や哲学の知としてではなく、文化人類学の対象とされてしまうことが往々にしてあります」と述べている(岡真理、崎山政毅、中村隆之「〈討論〉人間の全的開放と暴力——ファノン再読のために」、『思想』、39頁)。この指摘に立ち返るなら、ファノンが『黒い皮膚・白い仮面』において示したアフリカ哲学への態度を、今一度検討する必要があるだろう。
★33 河野哲也『アフリカ哲学全史』、ちくま新書、2024年、295頁。中村隆之による「アフリカ哲学への招待──「他者の哲学」から「関係の思想」へ」(webゲンロン)もアフリカ哲学を知るうえで最適な羅針盤のひとつである。URL=https://webgenron.com/articles/article20240520_01
★34 ファノン『黒い皮膚・白い仮面』、198頁。
★35 同書、199–200頁。
★36 同書、200頁。
★37 Carolyne Rooney, African Literature, Animism and Politics, New York: Routledge, 2000, p.25. 奇しくもルーニーとヘンリーの議論は同年に世に出たものである。
★38 とはいえ、この「ウブントゥ」の持つ徹底した楽観主義に対しては、現代思想の観点から鋭い批判も向けられている。たとえばナイジェリア人哲学者のエマニュエル・チュクウディ・エゼは、「ウブントゥ」が理想主義に寄りすぎていることを、「行き過ぎ too much」と「不十分 not enough」というふたつの視点から批判している。「ウブントゥは、行き過ぎである。というのも──もしそれが語りかけようとしている現代アフリカ社会の描写が正確なものであるとするならば──ひとつのイデオロギーとして、ウブントゥは、『非日常的なもの』、すなわち幸運や奇跡、そして『本源的な善性』という曖昧な概念に依存しすぎているからだ。一方で、ウブントゥは不十分でもある。なぜなら、人間性の本源的な善性に対するそれ特有の楽観主義を、私が呼ぶところの『日常的なもの』によって補完──あるいはこう言ってもいいが、抑制──することに失敗しているからだ」(Emmanuel Chkwudi Eze, On Reason: Rationality in a World of Cultural Conflict and Racism, Durham and London: Duke University Press, 2008, p. 230)。
★39 エメ・セゼール『帰郷ノート/植民地主義論』、砂野幸稔訳、平凡社ライブラリー、2022年、168頁。
★40 同書、170頁。強調は原著者。
★41 Henry, Caliban’s Reason, p.87.
★42 ヤンハインツ・ヤーン『アフリカの魂を求めて』、黄寅秀訳、せりか書房、1976年、142頁。
★43 Kamau Brathwaite, Roots, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1993, p.236.
★44 Ibid., pp.239–41.


中村達




