はじめに──ヤン・ボードアン・クルトネ『民族の平和的共存は可能か』より|桑野隆
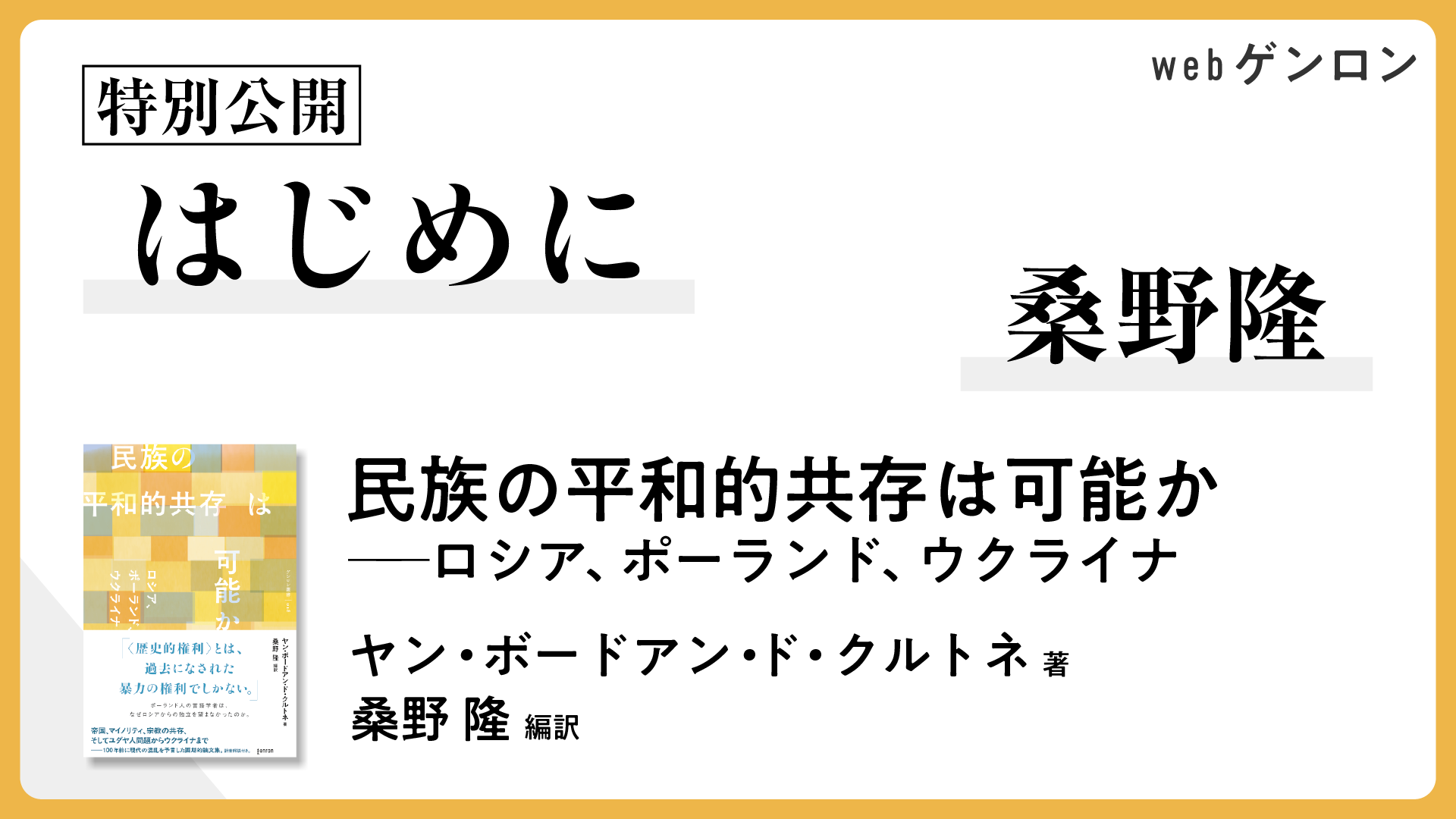
〈歴史的権利〉とは、過去になされた暴力の権利でしかない。──いまから約100年前のロシア帝国で活躍した言語学者、ヤン・ボードアン・クルトネ。ポーランド出身のクルトネは、社会問題や民族マイノリティ問題について多くの論考を執筆しながら、しかし祖国の独立は望んでいませんでした。筋金入りの平和主義者である彼は、民族や国家をどのように考えていたのか。当時の〈ウクライナ問題〉をどのように受け止めていたのか。11月25日(火)の書店発売をまえに、編訳者、桑野隆さんによる「はじめに」を特別公開いたします。(編集部)

日本では、ロシアによるウクライナ侵攻それ自体に関してはむろんのこと、ウクライナの政治・社会・文化、さらには歴史に関しても、ここ数年良書が相次いで刊行されており、ウクライナに対する関心は飛躍的に高まり、理解も深まってきたように思われる。
その一方、かの地に平和はいっこうに訪れないどころか、たたかいはパレスチナ・イスラエルでもはじまり、さらには世界各地で戦争・紛争状態が頻発している。
こうしたなか、出版や新聞・テレビの世界で目立つのは、当然のことながら──歴史的背景にも触れているとはいえ──現状報告や事態の具体的分析である。当面の軍事や地政学、あるいは政治・経済などの動きに着目したものが多い。あまりに苛烈な現実に直面している以上、具体的、実証的分析にまずは精力がそそがれるのももっともであろう。
しかし、はたしてそれだけでいいのであろうか。混沌状態がつづいているいまだからこそ、あらためて根本原理に立ち返ったような、いわば「反時代的な」ウクライナ論もあっていいのではなかろうか(「根本原理」である以上、問題はひとりウクライナにのみとどまるものではないが)。これが、1世紀以上もまえに独自の社会論、民族論を開陳していたひとりの言語学者の発言を広く紹介してみたくなった動機である。
ここにとりあげたポーランド出身の言語学者ヤン・ボードアン・ド・クルトネ(1845─1929)は、専門の言語学においてはすでに高く評価されているものの、19世紀末から社会評論活動にもたずさわり、新聞、雑誌などに300点近い文章を発表していたことは、あまり知られていない。だが実際は、現代でいえばノーム・チョムスキーのような、言語学と社会問題を架橋する存在であった。
民族マイノリティ擁護を中心として、「民族の平和的共存」、「人間の尊厳」、「個人の(選択の)自由」、「非戦」、「反・差別」をめぐってボードアンがくりかえしていた見解は、1世紀以上を経た今日にあっても異彩を放っており、独創的である。たとえば、1913年の発言から二箇所引いてみよう。
一般的にいって、いわゆる「歴史的権利」とは、過去になされた暴力の権利でしかない。「歴史的権利」によって、ありとあらゆる略奪、不法、残虐、不公正を正当化することができる。現代のロシアをつくりあげている昨今の略奪と征服もまた、「歴史的」事実であり「歴史的権利」となっている。(本書93頁)
プーチンの顔が浮かぶひとも少なくあるまい。「歴史的権利」を口実にすることの不当性を非難しているだけではない。そもそも「歴史的権利」に固執していては事態は解決しないというのが、ボードアンの持論でもあった。それゆえにボードアンは、(主たる活動場所の)ロシア帝国内だけでなく、母国ポーランドにおいても反感を買っていた。
強制的な「国家的措置」のすべて、「ウクライナ民族の民族的特質を剥奪しようとする」強制的な「感化策」のすべては、きわめて悲惨な結果を今日までもたらしてきた。[……]このようなすべての措置は、意識の高いウクライナ人の個人的・民族的尊厳にとどまらず社会的正義感をも侮辱することによって、はなはだ効果的な煽動や挑発となっており、民族的な感覚過敏、抑圧者たちに対する頑強な反抗や内に秘めた敵意を呼び起こしている。しかもこうした敵意は、概念の混同や批判的態度の欠如のせいで、統一国家体制志向の近視眼的な熱狂者や、上役からの命令の鈍感な遂行者に対してにとどまらず、なんら悪意のない同種族の人びと(このばあいでいえば大ロシア民族全体)に対しても速やかに広がりつつある。(本書42頁)
これまた、ロシアによるウクライナへの本格的な軍事侵攻が開始された2022年2月24日以降に強まっていくウクライナの人びとの心情、さらにはロシアの良識ある人びとがおかれた立場を、ほうふつさせよう。
あるいはまた、往時の東アジアを想起するならば、「ウクライナ」は「朝鮮」や「台湾」、「ロシア」は「大日本帝国」にも置き換えられよう。
むろん、今日のパレスチナ・イスラエル情勢もふくめ、世界各地の戦争・紛争状態にもあてはまる。
ボードアンの発言のこうした「普遍性」は、(本書にも散見されるように)「一般原則」にこだわる「原則主義」に起因するところが大きかろう。
*
ヤン・イグナツィ・ニェチスワフ・ボードアン・ド・クルトネは、ポーランド王国のワルシャワ近郊の町ラジミンで生まれた。当時ポーランド王国は、ウィーン会議(1814─15)の結果ロシア帝国内の分割領となっていた。
ワルシャワ中央学校(のちのワルシャワ大学)を1866年に卒業したボードアンは、その後プラハ、イエナ、ベルリン、ペテルブルグなどで言語学の研鑽を積み重ね、1870年秋から一年間ペテルブルグ大学に勤めたあと、1875年にロシア帝国内のカザン大学に准教授(のちに教授)の職を得ている。ただ、民族マイノリティ擁護が主因となって大学当局と対立し、83年に退職した。その後、ロシア帝国内のドルパト(現タルトゥ)大学、オーストリア領クラクフのヤギェウォ大学、ふたたびロシア帝国内のペテルブルグ大学などに勤めているが、やはりいずれの地においても思想や信念が関係した問題に見舞われている(本書所収の減刑嘆願書からもその一端はうかがわれよう)。
主たる活動領域であったロシアでは、ロシア語でイワン・アレクサンドロヴィチ・ボドゥエン・デ・クルテネと名乗っていた。1918年には、独立後まもないポーランドに帰国しワルシャワ大学に勤めているが、生涯を通じてロシア帝国内で活躍した期間が長かったこともあり、ロシア言語学史上の代表的人物として位置づけられることが多い。

姓はボードアン・ド・クルトネ(ロシアではボドゥエン・デ・クルテネ)であるが、通常は、その全体ではなく前半部ボードアン(ボドゥエン)だけがもちいられている。
フランス系をほうふつさせるようなこの姓については、本書収録のヴィクトル・シクロフスキーのエッセイ「昔々あるところに……」からの抜粋を参照されたい。
ボードアンの言語学関係の業績としては、印欧祖語再建を主たる課題とした歴史・比較言語学が支配的な19世紀後半の状況下にあって、そもそも「言語とはなにか」という根本問題に取り組み、言語学そのものの自立をめざしたことがあげられる。具体的には、〈共時態と通時態〉の区別や〈ラングとパロール〉の区別の必要性をフェルディナン・ド・ソシュールに先立って唱えるとともに、〈音素〉概念の確立に貢献したことでも知られている(詳しくは本書所収の拙論「ソシュールとボードアン」を参照)。
と同時にボードアンは、ヤギェウォ大学時代の教え子である言語学者ヘンリク・ウワシンの言葉を借りるならば、「ほんものの学者=思想家であり言語学者=哲学者であるというかなり稀有なタイプであった」。
*
ボードアンの思想・哲学の根底にあったのは、「人間の尊厳」と「個々人の選択の自由」である。民族、国家、宗教、戦争、その他ほぼすべてをめぐる見解が、この二原則にもとづいて展開されている。
ボードアンは、みずからもことわっているように、政治や社会に関しては「素人」である。しかも、これまた当人がことわっているように、その見解は「実践的」ではなく「理論的」、「原則的」である。
一市民としてのアマチュア精神に立脚して、欺瞞や不平等、不公正に怒りをおぼえるとともに、個々人の信念の自由や良心をひときわ重視していた。
また、筋金入りの平和主義者でもあり、いかなる戦争にも反対し、殺人、死刑、植民地主義、ショーヴィニズム(排外的愛国主義)、暴力などを激しく非難した。
あらゆる暴力に反対であるがゆえに、十月革命後にきわだってきたボリシェヴィズムの軍国主義的傾向をも正面切って指弾した。
1913年にはアンケートへの回答「民族を超越した視点からみた〈ウクライナ問題〉」(本書所収)において、つぎのように述べている。
私にとっては、「愛国主義」というのは、血や強盗、焼けた肉、狼の穴、母親・寡婦・孤児の涙、文化的価値の荒廃、道徳的水準の低下などの匂いを漂わせている。[……]
私の頭や心には、「偉大なるロシア」とか「偉大なるドイツ」、「偉大なるポーランド」などといった類いのフレーズからはなにひとつ響いてこない。こうした言葉の使用は、人類撲滅や暴力などの有象無象の専門家にそっくりまかせておけばよい。(本書27─28頁)
あるいはまた、非戦の思想をつぎのように開陳してもいる。
たたかう側のいずれかの隊列に加わるために、みずから進んで戦争への準備をするなど、愚の極みである。われわれなしでも彼らはやってのけるであろう。われわれ局外の人間は、戦争に対して他のあらゆる災難──地震、洪水、ペスト、コレラ等々──とおなじような態度をとるべきである。[……]
あらゆる戦争は不幸であり犯罪である。われわれは強制されてもいないのにみずから進んで犯罪に加わるべきではない。(本書47─48頁)
またボードアンは、宗教や民族に関しては、個々人の意志を無条件に尊重していた。そのため、信仰の自由や民族所属の自己決定を侵害しようとするすべての企ては、人格の尊厳に対する犯罪であり、法治国家においては許されるべきでない、とまで断言している。
当然のことながら、いかなる民族も対等であると考えており、とりわけロシア帝国内の「マイノリティ」すなわち「(大)ロシア人以外のすべての民族」を擁護する発言をくりかえしていた。
こうした信念につらぬかれていたボードアンは、1913年に『自治の面からみた民族的特徴と地域的特徴』(執筆は1907年)を刊行した廉で逮捕されている。翌1914年にはペテルブルグ大学から解雇されるとともに、ペテルブルグの監獄に3ヶ月幽閉された。原文で90頁近くあるこの小冊子はつぎのように締めくくられている。
私や私と信念をおなじくする者たちの見解では、ロシアは、一方では、すべての公民だけでなくすべての信教、民族、その他の文化的集団・連盟の権利を完全に平等にする方向へ進むべきであり、他方では、脱中心化、個々の地方の地域的自治、最終的には連邦化へと向かうべきである。さもなくば、ロシアは分解と最終的破滅のおそれがある。
もちろん、私がまちがっている可能性もあり、破滅は起こらないかもしれない。それに越したことはない。
ロシアが破滅する可能性に関しては、もう一点述べておきたい。
不法や情け容赦なき非道が国中を闊歩しているような国家、倫理的戒律侵犯や犯罪一般が慢性的で規則にまで高められていて、それがなんら非難も軽蔑もされないどころか、功績として称賛され気前よく褒美まであたえられているような国家、そのような国家の滅亡は、だれの同情も呼び起こさないであろう。(本書137─138頁)
どうやら、監獄暮らしも大学解雇もボードアンに挫折をもたらすことはなかったようで、1916年には「ロシアにおいて民族(ナロードノスチ)の平和的共存は可能か」(本書所収)を公刊している。
ボードアンが実現の可能性に期待していた社会は、一時期のカデット(立憲民主党あるいは人民自由党)のそれに近く、議会を通じての平和的改革にもとづくものであった。ただ、そのあまりに激しい批判精神ゆえに、ボードアンを「左翼リベラル」、さらには国家無用論ともとれる発言ゆえに「アナーキスト」と位置づける者もいる。
1917年の二月革命のあとにはペテルブルグ大学に非常勤教授として復帰するものの、1918年に独立ポーランドに帰国している。
ポーランドでは、国内の民族マイノリティ(ウクライナ人、ベラルーシ人、リトアニア人)に推され、大統領選挙にも出馬した。
いずれも、ボードアンの思想の一端を示していることだけはまちがいない。
*
本書の第1部「ウクライナについて」には、1913年にボードアンが回答したアンケート「民族を超越した視点からみた〈ウクライナ問題〉」を収録した。この日本語訳は『思想』(岩波書店、2024年6月号)に掲載済みであるが、その折りに省略した「ポーランドとウクライナの関係」部分を今回の訳では付け加えた。
第2部「自治の面からみた民族的特徴と地域的特徴」では、ボードアンが民族問題に言及した代表的著作ともいえる小冊子『自治の面からみた民族的特徴と地域的特徴』(1913)と、これに起因する裁判の際の嘆願書数点をとりあげることにした。
第3部「民族の平和的共存について」では、民族問題をめぐるボードアンの見解をさらに広く知るために不可欠と思われる二つの論考「ロシアにおいて民族(ナロードノスチ)の平和的共存は可能か」(1916)、「無民族であることと多民族であること」(1926)を収録した。ボードアンが民族問題をめぐって書いた論考は数多く残されているが、以上の3部でもって趣旨は十分に伝わるものと思われる。
また、第4部「文学と言語」では、民族問題に関連する発言として、トルストイ論二点とエスペラント論をとりあげた。ボードアンはトルストイに大いに共感する一方で、その思想に「社会」や「歴史」が欠如していることには批判的であった。エスペラントに関しても、高く評価する一方で、その絶対視からは距離をとっていた。
以上の論考のすべては、直接的ないし間接的に民族問題に関係するものであるが、そのほかに「補遺」として、ロシア・フォルマリズムの重鎮シクロフスキー(1893─1984)のエッセイ「昔々あるところに……」と、拙論「ソシュールとボードアン」を添えた。前者では、フォルマリズム運動を開始したばかりの青年シクロフスキーからみたボードアン像が生き生きと描かれている。なお、このエッセイの日本語訳は水野忠夫訳『革命のペテルブルグ』(晶文社、1972年)に収録されている。後者は、既発表の「カザン学派」を改稿したものであるが、これによって、ボードアンの専門である言語学における特徴がうかがえるものと思われる。
*
ロシア語文献にでてくる日付は、1917年以前に関しては旧暦(ロシア暦)のままである。
なお、ロシア語では、「民族」を意味するもっとも一般的・抽象的な語はнарод(ナロード)であるが(「民衆」、「国民」、「人民」、「人びと」という意味でももちいられる)、それ以外にнациональность(ナツィオナリノスチ)、нация(ナーツィヤ)、народность(ナロードノスチ)ももちいられる。национальность(ナツィオナリノスチ)は「国籍」と「民族」の双方にまたがっており、нация(ナーツィヤ)はロシア帝国では「国民国家の主体となる民族」の意味で使われている。народность(ナロードノスチ)は「正教、専制、ナロードノスチ」という三位一体でももちいられていたように、民族主義との結びつきが目立った時期もあったが、やがてнация(ナーツィヤ)との対比で「少数民族」を指すことが多くなった。
とはいえ、これらの使い分けは時代や個人しだいで揺れており決して厳密ではなく、ボードアンにも同一事象を指しながら複数の「用語」を使っている箇所がみられる。そのような事情を踏まえ、本書ではнарод(ポーランド語naródないしlud)、национальность(ポーランド語narodowość)、нация(ポーランド語nacja)、народностьの4語とも「民族」と訳し、народとнациональностьにはルビを振らず、нацияには「ナーツィヤ」、народностьには「ナロードノスチ」とルビを付すことにした。ただし、народは「民衆」と訳した箇所もある。
訳注は、短いばあいは割注にした。訳注作成にあたっては以下の文献を参考にした。
田中陽兒、倉持俊一、和田春樹編『世界歴史大系 ロシア史2──18世紀~19世紀』、山川出版社、1994年。伊東孝之、井内敏夫、中井和夫編『新版世界各国史20 ポーランド・ウクライナ・バルト史』、山川出版社、1998年。黒川祐次『物語 ウクライナの歴史──ヨーロッパ最後の大国』、中公新書、2002年。志摩園子『物語 バルト三国の歴史──エストニア・ラトヴィア・リトアニア』、中公新書、2004年。高田和夫『ロシア帝国論──19世紀ロシアの国家・民族・歴史』、平凡社、2012年。服部倫卓、原田義也編著『ウクライナを知るための65章』、明石書店、2018年。黛秋津編『講義 ウクライナの歴史』、山川出版社、2023年。セルヒー・プロヒー『ウクライナ全史──ゲート・オブ・ヨーロッパ』、上・下、鶴見太郎監訳、明石書店、2024年。

ヤン・ボードアン・ド・クルトネ(Jan Baudouin de Courtenay)
1845年生まれ。言語学者。帝政ロシアの分割領であったポーランド王国で生まれる。ワルシャワ中央学校で言語学を修めたのち国内外で研究を重ね、1875年にカザン大学に就任。その後もロシアとポーランドの各地の大学で多くのすぐれた言語学者を育てた。その斬新な言語理論ゆえに、ソシュールと並ぶ構造主義言語学の先駆として高く評価されている。民族問題を中心とする社会問題についても活発に発言していた。1929年没。


桑野隆




