三島由紀夫の「空(くう/そら)」──『豊饒の海』を読み直す | 菊間晴子
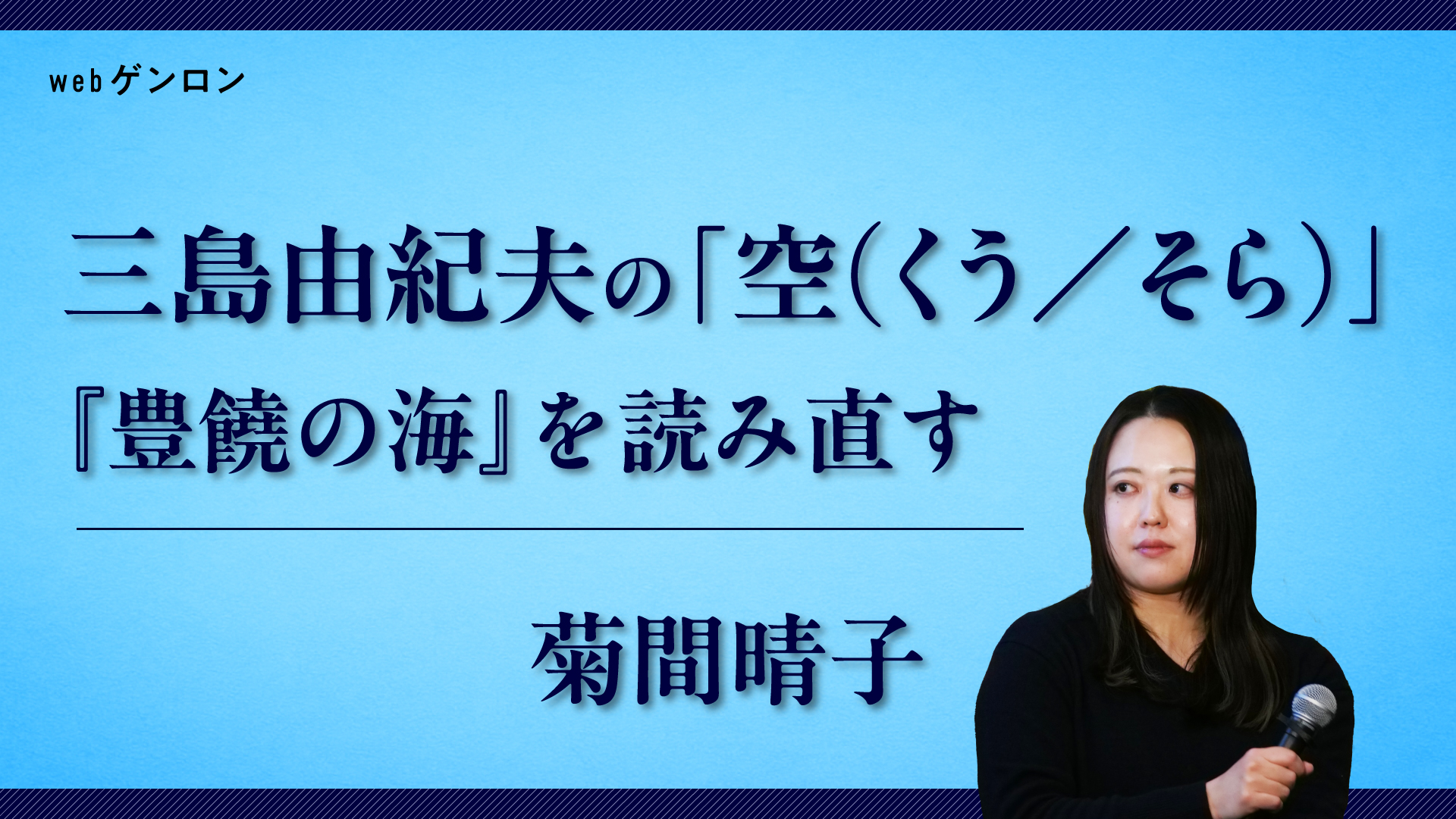
三島はその最期に何を見ていたか?
1970年11月25日、小説家・三島由紀夫は、自らが結成した組織「楯の会」のメンバー4人とともに陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地に闖入し、自衛隊に蹶起を呼びかけたが聞き入れられず、「天皇陛下万歳」と叫んだのち、割腹自殺を遂げた。45歳。戦後日本を代表する文化人として知られた彼の死に様は、あまりにも苛烈なものだった。そして全四巻から成る大作『豊饒の海』の最終原稿は、彼の死の当日に編集者に渡された。したがって『豊饒の海』という小説は、その完結と作家の生涯の最期とを重ね合わせるという稀有な実践のために、計画的に執筆された作品だと言える。
決まって20歳で夭折する美しい主人公たちと、彼らを「転生者」と信じその生涯を見守る本多繁邦が織りなす物語を、四巻まで読み進めてきた読者の多くは、この作品の結末に驚かされることだろう。それは一般に、本多が80歳を過ぎるまで生涯をかけて追い求めてきた「転生」の夢が打ち砕かれ、『豊饒の海』という物語の根幹すら揺らいでしまう究極のバッドエンドとして読まれてきた。三島がこの作品の末尾に示したのは、この世界を構成するすべてのものには実体などなく、うつろいゆく幻のような存在にすぎないという、「空」の思想の表れなのだと。
しかし『豊饒の海』には、あらゆる個々の存在が雲散霧消する「空」の境地に抗うかのように、一人ひとりの人間の生の意義を希求する運動性が随所に見られる。そして、その個別の生を支える役割を担うものこそが、「空」なのだ。『豊饒の海』の登場人物たち、とりわけ本多が折々に見上げる「空」には、単なる風景を超えた、特別な意味が付与されている。この作品を特徴づけるものはまさに「空」と「空」のせめぎあいであり、結末部分においてさえその緊張関係を見出すことができるのである。
本稿の目的は、『豊饒の海』、とりわけその第三・四巻における「空(くう/そら)」のイメージを、三島が遺した「創作ノート」にも目配りしつつ詳細に分析することを通して、この作品の結末の意味を再考し、三島由紀夫がその生涯の最期に見据えていた──「空」に回収されない未来性を帯びた──ヴィジョンに迫ることである。
自己完結的な虚無への収束
まずは、『豊饒の海』の結末について紹介した上で、それがこれまでどのように解釈されてきたかを検討していこう。第一巻『春の雪』の主人公は松枝清顕、第二巻『奔馬』の主人公は飯沼勲、第三巻『暁の寺』の主人公はジン・ジャン、第四巻『天人五衰』の主人公は安永透と設定されている。しかし清顕の友人として第一巻に登場したのち、全巻にわたって大きな存在感を保ち続ける本多繁邦は、間違いなくこの作品の最重要人物だ。四人の主人公たちは、左脇腹に三つの黒子があるという共通の特徴を持っており、本多はそれを証拠として彼らが同一人物の──自身の親友であった清顕の──「転生」した姿なのだと信じる。若い肉体の輝きを保ったまま命を燃やして死んでいく主人公たちと、現実世界との乖離感を抱えたまま老いていく自身との間に埋められない溝を感じつつも、彼らと関係を取り結びたいという欲望が、本多の人生を突き動かしていく。
三島は、このような転生者と傍観者の対比を作品全体の基礎構造とすることで、明治末期から昭和にかけての日本社会の激動を生き生きと浮かび上がらせることに成功したのだ。
第四巻にいたって、本多はすでに老境を迎えている。養子にまでした透からの冷酷な仕打ちに悩み、彼は贋の転生者なのではないかという疑いすら抱くようになるが、それでも本多は転生の実在に望みをかける。しかし透が自殺未遂の末に失明しながらも、20歳を超えて生き延びたことで、その夢は脆くも打ち砕かれてしまう。そして自らの死期が近いことを悟った本多は、奈良・月修寺の門跡である聡子の元を訪ねる。彼女は清顕の幼馴染であり、若かりし日、宮家との縁談が固まったにもかかわらず清顕と恋愛関係に陥ったことに苦しみ、出家したのだった(この悲恋の顛末が『春の雪』の主題である)。しかし、数十年ぶりに再会した本多の前で彼女が口にした言葉は、思いがけないものだった。
「しかし松枝清顕さんという方は、お名をきいたこともありません。そんなお方は、もともとあらしゃらなかったのと違いますか?」[★1]──冗談とも思えない聡子の言葉に混乱し、茫然自失となった本多の目に映るのは、月修寺の南庭の景色である。
芝のはずれに楓を主とした庭木があり、裏山へみちびく枝折戸も見える。夏というのに紅葉している楓もあって、青葉のなかに炎を点じている。庭石もあちこちにのびやかに配され、石の際に花咲いた撫子がつつましい。左方の一角に古い車井戸が見え、又、見るからに日に熱して、腰かければ肌を灼きそうな青緑の陶の榻が、芝生の中程に据えられている。そして裏山の頂きの青空には、夏雲がまばゆい肩を聳やかしている。
これと云って奇巧のない、閑雅な、明るくひらいた御庭である。数珠を繰るような蝉の声がここを領している。
そのほかには何一つ音とてなく、寂寞を極めている。この庭には何もない。記憶もなければ何もないところへ、自分は来てしまったと本多は思った。
庭は夏の日ざかりの日を浴びてしんとしている。……[★2]
この庭において、『豊饒の海』という物語は幕を下ろす。他者の存在の確かさも、そして自分自身の存在の確かさも、すべてが瓦解してしまった本多の境地を映し出すような、「何もない」庭である。またこの庭は、『豊饒の海』という物語そのものが無に帰す場でもあることは重要だろう。
井上隆史はこの結末について、「それまでの登場人物の存在や人間間の出来事そのものが否定されている」のであって、「『豊饒の海』全篇の作品世界は一瞬のうちに消え去り、それ自体が虚無そのものとなってしまうのである」と論じている[★3]。三島が全四巻にわたって紡いできた作品世界を、その終幕にいたって一気に虚無に収束させたとすれば、それはすでに自らの手で生涯を閉じることを決意していた彼による、周到なたくらみに他ならない。そして、『豊饒の海』に対する大江健三郎の強い批判は、このたくらみにこそ向けられていたはずだ。
この作家に関するかぎり、完成することなしに放置されてしまった最後の数ページということはないはずであろう。しかしそこからかえって三島由紀夫の文学的な生涯が、あまりにも「閉じた」ものとして終った、という印象はいなめない。しかも単に印象にとどまらず、『豊饒の海』四部作を分析するならば、文学的な実質として——あるいは文学的な実質のかたよりとして——、それは容易に提示できよう。[……]あえていえば三島由紀夫は、自分の「最後の小説」が、後から来る者らによって継承・発展させられることはないようにとたくらんで、その生涯をしめくくったのではなかっただろうか?[★4]
大江は続けて、三島の死について、「三島由紀夫の政治思想を、かれの死体とともに埋葬するための、幕引きのパフォーマンスのようだった」とも語っている[★5]。『豊饒の海』もまた彼の「幕引きのパフォーマンス」の一環であって、自らの手で自らの文学を葬り去ることこそがその執筆の目的だったとするならば、それが他者による独創的な解釈や新たな形での継承・発展を拒む「閉じた」作品だ、という大江の批判は妥当なものであるように思われる。
「空」は希望か、絶望か?
もう一つ指摘しておきたいのは、先行する論においてはしばしば、『豊饒の海』の最後に立ち上がるこの庭が、仏教における「空」の思想——この世界におけるあらゆる事象は生成流転し続けるのであって、独立して存在する実体などはなく、「我」すらも仮象である、という境地——と結びつけられてきたことである。仏教の教えでは、この世界に対する様々な執着と、そこから生まれる苦しみからの解放にいたる契機として、「空」の境地が定義される。『豊饒の海』の執筆時、三島が仏教思想に対して強い関心を抱いていたことは事実であり、『暁の寺』第一部では本多による「唯識」研究にかなりの分量が割かれている。次の引用は、そのごく一部である。
唯識の本当の意味は、われわれ現在の一刹那において、この世界なるものがすべてそこに現われている、ということに他ならない。しかも、一刹那の世界は、次の刹那には一旦滅して、又新たな世界が立ち現われる。現在ここに現われた世界が、次の瞬間には変化しつつ、そのままつづいてゆく。かくてこの世界すべては阿頼耶識なのであった。…… [★6]
この引用から明らかなように、本多は、中年を迎える頃にはすでに「この世界すべては阿頼耶識」であるという認識を得た人物、つまりこの世界は瞬間ごとに生滅を繰り返しながら流動していくのであり、その実相は「空」に他ならないことを理解した人物として設定されている。ならば、死の間際の本多の目に映った「何もない」庭は、生の苦しみから人間を救済する希望としての、「空」の境地の具現化だと言えるだろうか。
あるいは安藤礼二は、『豊饒の海』の原型が『浜松中納言物語』の現存しない「首巻」であることを指摘し「『浜松中納言物語』の失われた「空」の書物からはじまった「豊饒の海」という巨大な物語が、作者とともに「空」に還ることは、いわば必然であった」と述べている[★7]。安藤はさらに、「空」に始まり「空」に還るというこの運動性を、三島が「文化防衛論」(1968)のなかで日本文化の特色として挙げた、オリジナルとコピーの不分別性[★8]と重ね合わせてもいるのだが、この考えに依拠するならば、「何もない」庭とはまさに、三島自身が追求し自ら体現しようとした日本的な「空」の美学の象徴ということになるだろう。
しかしながら、その「何もない」庭に対面した本多の胸中には、救済の喜びも、そして美学的な満足も、決して到来していないように見える。平野啓一郎は、「その中庭が、いかに「浄土」的であろうと、本多は徹底的に孤独な虚無感の底に佇んでいることになり、浄福観からは程遠いということになる」と述べた上で、その理由として「三島の空観」が「最後まで、戦後社会の空虚さと同等の否定的な観念に留まっていた」ことを挙げている[★9]。
実際三島は、1970年に行われた武田泰淳との対談で、自身が仏教思想に強く関心を抱いていることを明かしたのち、「戦後世界というのは、ほんとうに信じられない、つまり、こんな空に近いものはないと思っているんです」と述べ、「現実世界の崩壊」と「戦後世界の空白」とを「空」というイメージによって繋げる試みとして『豊饒の海』を書いたと明言しているのだ[★10]。
すなわち三島にとって「空」は、人々を繋ぐ共通の価値観が失われ、文化が形骸化し、曖昧な言説が蔓延る戦後社会の空虚さそのものを指す概念でもあったのである。この点を踏まえれば、『豊饒の海』の結末に立ち上がる「空」には、三島が自らの命を投げ打って極端な行動を起こす一つのきっかけとなった、戦後社会に対する幻滅や諦念、虚無感こそが色濃く反映されていたと考えられる。
1945年、引き裂かれた「空」
『豊饒の海』の結末は、三島由紀夫による意識的な「幕引きのパフォーマンス」であって、その最後に立ち上がる庭の景色は、まさに「空」の境地を象徴している。そしてそこには、この世界のすべてが「空」であるという認識に伴うわずかな希望と、圧倒的な絶望とが刻み込まれている——。ここまで検討してきた諸解釈を総合すれば、このように結論づけることができるだろう。
ただし、先に引用した『豊饒の海』の結末部分を注意深く読むと、実はその庭には、「空」に拮抗する要素が描き込まれていることがわかる。本多はここで、限られた区画に構築された「何もない」庭だけを見つめているのではない。彼はその庭の後方にそびえる裏山の頂に広がる、輝く夏雲を浮かべた「青空」をまなざしてもいるのだ。
ひるがえって見ると、『豊饒の海』という作品には、登場人物が「空」を見上げる描写が頻出することに気づく。とくに本多と「空」の結びつきは深い。たとえば『春の雪』においては、少年時代の本多が、松枝邸内の池に浮かぶ中ノ島の草地に清顕と並んで寝ころび、「よく晴れた晩秋の空」を仰ぐ場面がある。この時彼は、「何かの予感に充され」つつ、「こんなに何もなくて、こんなにすばらしい日は、一生のうちに何度もないかもしれない」と口にする[★11]。まるで、清顕との友情がこのあと辿る数奇な運命を、「空」から直観的に読み取っているかのようである。
また『奔馬』にも、奈良で出会った少年・勲に清顕の面影を見出して心をかき乱された本多が、なかなか眠りにつくことができず、ホテルの窓から「明けやらぬ空」を見つめる場面が描き込まれている[★12]。白みかけた暁の「空」、そしてそこに融け入るようにそびえる興福寺の五重塔の眺めに、夢と現実のあわいに立ち上がる転生の神秘を重ねた彼は、清顕の死後に陥っていた「精神の氷結」から自身が恢復しつつあることを感じ、「ふしぎな安堵」に包まれながら寝入るのだ[★13]。
本多という人物はこのように、その生涯にわたって、「空」を鏡として自らの心と向き合うとともに、「空」からこの世界を生きるための励ましを得ようとし続ける。本多と「空」の関係を、物語の流れに即して分析することは、月修寺の「庭」で最後に彼が相対する「青空」の意義を明らかにし、『豊饒の海』の結末について新たな解釈を示すための重要な足がかりとなるだろう。
なかでも『暁の寺』、『天人五衰』では、物語のなかで本多が果たす役割が大きくなるのに比例するように、「空」の印象的な描写が頻出する。まず注目したいのは、『暁の寺』第一部に描かれる「空」である。太平洋戦争の戦局が悪化の一途を辿っていた1945年6月、仕事で渋谷を訪れた本多は、道玄坂を上った先にある松枝侯爵邸に足を運ぶ。かつて清顕に会うために通い、ともに「よく晴れた晩秋の空」を見上げた、あの立派な邸宅が、先月の空襲によって見渡すかぎりの焼趾になっているのを目の当たりにした時、彼はやはり「空」にまなざしを向ける。
しかし、坂巻く夕焼雲の下に、ちぢれたブリキ、割れた瓦、裂けた立木、融けたガラス、焦げた羽目板、あるいは煖炉の煙出しの白骨のようにしらじらと孤立したありさま、菱形に崩れたドア、などの無数の破片は、一様に銹朱のいろに染っていた。それらは崩れて地に伏したのだが、あまりにも奔放で、規矩を踏みにじったそれらの形は、あたかも今地から芽生えた奇怪な莿草のように眺められた。夕日が影をひとつひとつに的確に添えているので、尚更そうである。空は引きちぎった雲をいちめんに散らかしたような布置の赤一ㇳ色である。雲の染まり具合が、雲の骨髄に浸みている。そして、引きずったあとに残る雲の糸のほつれが、ことごとく金光を放っている。空がこれほど凶々しく見えたことは本多にははじめてだった。[★14]
破壊し尽くされ「無数の破片」となってしまった邸宅の上に広がる「空」の、圧倒的な凶々しさ。「雲の染まり具合が、雲の骨髄に浸みている」という表現からも、夕焼け空に浮かぶ朱に染まった切れ切れの雲に、本多が血だらけの骸のイメージを重ねていることは明らかだ。この、バラバラに引き裂かれたかのような「空」の様相は、自身の拠り所が戦争によって脆くも失われたことを知った本多の痛みを、如実に反映するものである。
注意したいのは、そもそも本多は戦時下において、混乱する社会から距離をとり、悠々自適に過ごしていた人物であったことだ。弁護士として働きつつ、経済的・時間的な余裕を生かして輪廻転生の研究に精を出していた彼は、戦争の被害や人々の苦しみに心を向けることなく、社会情勢を達観していた。松枝邸に向かう直前、松濤にある依頼人の邸宅の二階から、焼趾となった街を見下ろす場面には、このような彼の姿勢が如実に表れている。
見わたすかぎり、焼け爛れたこの末期的な世界は、しかし、それ自体が終りなのではなく、又、はじまりなのでもなかった。それは一瞬一瞬、平然と更新されている世界だった。阿頼耶識は何ものにも動ぜず、この赤茶けた廃墟を世界として引受け、次の一瞬には又忽ち捨て去って、同じような、しかし日ごと月ごとにますます破滅の色の深まる世界を受け入れるにちがいない[★15]。
この世界が生成流転する阿頼耶識そのものなのだとしたら、いま自分が二階から見下ろしている廃墟もまたその一瞬の表れに過ぎず、破滅こそ世界の理なのだ——。このように悟った彼は、「唯識から学んだこの考えの、身もおののくような涼しさに酔った」[★16]という。この場面において、本多はまさに先に述べた「空」の境地にある。安全圏から地上を見下ろす天人のような、超然とした自らのまなざしに陶酔しきった彼の心境がそこに反映されている。
けれども、そのあと自分の足で渋谷の街を歩き、松枝邸の崩壊を目の当たりにした本多は、その「空」の境地から引きずり下ろされることとなる。過酷な地上の現実に対峙した彼は、何か大きな力に縋ろうとするかのように、引き裂かれた「空」を茫然と眺めやることしかできないのである。
ここで描かれる本多の心情から想起されるのは、堀田善衛が『方丈記私記』(1971)で回想している空襲下の感覚──自身がいま「断裂、亀裂、裂け目」のただなかに在るという「浮雲の思ひ」──である[★17]。これまでの日常や常識がガラガラと崩れ、すべてが瓦礫と化した1945年という時代の裂け目に生きる人々の不安が、まさに地上を覆う「空」の裂け目に象徴されているのだ[★18]。
絶対の「空」の希求
この「空」の裂け目の経験、そして8月の終戦──作中では直接的に描かれることなく、空白期間として設定されている──を経て、本多は裕福な資産家として戦後社会を生きることになる。しかし彼はもはや、かつてのように「空」の境地に酔い、世界を達観することはできない。むしろ滑稽なほどに、ある特定の対象への強い執着を見せはじめるようになるのだ。
その対象とは、転生者のなかで唯一の女性であり、かつ異邦人(タイ国の王女)でもあるジン・ジャンである。本多のジン・ジャンへの執着の激しさは、彼女の美しい肉体に性的に惹かれていたことだけが理由ではないだろう。本多は彼女に、1945年に引き裂かれた「空」に代わる、絶対の「空」の役割を期待していたのである。
一つの宇宙の中に自足しているジン・ジャン、それ自体が一つの宇宙であるジン・ジャンは、あくまでも本多と隔絶していなければならない。彼女はともすると一種の光学的存在であり、肉体の虹なのであった。[……]……そしてその虹の端は、死の天空へと融け入っている。死の空へ架ける虹。知らないということが、そもそもエロティシズムの第一条件であるならば、エロティシズムの極致は、永遠の不可知にしかない筈だ。すなわち「死」に。[★19]
ここで本多は、「一種の光学的存在」として、しかも「永遠の不可知」の対象として、ジン・ジャンを捉えようとする。つまり、絶対的な強度で頭上に君臨し続け、あくまで自らと隔絶しているからこそエロティシズムの極致を与えてくれる、不変に光り輝く「空」としてのジン・ジャンをこそ、彼は求めたのだ。
この引用から想起されるのは、三島がエッセイ「太陽と鉄」(1968)に記した「絶対の青空」をめぐる挿話である。自らの肉体を鍛え上げた三島が、実際に祭りで神輿を担いだ際に、神輿の担ぎ手たちがあれほどの陶酔を得ているのはなぜなのか、という「幼時からの謎」が解けたという。その答えは「空」にあった。ともに激しい肉体の苦痛を経験しつつ「初秋の絶対の青空」を見上げた時、人々は陶酔のなかで連帯することができる。また何より彼を歓喜させたのは、「自分の詩的直観によつて眺めた青空と、平凡な巷の若者の目に映った青空との、同一性」であった[★20]。
ここで語られる「絶対の青空」とは、それを見上げる人を熱狂させ、この世界を生きる力を与えるとともに、同一の対象を見上げる他者との確固とした連帯感を生じさせる存在のことだ。そして三島がこの「絶対の青空」に見出した意義は、晩年の三島が謳った「文化概念」としての「天皇」のそれに通じるものでもある。
戦中に徴兵検査に合格しながらも、肺浸潤と誤診されて戦地に赴くことを免れ、1945年を超えて生き延びた三島は、戦後失われた日本の文化や連帯感を取り戻すため、「天皇」という装置の意義を追求した。そこで彼が掲げたのは、言論の自由を保障し、高貴も卑俗もすべて抱きとめ、あらゆる人々の生のエネルギーの受け皿となる装置としての「天皇」像だった。だからこそ、「天皇」は決して人間であってはならず、人間が絶対に到達できない高みにこそ存在しなければならなかった。
三島によるこのような天皇像の希求は、ジン・ジャンという特別な転生者に、1945年の引き裂かれた「空」に代わる絶対の「空」の役割を託そうとした本多のそれと、明らかに重なり合うものである。
消えゆく「空」の幻
しかし皮肉なのは、本多が絶対の「空」を強く希求することになった戦後において、その「空」の役割を担うはずの転生者、すなわちジン・ジャンの俗物性があらわになっていくことだ。ジン・ジャンが絶対の「空」であり続けられるのはあくまで本多の妄想のなかだけであって、彼女の実像は、肉体的快楽の追求には貪欲である一方精神的には未成熟なままの少女である。
さらに、『天人五衰』の主人公である安永透にいたっては、美しい少年であるとはいえ、「純粋な悪」[★21]という本多による形容にふさわしい神秘性・特権性を、実際には持ち合わせていない。作中に挿入される「手記」を読めばわかる通り、周囲の人間を見下し自らを特権視する彼の態度は、いかにも世間を知らない少年が陥りそうな——率直に言って、微笑ましいほどありがちな——ものなのだし、その実、本多の友人である慶子の発言にあるように「卑しい、小さな、どこにでもころがっている小利口な田舎者の青年」[★22]にすぎない。本多が転生者たちに絶対の「空」としての役割を託そうとどれほど努力しても、もはや彼らがそのような器を持ち合わせていないことは明らかなのだ[★23]。
『天人五衰』には、本多の「空」への希求の絶望的な末路を象徴する場所が登場する。それが、天人伝説で知られる静岡の「三保の松原」である。慶子とともにそこを訪れた本多の目に映るのは、戦後社会における俗化の波に犯され、もはや天人の夢を託すことも難しくなった、景勝地の惨状だ。
三保の松原でも、この詩の骸の中空に、天人は人々の想像上の要望に応じて、サーカスの芸人のように、何万回何十万回となく踊ることを強いられていた。曇った空はその踊りの見えない軌跡でいっぱいだった、まるで銀いろの高圧線の交錯に充たされた空のように。人々は夢のなかでも、五衰の姿の天人にしか会わぬだろう。
時刻は三時をすぎていた。日本平県立自然公園、三保の松原、と書いた立札も、かたわらの松の荒々しい鱗を怒らせた樹皮も、のこる隈なく緑苔にまぶされていた。ゆるい石段を昇ってゆくと、空を縦横に稲妻形に切り裂いた不遜な松林のすがたが現われ、死にかけた松も枝毎に掲げた緑の燭のような花々のむこうに、生彩のない海が伸び上ってきた。[★24]
本多はここで、松林と海岸、そして富士山が織りなす美しい光景を味わうことは叶わず、その荒廃にばかり目を奪われている。「空気はしたたかに車の排気ガスに犯され、松は瀕死の姿」であり、「コカ・コーラの赤い梵字」が満載の茶店には、清水の次郎長とお蝶を象った「顔のところだけ穴を開けた記念撮影用の絵看板」——いわゆる顔はめパネルである——が設置されている[★25]。海岸線には打ち上げられた空壜が見える。天人の羽衣の裂を宝物とする御穂神社の桜並木は、害虫駆除のための毒にまみれ、その実を食べないように注意札が張り巡らされている。高度経済成長に伴う消費社会の到来、それに起因する環境破壊の拡大が、神秘的な景勝地にも甚大な影響を及ぼしている様子が、克明に描き出されているのだ。
本多は、この松原に立って梅雨時の曇り空を見上げてみたところで、そこに光り輝く天人の幻すら見出すことができないことを了解している。この時点で本多はまだ安永透に出会ってすらいないが、1945年に引き裂かれた「空」を絶対の「空」の幻で代替することは、この戦後社会にあってもはや不可能であるという事実を、すでに悟っているのである。
『豊饒の海』の創作ノートには、1970年6月10日、三島が実際に三保の松原を訪れた際の記録が残されている。創作ノートの記録と『豊饒の海』本編を見比べてみると、三島がかなり忠実に、三保の松原の現状を小説に写し取ろうと試みたことがわかる。その日の天気は曇りで、おそらく富士山を望むことはできなかったのだろう。三島の目に映ったのは「異常に、斜めに、稲妻形になびいた砂上の松林」[★26]であり、茶店と絵看板の俗っぽさであり、害虫駆除の注意札の無粋さであり、景色全体を覆いつくす寂寥感であった。彼が三保の松原で直面したのは、天皇という「空」の追求がもはや意味をなさないと思われるほど荒廃した、戦後社会に対する絶望だったのかもしれない。
「空」も「空」も必要としない女性たち
ただし面白いのは、絶対の「空」を仰ぎ見ることの不可能性に打ちひしがれる本多とはまったく対照的な人物が、この場面に登場することだ。本多とともに三保の松原を訪れた慶子である。本多にとって彼女は良い友人だったが、「本当に日本文化がわかっているのかどうか、甚だ怪しい」[★27]と、時に彼女の振る舞いに鼻白んでいた。彼が三保の松原への案内を買って出た背景には、「この景勝の地の荒れ果てた俗化のありさまを慶子に見せて、彼女のいい気な浮っ調子の夢想を打ち破ってやろう」[★28]という魂胆があったのである。
しかし実際に三保の松原を目にした慶子は「少しも心を傷つけられなかった」し、「まあ、いい景色。すばらしいところね。それに空気のいい匂い。海が近いからね」とすら言ってのける[★29]。絵看板に顔を差し入れて写真を撮ることを本多に提案し、堂々たる振る舞いで周囲の人々の関心を集め、往年の大女優と勘違いされてサインを求められすらする。また御穂神社では、有毒の注意札を無視して桜の実を食べてしまい、後方を歩いていた本多は懸命に彼女を止めようとするけれども、「慶子が決して些少の毒くらいに中ることのないのを知っていた」[★30]——。彼女は、いまここの世界の様相がいかなるものであろうとも、それを心身両面で存分に楽しむことのできる人物なのである。
創作ノートに記録された「三保の松原」は、活気なくうらぶれた、空虚な場所である。しかし三島はその情景を小説化するにあたって、本多を無邪気に振り回し続ける慶子の姿をそこに書き足した。その目的は、社会の俗化を際立たせ、物語に滑稽味を付加することだけではなく、本多が感じている戦後の虚無感を一笑に付す、エネルギッシュな女性像を打ち出すことにあったのではないか。
『豊饒の海』には、慶子のような独特の力強さを持った女性たちが、随所に姿を現す。たとえば、聡子の侍女であった蓼科。先に分析した1945年6月に本多が松枝邸を訪れる場面には、齢95を迎える蓼科との再会も描き込まれている。ここで、老いの醜さのなかにもなまめかしさを感じさせる蓼科に、本多がちょうど持っていた卵を分け与えた際の反応は、特筆に値するものだ。久しく口にしていない卵に喜んだ蓼科は、その場で割って「夕空へひろげた口から、しらじらと光る総入歯の歯列のあいだへ流し込」み、「その口をとおるときの黄身の光沢のある丸みが一瞬見え、蓼科の咽喉の鳴りが、いやに健やかにひびいた」[★31]。このグロテスクな描写からは、頭上に広がる引き裂かれた「空」を気にもとめず、それを卵とともに丸呑みして自らの滋養にしてしまうかのような、彼女の底知れない生命力が感じられる。
そして、『天人五衰』の終盤で透と結婚する絹江。自分の醜さを知らず、絶世の美女だと信じ込んでいる彼女は、狂疾が作り上げた強固な想像の世界のなかに充足して生きている。単に肥って身動きが取りにくくなったことを病気の兆候と捉えた絹江が、自身の運命が儚く美しいことに喜び、「たえず消化薬を嚥んでは、いつ喪うことになるともしれぬ葉ごしの青空を、縁先の寝椅子から眺めていた」という描写には、彼女にとっての「空」が、自身が主役を務める感動的な悲劇を彩る舞台装置にすぎないことをよく表している[★32]。自殺未遂後、一日中家で過ごすようになった盲目の透を愛し、彼との生活を心底楽しんでいた彼女の体には、やがて妊娠の兆候が表れる。彼女の行動は一貫して、どんな現実も自らの物語の一部へと変えてしまう強固な美学と、透への愛情に貫かれており、それを他の誰にも譲ろうとしないまっすぐな意志を感じさせるものなのである。
本多は、かつて「空」の境地に触れながらも、1945年という時代の裂け目にあってそれを保ち続けることができず、戦後には自らの生の意義を保証してくれる絶対の「空」を追い求めたが、その試みはついに挫折にいたる。一方で、慶子や蓼科、そして絹枝は、超然とした「空」の境地も、絶対の「空」の幻も必要としない。彼女たちには本多のような思慮深さは欠けているものの、そのぶん最大限の快楽を追求しつつ自らの人生を充実させていく、ふてぶてしさとしたたかさがある。三島は、本多とは対照的なこのような彼女たちの生き方を実に魅力的に描いている。「空」にも「空」にも依らず、あるがままの生を自らの力で不断に肯定していく運動性が、戦後社会を生き抜く一つの方策として、『豊饒の海』のなかに示されていることは注目に値する。
未来に広がる「青空」
では、ここまでの考察を踏まえて、再び『豊饒の海』の結末における「空」の描写に立ち戻ろう。創作ノートの記録によれば、1970年7月22日、三島は月修寺のモデルとなった奈良の円照寺を訪ねている。下記はそのノートからの引用だが、三保の松原の場合と同じく、三島はここで実際に目にした南庭の風景を、かなり忠実に『豊饒の海』本編に反映させていることがわかる。
◯南むきの庭。南の御庭、芝生、左方に車井戸、右方に撫子の花、
「今日は朝からクヮクコウ鳴いてをりました」
庭の木々、緑にしづむ〔「ま」の誤記か〕り浄土の如し 完全な静寂。夏雲、山の林へ導く庭の門のたゝずまひ、日に熟してゐる青緑の陶の榻。二三の暗い赤の楓の紅葉。
◎じゅゆずを繰るような蝉の声。日はしんしん〔編集部注:踊り字を通常のかなに置き換えた〕と浄土の如し。夏ここにさかり也。何ものもなし。人住まず。何もない庭へみちびかる。記憶もなし。何もなし。ただ深閑たる夏の庭也。
ラストシーン
何もない南の庭は 夏の日ざかりの日を浴びてしんとしてゐる。[★33]
ただし注目したいのは、ノートには「夏雲」という記述があるのみで、「青空」への言及は見られないことである。さらに、本編に見られる「明るくひらいた御庭」という表現も、ノートの段階では存在しない。実際の円照寺南庭は、「浄土の如し」と形容される通り、静謐さのなかに閉じた空間だったが、三島は小説化に際してそれを、遠景に「青空」を望む「ひらいた」庭へと書き換えたのである。
三島による書き換えによって生じたのは、本多と「青空」との邂逅だ。この「青空」は、1945年に彼が目撃した引き裂かれた「空」でも、戦後社会において彼が希求した絶対の「空」でもない、ごくごく平凡な「空」である。それでいて、庭先に佇む彼の頭上にではなく、庭ごしに見える裏山の頂という空間的に隔たった地点に広がるこの「空」は、明らかに未来性を帯びている。死を目前にした本多が、挫折の果てに辿り着いた「何もない」庭の先に、ありふれた、しかし未来に広がる「青空」を垣間見た瞬間。それは、「空」と「空」のはざまで翻弄され続けてきた彼が、そのどちらにも依らずに自らの生を肯定し、その生の先に続いていく未来を意識した瞬間として解釈できよう。透と絹江の子、本多にとっての孫の誕生の予感は、この不確定の未来を彩る一要素である。そしてこの「青空」との出会いは、慶子をはじめとするあのエネルギッシュな女性たち——彼をこの庭へ導いた聡子もまたその一人であろう——が体現する、あるがままの生の肯定の境地からもたらされた恩恵に違いない。
はじめに言及したように、大江健三郎は、三島の「最後の小説」となった『豊饒の海』が、あまりにも「閉じた」ものであったことを強く批判した。その背景には、ともに戦後社会を生きる文学者であった三島が、「天皇」を掲げた蹶起の果てに自ら命を絶つことを計画し、彼の美学に貫かれた「幕引きのパフォーマンス」の一環として「最後の小説」を利用したことに対する、動揺と憤慨があったはずだ。だからこそ大江は老年にいたるまで、社会的な情勢を敏感に捉えつつ、彼自身を規定する「天皇」の幻影を、作品世界のなかで幾度も書き直しながら解体していった。三島という存在を強く意識した上で、自身の「最後の小説」が「閉じた」ものとならないよう、その想像力の枠組みを破壊することを目指して執筆を続けたのである。
ただ、ここまでの分析を踏まえれば、『豊饒の海』という作品には、三島個人の美学に回収することのできない要素が含まれていることは明らかだろう。その結末にすら、自身を規定する想像力とは相反する他者の生き方にこそ希望を託そうとする、彼の「ひらいた」境地が、わずかに透けて見えるのである。
三島由紀夫という小説家は、『豊饒の海』の本多繁邦と同じく、「空」と「空」のせめぎあいに生き、そのただなかに散った。けれども、この作品の末尾に「青空」をさりげなく書き込んだ時、彼のまなざしはその先に、ささやかな未知の希望を孕んだ未来を、確かに捉えていたのではないだろうか。
【後記】
2025年8月、筆者は初めて三保の松原を訪れた。三島が訪れた日のように曇りではなかったものの、真夏の熱気のためか、やはり富士山を望むことはできなかった。写真は、三島の創作ノートでも言及されている名勝「鎌ヶ崎」。

松原は、おそらく三島が現地を訪れた時よりも美しく整備されており、『豊饒の海』に記されているほどの荒廃は感じなかった。しかしその風景のなかで最も印象的だったのは、海風を受けて曲がりくねった松の枝と、地面にへばりつく無数の根の、不気味なほどの迫力であった。三島は創作ノートのなかで、「ことごとく燭を掲げたり」と擬人法を用いてその枝ぶりを表現しているが(三島由紀夫「「豊饒の海」創作ノート」、858頁)、海岸沿いに佇む無数の松の姿は、確かに妙に人間的だ。この場所に似合うのは、天人の優美な伝説ではなく、まさに慶子をはじめとする女性たちが体現していた、どんな状況にあってもこの地上の生を謳歌しようとする泥臭いエネルギーであるように思われた。


★1 三島由紀夫『天人五衰(豊饒の海・第四巻)』、新潮文庫、2003年、340頁。
★2 同書、342頁。
★3 井上隆史『三島由紀夫 幻の遺作を読む もう一つの『豊饒の海』』、光文社新書、2010年、243頁。
★4 大江健三郎「最後の小説」、『最後の小説』、講談社、1988年、49-50頁。
★5 同書、50頁。
★6 三島由紀夫『暁の寺(豊饒の海・第三巻)』、新潮文庫、2002年、163頁。
★7 安藤礼二「物語を生み出す「廃墟」——『豊饒の海』」、『ゲンロン18』、141頁。「空」のルビは引用者による。
★8 三島は「文化防衛論」で、日本の造形美術は「木と紙の文化に拠った」ものであるゆえ、「ものとしての文化への固執が比較的稀薄であり、消失を本質とする行動様式への文化形式の移管が特色的」であると論じている(三島由紀夫『文化防衛論』、ちくま文庫、2006年、44頁)。そのような日本文化の特色の代表として彼が挙げるものこそ、式年遷宮によって新たに建て替えられる「コピー」であるはずの宮が唯一の「オリジナル」とみなされる伊勢神宮であり、天照大神の神性を代々継承する「コピー」であるはずの人物が唯一の「オリジナル」とみなされる天皇制である。
★9 平野啓一郎『三島由紀夫論』、新潮社、2023年、628頁。
★10 武田泰淳、三島由紀夫「文学は空虚か」、『三島由紀夫 文芸読本』、1983年、河出書房新社、147頁。
★11 三島由紀夫『春の雪(豊饒の海・第一巻)』、新潮文庫、2020年、25頁。
★12 三島由紀夫『奔馬(豊饒の海・第二巻)』、新潮文庫、2002年、55頁。
★13 同書、56頁。
★14 三島『暁の寺』、171頁。
★15 同書、168頁。
★16 同上。
★17 堀田善衛『方丈記私記』、ちくま文庫、1988年、91頁。
★18 ここで指摘しておきたいのは、「暁の寺」第一部において、まさに空間・時間の裂け目と「空」の裂け目が重ね合わされて解釈される場面が存在することだ。本多がタイで幼いジン・ジャンに出会い、ともにバンパインに赴く舟路において、太陽を隠そうとする雨雲と、そこに抗って光を届けようとする太陽のせめぎあいが繰り広げられる不穏な空を、彼女が見つめていることに気づく。本多はこの時、ジン・ジャンが見ているものは、「異なる時間の共在でもあり、異なる空間の共在でもあって」、いわば「この世界の裂け目」なのだと考えるのである(三島『暁の寺』、58頁)。
★19 同書、264頁。
★20 三島由紀夫「太陽と鉄」、『三島由紀夫全集 決定版 33』、新潮社、2003年、511-512頁。
★21 三島『天人五衰』、94頁。
★22 同書、298頁。
★23 ここでは、ジン・ジャンと安永透が、本多の妄想のなかでのみ神格化されているだけの俗物であることが、作中の描写から読み取れることを指摘した。付言するならば、実は『春の雪』の松枝清顕や『奔馬』の飯沼勲も、神格化に値する人物としては描かれていない。清顕の聡子に対する行動は、彼女への強固な愛情というより自尊心や虚栄心に依拠するものであり、彼は一貫して彼女を傷つけようとしているようにも読める。清顕の行動は、実は『天人五衰』の安永透が百子に行った仕打ち——義父である本多を苦しめることを目的に彼女と付き合い、様々な謀略を巡らして彼女を傷つけ、裏切った——と大差ないのである。また勲は、国を憂い、天皇に忠義を尽くそうとする強靭な志を持ってはいるものの、要所要所でその視野の狭さや詰めの甘さが目立つ。美しい年長の女性・槇子に不用意に計画を話してしまったことで蹶起計画が破綻する場面から浮かび上がるのは、彼女への慕情を断ち切ることのできない素朴な少年の姿だ。三島は、『豊饒の海』前半の、戦前を舞台にした物語においてさえ、転生者の人間臭さや未成熟さを意図的に描き出すことで、彼らを神格化することの不可能性と、本多の試みの滑稽さを仄めかしていたと言えるのではないだろうか。
★24 三島『天人五衰』、78-79頁。
★25 同上。
★26 三島由紀夫「「豊饒の海」創作ノート」、『決定版 三島由紀夫全集 14』、新潮社、2002年、858頁。
★27 三島『天人五衰』、68頁。
★28 同書、77頁。
★29 同書、78頁。
★30 同書、85頁。
★31 三島『暁の寺』、178頁。強調は筆者による。
★32 三島『天人五衰』、284頁。強調は筆者による。
★33 三島「「豊饒の海」創作ノート」、870頁。


菊間晴子
1 コメント
- TM2025/09/22 16:50
安藤さん、横山さんとのイベントで展開された距離の話題が、空(そら)としてこう着地するのかと驚かされました。 『豊饒の海』の慶子ら女性の欲望に率直に進むエネルギッシュさは確かに、本多の傍観者として世界に着地しない様に比べると、未来を感じさせる活力があります。 ただやはりそこには本多が見続けた阿頼耶識的な暴流の忘却という要素はありそうで、それはそれでふとした瞬間に奈落に落ちるような恐ろしさを抱えているのではないでしゃうか。 私も三島が周到に閉じようとして閉じられなかったこの物語は、現代の作家によって語り直されるべきなのではと感じます。 大江が驚くような開かれが訪れる。 そんな日を期待してしまいます。




