追悼 中川李枝子──『ぐりとぐら』が登場するとき(1) 絵本と保育|阿部卓也
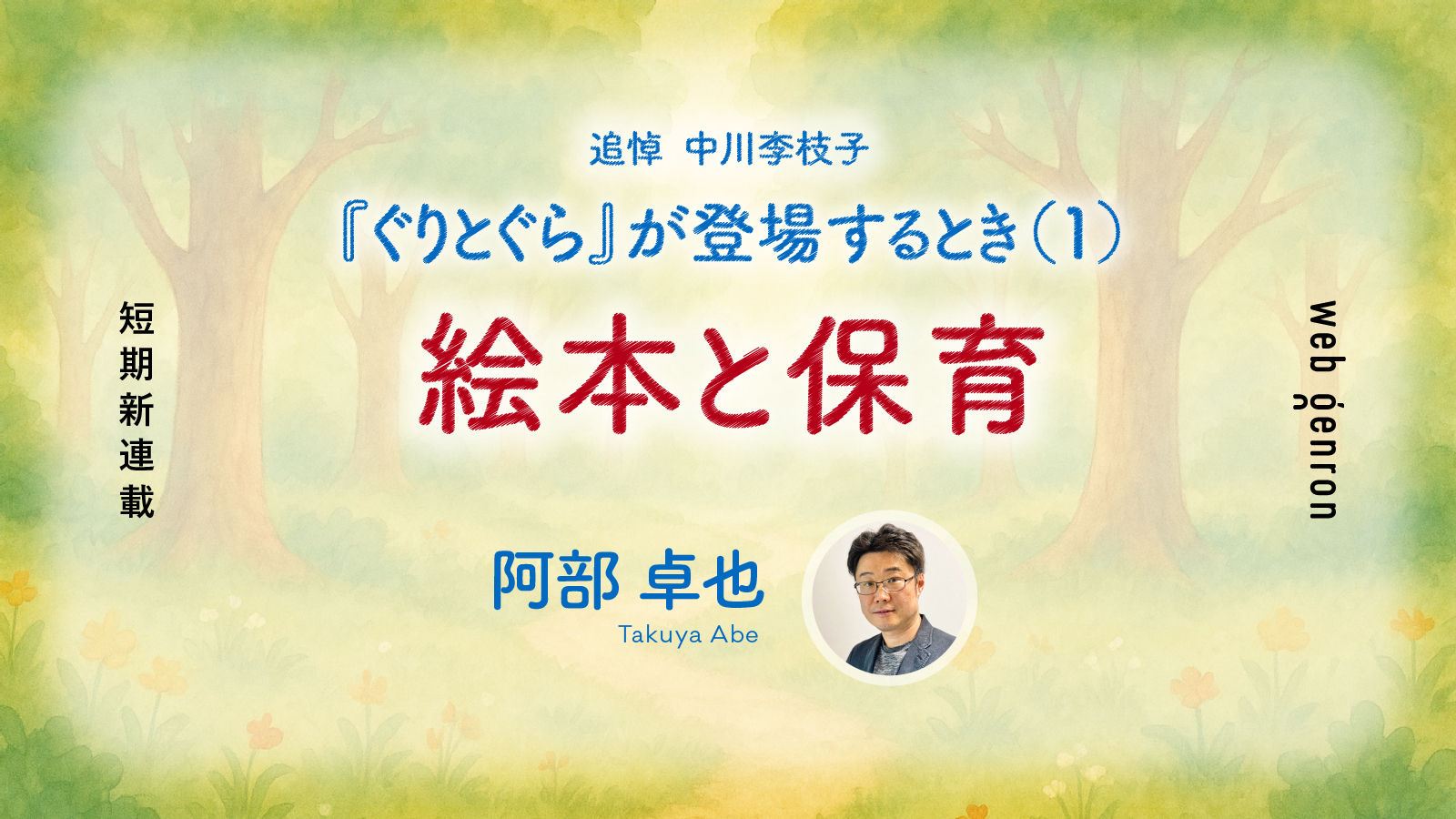
使命とは、必ずしも大きな仕事とは限りません。
どこに自分の仕事があるか、まじめに生活を考えましょう。村岡花子訳『ジェーン・アダムスの生涯』訳者まえがき(岩波少年文庫、1953)より
私の目標は、日本一の保育士になることでした。
中川李枝子『ママ、もっと自信をもって』(日経BP、2016)より
世界と絵本史の転換点に
この文章を日本語で読んでいる読者の中で、絵本『ぐりとぐら』をまったく知らないという人は、ほとんどいないだろう。筆者が教える大学の講義で、『ぐりとぐら』を読んだことがあるかと学生に尋ねると、大教室に座った19歳前後の受講生の大半が、一斉に手を挙げる。数年前まで保育園児だった私の子どもたちだって、もちろん『ぐりとぐら』で育った。自宅で、保育所で、地域を回る移動図書館で。病院の待合室で、不動産屋のキッズスペースで、オーガニックなカフェ、あるいは町中華で。タイミングは様々でも、私たちは子供時代のどこかで、あの青と赤の服を着たオレンジ色の野ねずみの双子の兄弟に出会い、大きな卵から作ったカステラを森の動物たちと分かち合う物語に触れたのではないか。
『ぐりとぐら』は時代を超えた存在、ロングセラー絵本の代表格だ。累計発行部数は、2024年10月の時点で571万部、250刷に達している(全22作のシリーズ累計では2200万部)[★1]。ロングセラーの定義からして当然のことだが、『ぐりとぐら』に時代や文脈、モード性を想起させる要素はほとんどない。手を挙げた大学生たちに、では『ぐりとぐら』はいつ頃書かれた作品か?と尋ねると、困惑したように、「30年前」とか「80年前」とか、さまざまな答えが返ってくる。「考えたこともなかった」というのが正直なところだろう。
実際には、『ぐりとぐら』の第1作は、1963年に「こどものとも」の12月号として配本され、1967年に「傑作集」入りして一般販売された。それは取りも直さず、この60年近くのあいだ、生まれた子どもと保育者が次々にこのシリーズの新しい読者になり続けてきたことを意味する。そのような受容のされ方をしている作品では、いつ誰が読んでくれたのか、誰からの贈り物だったのかといった、それぞれの本の中に宿る個別の「文脈」こそが重要で、作品自体がいつどのように書かれ(描かれ)たのかという生成論的な「文脈」は、意識されにくいのも当然だ。
しかし『ぐりとぐら』もまた、時代の中で生まれ、今も時代の流れの中にある。
*
2024年10月14日、『ぐりとぐら』の作者で児童文学作家の中川李枝子(1935–2024)が89歳で逝去した。さらにその9日後の10月23日、「いやだいやだの絵本」シリーズなどで知られる絵本作家のせなけいこ(1932–2024)が91歳で逝去した。両氏とも、老衰により亡くなったと発表された。
中川の死から遡ること2週間前の10月1日、『ぐりとぐら』や「いやだいやだの絵本」の版元でもある福音館書店のウェブサイトに、ひとつのニュースリリースが掲載された[★2]。それは1953年に創刊された同社の月刊誌『母の友』が2025年3月号をもって休刊し、70余年の歴史に幕を閉じることについての告知だった。「幼い子と共に生きる人への生活文化雑誌」を標榜する『母の友』は、『ぐりとぐら』を筆頭に数多くの名作を生んだ月刊絵本「こどものとも」の母体となった雑誌としても知られる。『ぐりとぐら』のプロトタイプとなる物語が最初に掲載されたのも、『母の友』の誌上だった(1963年6月号にモノクロ3ページで掲載された「三歳の子どもに聞かせる話 たまご」という作品)。
『母の友』の休刊理由は「昨今の情報メディアをめぐる環境の大きな変化」と説明された。全8行の簡潔なリリース文は、同誌の休刊と入れ替わりに開始される予定のウェブマガジンを予告して締めくくられた。
2024年に大きな変化を被ったのが、決して情報メディアだけでなかったことは、誰もが知っている。国内外の政治、戦争と人道危機、温暖化や自然災害など、世界の様々な領域で高いリスクを孕んだ環境変動が間断なく続き、それは2025年現在も収束どころか拡大の一途を辿っている。日本という国の退潮もますます明らかになる中で、今が歴史の転換点ではないかという感覚を、多くの人々が抱いている。その感覚の妥当性が真に明らかになるのはこれからだとしても、日本の絵本文化史に限れば、ひとつの節目を迎えていることは確かだろう。
『ぐりとぐら』の起源へ
今が歴史の巨大な転換点ではないかという予感のもと、ここで一度立ち止まり、歴史の淘汰を生き抜いてきた作品の「登場時の文脈」に目を向けたい、というのがこの短期シリーズ連載の目的である。時代を超える力を現に有してきた出版史上特筆すべき絵本は、元々、どのような社会や環境条件の中で、それまでの歴史をどのように引き継ぎ、いかなる問題意識を持った人々の実践を通じて誕生したものだったのか。それを確認することで、この先の未来を(願わくば出版文化に限らず、社会全般の未来を)構想するためのヒントが得られる可能性が、あるのではないか。このような関心から、「絵本作家・中川李枝子」と『ぐりとぐら』の成立過程を検討することを試みたい。
基本的な前提として、『ぐりとぐら』を考えることは、すなわち1960年代の日本における「創作絵本」というジャンルの確立について考えることである。ここで言う創作絵本とは、海外の絵本を翻訳したものや、すでに購買者が知っている古典や名作の再構成ではない、日本独自の新作物語絵本、という程度の意味だ[★3]。そうした新作がコンスタントに制作され、絵本受容のメインストリームになっていく動きが、この時代になぜ、どのようにして可能になったのかを、あらためて考えてみたい。もちろん、創作絵本文化の立ち上がりは複数の担い手による多様な実践を通して進行した複雑なプロセスであり、中川の個人史だけで説明できるものではない。しかし少なくとも、この問題の重要な一側面を理解する助けにはなるはずである。
幸いにして、中川の生涯や『ぐりとぐら』については、作家本人による回顧の書籍、新聞や雑誌の取材記事、シリーズのファンに向けた書籍やムック本など、極めて豊富な資料が存在している。この連載では、論点を絞ったうえでそれら複数の記述を比較することで、大きな系譜や時代の動きを可視化することを試みる。連載1回目となる今回は、中川が「保育園」の「保母」という出自を持っていたことの意義について考えてみたい[★4]。
ただ、子どもの世界に寄り添って(ジブリへの地下水脈)
ところで、中川が紡ぎ出す物語の特徴のひとつは、主人公が困難を克服して成長するといった一般的な説話構造が、原則として採用されていないことだ。それは、アニメ監督の宮崎駿(1941–)による、以下の発言で要約できるかも知れない。
僕たちが作るファンタージーでは、冒険に出て、いろんなことを経験して、賢くなって、成長して帰ってくる。そんなの嘘ですよね(笑)。子どもはそんなに簡単に成長しない。子どもは同じ間違いを繰り返すし、それをしていいのが子ども時代であって、そんな子どもそのものの姿が描かれているのが『いやいやえん』や『ぐりとぐら』だと思う[★5]
じっさい、ぐりとぐらは合理的な説明などなしに巨大な卵を発見し、美味しいカステラを焼いて動物たち(縮尺がバラバラのワニやライオンやキリンを含む)と分かち合い、卵の殻で作った自動車を運転して帰っていく。そこには教訓も、狭義での苦難の旅路もなく、ただ子どもたちの世界に寄り添おうとするイマジネーションだけが広がっている。
宮崎駿は中川より6歳年下だが、大学生だった1960年代前半に中川の児童文学に出会い、そのストーリーテリングから絶大な影響を受けたことを、インタビュー等で繰り返し語っている[★6]。だからこそ、「となりのトトロ」の主題歌「さんぽ」の歌詞は中川に依頼されなくてはならなかったし、宮崎/スタジオジブリは『そらいろのたね』『くじらとり』『たからさがし』などの中川作品を、あたかも強い使命感に突き動かされるかのように、繰り返し短編アニメ化してきた。さらに宮崎駿自身の長編脚本もまた、徐々にビルドゥングス・ロマン的な辻褄のある物語展開を拒む方向に発展していくことになるが、それはまた別の話だ。
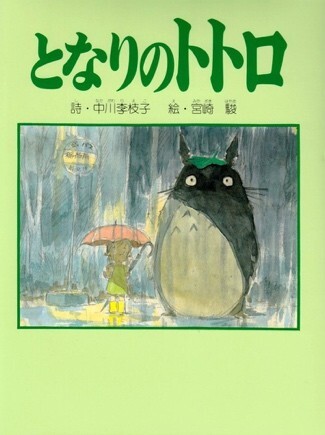
「保母」という起源
このような中川作品の特徴を理解するうえで決定的に重要なのが、現在で言う「保育士」、あえてかつての言い方で言えば「保母」という、中川のルーツにあると考えられる。
「小さなころから本は大好きでしたが、作家になりたいと思ったことはありませんでした。なりたかったのは「日本一の保育士」です。」(中川李枝子『ママ、もっと自信をもって』、日経BP 、2016年、p.1)
「保育園で幸せな子どもを眺めるのが、私の最大の楽しみ。だから子どもたちを喜ばせたくなる。それが私の書く動機です」(同、p.81)
晩年の、上記のような発言からも分かるように、中川は「保育」こそが自身の活動の目的だと、一貫して語ってきた。中川が保母として働いていたのは、20歳(1955年)頃から37歳(1972年)頃までの約16-17年間だが[★7]、それ以降も含め、中川にとっての絵本や児童文学の執筆は、あくまで保育ないし子どもを喜ばせるための「手段」、あるいは「結果」だと定義されている。
そして、おそらくそれと表裏をなす問題として、中川の作品群の中でも特に名作とされる絵本は、彼女が保母だった時期に集中して生まれている。もちろん中川は専業の絵本作家となって以降も数多くの優れた絵本や児童文学を執筆したし、「東京子ども図書館」(1974年創設)の理事や講演活動、海外児童文学の翻訳など、その活動領域は狭義での絵本に留まっていない。作家としての評価は、それら生涯を通じての実践の全体像を踏まえてなされるべきものである。そのような前提に立った上で、『いやいやえん』(1962)、『ぐりとぐら』(1963)、『かえるのエルタ』(1964)、『そらいろのたね』(1964)、『たんたのたんけん』(1971)、「くじらぐも」(1972)[★8]などの突出したロングセラーが多く生まれた時期は、彼女が保母を職業にしていた期間に、明らかに重なっている。
では中川の中で、保母であることと創作活動は、どのように繋がっていたのだろうか。話の前提として、保育園(法令上の正式名称は「保育所」)、そして保母とは何かを確認したい。
保育園と混同されやすい「幼稚園」は、あくまで学校に入る前段階の教育を主目的に制度設計されたものだ。幼稚園の設置基準や幼稚園教諭の資格を規定するのは「学校教育法」で、この法律は文部省(のち、文部科学省)の管轄である。対して保育園や保母資格を規定するのは「児童福祉法」で、厚生省(のち、厚生労働省を経て、こども家庭庁)が管轄する。現在では新制度のもと幼稚園と保育園の一体化が進められているが、歴史的に見れば、保育園は子どもの生命を守る福祉政策の一環、もっと具体的に言えば、子どもを世話する親がいない時間帯の託児施設という性質を、強く持っている。
そして日本における保育園の起源のひとつに、昭和の戦中期に設置が進められた「戦時託児所」がある。もちろん地域コミュニティー内での互助的・自然発生的な形態を含めて、集団での託児施設は、戦前からさまざまな形態で存在してきたはずだ。しかし戦況が悪化した太平洋戦争末期、男性の出征による労働力不足が深刻化するなかで、国家総動員法や国民徴用令を根拠に、学生から主婦まであらゆる世代の女性の強制的な動員が、国家規模で進められたことは大きな転期となっただろう。
家庭から女性を労働者として徴用してしまうと、誰がその間の子どもの面倒を見るのか、という問題が発生する。その対策として幼稚園からの転換、あるいは新設で、全国に戦時託児所が設置されることになった。これは、限られた裕福な家庭の子どもだけが通う幼稚園でも、特に貧しい家庭の支援だけを目的にした養護の施設でもなく、広く子どもたちを集めて集団保育する制度が大規模に実施されたという意味において、現在の保育園像と連続している。
児童福祉法、児童憲章、保母
そして敗戦後も、「保育が必要な未就学児童が大量に存在する」という社会問題は引き続いた。戦災者や引揚者が溢れ混乱した当時の日本は、孤児対策をはじめ児童福祉に関する問題をいくつも抱えていたが、それらに対処するための政策を基礎づけたのは、GHQだった。現在に至るまで日本の児童福祉の基本法となっている「児童福祉法」は、占領下の1947年に制定されている。
児童福祉法の第一章第一条は、「全ての児童は、適切に養育され、生活を保障され、愛され、保護され、心身の健やかな成長・発達と自立が図られる権利を有する」という主旨の総則で始まる。復興から高度経済成長へと至る戦後初期の児童福祉・幼児教育関係者の発言を確認すると、この児童福祉法と、先行する1946年の「日本国憲法」、後続する1951年の「児童憲章」の3つを、ひと続きのものとして解釈し、それらの中で表明された児童観を自らの実践の精神的支柱としている場合が非常に多い(中川も、そのような保育像を繰り返し語っている)。
「児童の保育に従事する女子」を「保母」という認定資格として制度化することで、保育の質の保証を進めたのも、児童福祉法だった[★9]。そして、この児童福祉法による規定を根拠に、全国規模で「保母の養成」が推進されることになった。保育所数が激増するなかで、保母の数が圧倒的に不足していたからだ。児童福祉法の制定以前に5年以上の実務経験を持つ者に対する特例措置も併用されたが、より安定して人材を供給するために、地方自治体が公立で養成施設を運営する動きが、1940年代末に急速に進んだ。
中川は、1954年に19歳で「東京都立高等保母学院」に入学しているが、これは1947年に日本で最初に厚生大臣の認定を受けた保母養成施設であり(開設は1948年)、したがって中川は、文字通り戦後最初の世代の保母だということになる。
「花子とアン」と中川李枝子
では中川個人は、なぜ保母を志したのだろうか。本人の説明によると、中学生時代に伝記物語『ジェーン・アダムスの生涯』を読み、決定的な影響を受けたからだという[★10]。ジェーン・アダムス(1860–1935)は、貧民街の児童など社会的弱者を支援し教化する英国発祥の運動「セツルメント」をアメリカで展開した女性運動家で、1931年にノーベル平和賞を受賞している。彼女の伝記は、村岡花子(1893–1968)の翻訳で、岩波少年文庫に収録されていた[★11]。
村岡花子は、NHK連続テレビ小説「花子とアン」(2014)のモデルにもなったプロテスタントの翻訳家で、『赤毛のアン』を日本に紹介したことで知られる。村岡は、戦前からラジオの悩み事相談などで活躍する、婦人問題や教育問題のオピニオンリーダーでもあった(絵本分野では、バージニア・リー・バートンの『いたずらきかんしゃちゅうちゅう』などの翻訳を手掛けた)。中川李枝子は8歳頃から、童話集『たんぽぽの目』(鶴書房、1941)の作者として、村岡花子の存在を認識していたと語っている[★12]。
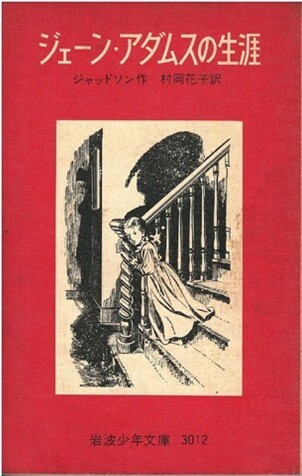
『ジェーン・アダムスの生涯』は、アメリカの女流児童文学者クララ・イングラム・ジャッドソン(1879–1960)によって書かれ、物語としての色合いがかなり強い。少女時代のジェーンの愛らしい日常描写から始まる、当時の子ども向け伝記らしい構成は、他の岩波少年文庫の名作物語と同じような感覚で読むことができる。村岡は訳者序文で、少年よりも少女に多く読まれる本になるだろうと予想したうえで、生涯の使命となる仕事と生活を真剣に考えてほしいと読者に呼びかけている(本稿エピグラフ参照)。
トットちゃん、だるまちゃんとの交差
そのようなわけで、中川はかなり理念的な問題意識によって、東京都立高等保母学院に入学したと考えられる。保母不足が深刻な問題だった当時、同学院の学費は無料で、少額だが毎月資金援助もあったらしい[★13]。けれども、中川の生家(大村家)の場合、大きな経済的困窮はなかったはずだ(中川の父・大村清之助は、農学博士号を持つ蚕糸技術者で、高円寺の蚕糸試験場に勤務していた)。中川は実践女子学園高等学校に通っていたので、実践女子大学に進学することは可能だっただろうし、後に『ぐりとぐら』をはじめ多くの作品でコンビを組む中川の実妹で挿絵画家の山脇百合子は、1960年に上智大学のフランス語学科に入学している[★14]。高等保母学院で「女性たちが真摯に学ぶ姿に志の高さを感じ、ここで学びたいと決め」たという[★15]、中川の回顧のとおりなのだろう。
結果的に、中川の生涯を貫いた保育理念の少なからぬ部分は、この高等保母学院で形作られた。中川は、学院での体験について「児童福祉法と同じ年にできた保母学院の先生方は、児童の権利を守る意欲に燃え、授業は刺激的でした。戦前・戦中・戦後の困難な時代、恵まれない子ども達を守り抜いたつわものぞろい。」と、思いを込めた表現で述懐している[★16]。
東京都立高等保母学院の歴史を研究した学術文献によると、同学院では創設後しばらくの間、東京都民生局の課長が学園長を務めるなど、都庁の出先機関的な性質が強かったらしい[★17]。そのような状況の中で実質的な教育の質を担保したのは、各授業を担当した非常勤の講師陣だった。
制度がいかに設計されようと、保育について教えることは高度に専門的な領域である。創設期の東京都立高等保母学院では、東京都民生局職員の秋田美子らの尽力によって、当時一線級の教育者や児童福祉専門家が、数多く講師として登用された(秋田自身も、戦前から保母としての経歴を持つ児童教育の有識者だった)。
例えば、「リトミック」の授業を担当したのは、1937年にトモエ学園を創設し校長を務めた小林宗作、つまり、大ベストセラーとなった黒柳徹子の自伝的物語『窓ぎわのトットちゃん』(講談社、1981)に登場する「小林先生」だった[★18]。戦時中に抑圧されていた大正自由教育運動の流れを汲む進歩的実践が、戦後になって保育者不足に対処するための人材育成事業に招聘され、思想的系譜として接続していたという事実は興味深い。
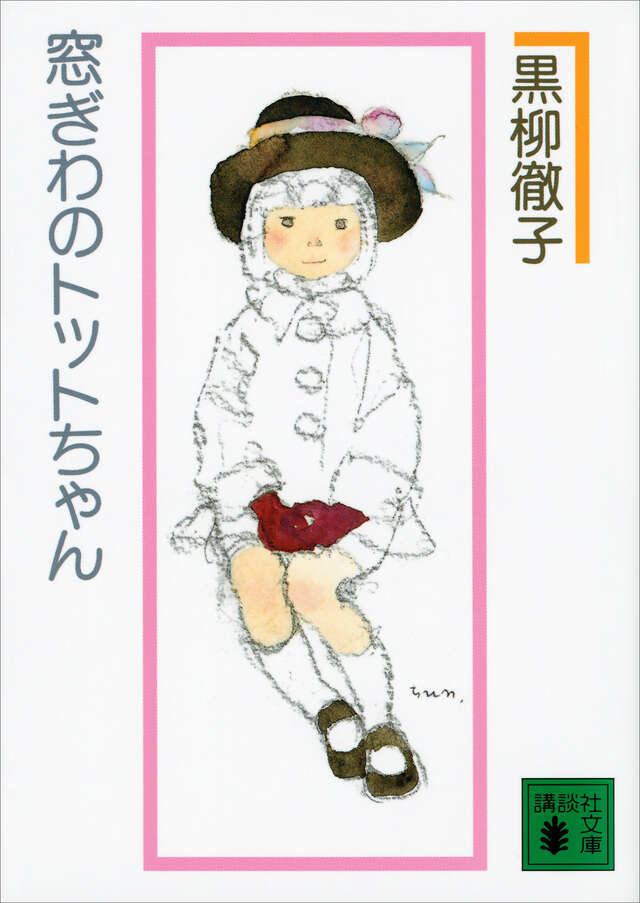
さらに中川は、保母学院在学中に実習やボランティアで、さまざまな児童福祉の現場に触れることになった。例えば、中川の未完の同人小説「青空が見えるまで」は、彼女が実習で訪れた養護施設「東京家庭学校」[★19]での体験が、色濃く反映されたものだ。
「ええと、お母さんは、女中さんか。1ヶ月に、一度くらいは、会えるだろうね。」[中略]
廊下を曲がると、プーンと便所の臭いが、信太の鼻をついた。[中略]礼拝堂は[中略]日曜日になると、近所からクリスチャンが集って、礼拝が行われるし、時にははなやかな結婚式場にもなる所だったから、便所くさい寮[引用者注;主人公が入居する児童養護施設]と、一緒に考えるわけには、いかない。
(中川李枝子「青空が見えるまで」、同人誌『麦』掲載、1956–1958年〈未完〉より)
また、数回だが東京・川崎のセツルメントにも参加している[★20]。だがそれは、シカゴの美しい隣保館を舞台にした『ジェーン・アダムスの生涯』が描く、理想化されたセツルメントのイメージとは、かけ離れたものだったという。「ごくふつうの民家」で「育ち盛りの5、6年生くらいの男の子が大勢集まって」「叫び、どなり、押しあい、ぶつかりあい」する「決して甘くない」日本のセツルメントの実情を目の当たりにした中川は、「肝を潰して逃げ帰った」と回顧する[★21]。
そしてこのとき、中川は絵本作家としてデビューする前のかこさとし(1926–2018)と遭遇している。中川よりも9歳年上のかこは、東京大学工学部を卒業して昭和電工で働く傍ら、東大セツルメントに深く携わり、1954–55年頃は川崎セツルメントにおける児童教育の中心人物だった[★22]。中川ら見学者たちに目もくれず、スーツ姿で大声を張り上げ、わんぱくな少年たちと渡り合って全体を取り仕切るかこの姿は、中川の心に強い印象を残した。かこがそこで実践していた幻燈や紙芝居の制作、児童との交流経験は、この後に『だるまちゃんとてんぐちゃん』(福音館書店、1967)、『からすのパンやさん』、『どろぼうがっこう』(いずれも偕成社、1973)といった絵本作品に反映されていくことになる。
そうした様々な経験を経て、2年間の保母養成課程を終え、1956年に東京都立高等保母学院を卒業した21歳の中川は、現在の駒沢オリンピック公園内に所在していた「みどり保育園」で主任保母として働き始める。その保育の現場で、中川が絵本作品をいかにして生み出していったのかは、次回見ることにしよう。

理念と現実の交点で
以上今回は、保母とは何か、なぜ保母にならなくてはいけなかったのかという視点を中心にしながら、デビュー以前の中川李枝子を、児童福祉を中心とする歴史の文脈の中に配置することを試みた。戦中から現在に至るまで、保母(保育士)はその専門性や業務負担に比して正当な待遇を与えられないまま、社会構造の皺寄せを引き受けてきた女性の仕事、という側面を持っている(厚生労働省の調査によると、2020年の時点でさえ、日本の保育施設で働く職員の95.8%は女性である[★23])。
だが、日本の保育園制度の立ち上がりは、戦後民主主義がもっとも希望に満ちていた時代の、美しい輝きの一つであり、そこへ戦前からの児童教育実践理念も接続されているなど、多様な側面を孕んでいる。次回以降では、そのような多面性の上に、『ぐりとぐら』の参照項となった海外絵本の存在、村岡花子や村岡に『ジェーン・アダムスの生涯』の原書を提供したという岩波書店編集部の石井桃子(1907–2008)ほか、先行する世代の女性作家/編集者が中川に与えた影響、福音館書店社長・松居直(1926–2022)が絵本出版界に起こした編集と流通の革命、そして『ぐりとぐら』の「え」を担当した中川の実妹・山脇百合子の存在といった論点をさらに重ねることで、「ぐりとぐらの時代」の意味を読み解いていきたい。
*
ところで、東京都立高等保育学院は、中川の卒業後も増え続ける保母需要に対応するべく定員を拡大し、1970年代には都内4校にまで増設された。だが、民間の短大・専門学校をはじめとする保母(保育士)資格の取得手段の増加や、保育園をめぐる状況変化の中で、次第に歴史的な使命を終え、2001年3月までに全校が閉校になった。現在、卒業生に対する証明書等の発行業務は、東京都福祉局(子供・子育て支援部)に移管されている。
(つづく)
謝辞
この論考は、愛知淑徳大学の2025年度特定課題研究助成からの支援を受けて執筆されました。また執筆にあたり、岡田泰枝氏(幼児教育)、酒井晶代氏(児童文学)からご助言を賜りました。御礼申し上げます。ただし本論の文責はすべて筆者にあります。
★1 「作家・中川李枝子さん死去 絵本「ぐりとぐら」やトトロ「さんぽ」」、 朝日新聞デジタル、2024年10月17日 。
URL= https://www.asahi.com/articles/ASSBK1G01SBKUCVL019M.html
★2 「月刊誌「母の友」休刊のお知らせ」、福音館書店ウェブサイト、2024年10月1日。
URL= https://www.fukuinkan.co.jp/oshirase/detail.php?id=943
★3 ここで本稿が述べている「物語絵本」も、またあくまで大まかな説明である。実際には人文科学の解説的な要素が強い絵本や、0〜3歳程度の未満児に向けて書かれた絵本など、物語要素が薄い作品も含まれる。ちなみに1960年代後半から1970年代以降になると、徐々に絵本の中でもサブジャンル化が進み、科学的なものは「認識絵本」、未満児向けのものは「赤ちゃん絵本」など、カテゴリーが分かれていく。
★4 小学校入学前の子どもを保護者に代わって保育する「保母」という職業(認定資格)は、男女共同参画社会基本法を踏まえて、1999年以降「保育士」の呼称に変更されている。だが本稿では、「保母」という表記を意図的に使用する。これは、中川が保育園に勤めていた時代に使われた実際の名称が「保母」だったからのみならず、日本の豊かな絵本文化とは、「保母」のような言葉遣いに象徴される不平等な性別役割意識に支えられた成人男性中心社会と、表裏一体をなすような形で生まれたものだとも考えているからである。
★5 「宮崎駿氏、『ぐりとぐら』作者・中川李枝子氏と対談「別格官幣社」と絶賛」、ORICON NEWS、 2014年2月1日。
URL= https://www.oricon.co.jp/news/2033601/full/
★6 一例として、「【中川李枝子さん×宮﨑駿さん・対談】『いやいやえん』から生まれたアニメ「くじらとり」。すべては子どもから教わったこと」(HugKum 、2024年12月1日)や、「【追悼】『トトロ』から『ポニョ』へ、中川李枝子が宮崎駿に与えた影響」(アニメージュプラス、 2024年10月17日)など。それぞれ以下のURLから閲覧できる。
URL= https://hugkum.sho.jp/662416
URL= https://animageplus.jp/articles/detail/60601/2/1/1
★7 『ISSUE 中川李枝子 冒険のはじまり』(スイッチパブリッシング、2024年)掲載の「中川李枝子 年譜/作品一覧」124頁では、1956年(21歳)に保母としてみどり保育園で働き始め、1972年にみどり保育園が閉園したとされている。いっぽう、神宮輝夫『現代児童文学作家対談3』(偕成社、1988年)掲載の「中川李枝子年譜」240-241頁では、1955年(20歳)にみどり保育園での勤務を始め、1970年(35歳)でみどり保育園が閉園となり保母をやめたと記載されている。中川李枝子本人は、『子どもはみんな問題児。』(新潮社、2015年)p.7ほかにて「17年間保母をして」と語っている。
★8 中川が光村図書の依頼で書き下ろした童話「くじらぐも」のこと。1972年の初掲載以来、現在まで小学1年生の国語教科書に採用され続けている。内容は、『いやいやえん』に収録された「くじらとり」の発展形という側面を感じさせる。
★9 保母という言葉自体は、児童福祉法以前から存在している。戦前から戦中期においては、幼稚園令が規定する幼稚園で働く婦人の認定資格(現在の幼稚園教諭に近い)、法的な規定のない託児施設で働く婦人、少年教護院(今でいう児童自立支援施設)で働く婦人など、実情の異なる複数の専門職域が、保母(保姆)という職名でカテゴライズされていたようである。
★10 中川李枝子『本と子どもが教えてくれたこと』、平凡社、2019年、44頁。
★11 ジャッドソン『ジェーン・アダムスの生涯』、村岡花子訳、岩波少年文庫、1953年。なお、中川の中学時代ということは、1948年から1950年頃ということになるが、日本での『ジェーン・アダムスの生涯』の刊行は1953年で、訳者の村岡による序文の日付も1953年3月となっている。中川が同書を読んだのは、実際には高校時代以降かも知れない。岩波少年文庫が中川の文学的素養の形成に果たした役割については、本連載の次回以降で確認したい。
★12 村岡恵理編『村岡花子と赤毛のアンの世界』、河出書房新社、2013年、144頁。
★13 下記のnote記事を参照。「児童文学作家「中川李枝子さん」と「都立高等保母学院」と、ちょこっと「母」のこと~そして、私が譲れないこと」、2024年。
URL= https://note.com/jj1snc/n/ne6f8c0815556
★14 カトリック系の上智大学が女子学生の入学を許可したのは1957年からなので、山脇はもっとも初期にこの4年制私立大学でフランス語を学んだ女性だったことになる。
★15 『ママ、もっと自信をもって』、日経BP社、2016年、68頁、あるいは『本と子どもが教えてくれたこと』、45頁。高校時代に、父が購読していた雑誌『遺伝』に掲載されていた「学校探訪」のコーナーを読んで、東京都立高等保母学院の存在を知ったとある。1947年に創刊された生物科学の総合啓蒙誌『遺伝:生物の科学』(裳華房)のことか。
★16 『ママ、もっと自信をもって』、69頁。
★17 江津和也「保育所保育の歴史的変遷の中で東京都立高等保母学院が果たした役割」、『淑徳大学研究紀要 総合福祉学部・コミュニティ政策学部』50号、2016年。
★18 小林宗作が東京都立高等保母学院で教鞭を執った期間に関しては、正確な資料を確認できなかったが、少なくとも中川の1年前に入学した元学生は、小林の授業を受けたと証言している。小林は、中川が入学した1954年の時点で61歳前後である。下記のnote記事を参照。「母の「ノート」が素晴らしくて、捨てられない話」、2022年。
URL= https://note.com/jj1snc/n/n197bd2c21e75
★19 東京家庭学校は、キリスト教精神に基づく児童福祉施設。留岡幸助(1864–1932)が1899年に創設した民営の感化院の活動に始まり、現在も東京都杉並区で事業を継続している(公式サイトは以下。URL= https://katei-gakko.jp)。留岡幸助は、同志社英学校で新島襄の教えを受けたプロテスタントの牧師で、社会事業家。中川の父、大村清之助(1907–1990)も、北海道大学の学生時代に留岡幸助の思想から大きな影響を受け、札幌の養護施設に下宿していたこともあったという。『ISSUE 中川李枝子 冒険のはじまり』、67頁。
★20 中川は、セツルメントが戦前から東京で展開されていたことを知らなかったらしいが、保母学院で「保育理論」を担当していた講師が、女子大生時代からセツルメントで活動した経歴を持っていた。また、すでに活動に参加済みの上級生もいたことから、在学中に川崎セツルメントに2、3回ほど足を運んだという。かこさとし『未来のだるまちゃんへ』、文春文庫、2016年、264-267頁(中川による巻末解説)、中川李枝子『本・子ども・絵本』、文春文庫、2018年、176頁などを参照。なお、「保育理論を担当していた講師」とは、前述した東京都民生局職員の秋田美子だと思われる。
★21 かこ『未来のだるまちゃんへ』、265-266頁(中川による巻末解説)。
★22 なお、かこが川崎セツルメントに参加した際の写真は公式サイトのブログに掲載されている。
URL= https://kakosatoshi.jp/blog/%E4%B8%80%E6%9E%9A%E3%81%AE%E5%86%99%E7%9C%9F/
★23 厚生労働省「保育士の現状と主な取組」 。
URL= https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000661531.pdf


阿部卓也




