「ポスト」モダニズムのハード・コア──「貧しい平面」のゆくえ(23)|黒瀬陽平

初出:2018年02月16日刊行『ゲンロンβ22』
ポストモダニズムという語が、視覚芸術つまり平面作品に対してはじめて適用されたのは、レオ・スタインバーグの「他の批評基準」においてであるといわれている[★1]。スタインバーグは、1950年代にあらわれた一群の新しいタイプの絵画たちが、情報化社会に代表されるポストモダンな社会状況と密接に関係していることを示そうとした。そのために彼が考えた新しい概念が、かの有名な「平台型絵画平面(flatbed picture plane)」である。
「flatbed(フラットベッド)」とはもともと、平台印刷機の原稿台部分を指す技術用語で、いわゆるコピー機やスキャナで印刷する原稿を置く、水平のガラス面のことだ。平台型絵画平面は、まるでフラットベッドのように、あらゆるオブジェやテクスト、イメージを取り込むことができる。それは、直立して世界を見る人間に対応した垂直のスクリーンに、世界を再表象するイメージが投影されるというモダニズムの絵画平面の「垂直性」とはまったく異なる「水平性」である。
スタインバーグは、ロバート・ラウシェンバーグの作品を例に挙げながら、その水平の場が、テーブルの天板やアトリエの床、図面、掲示板といった、その上になんでも貼りつけておける「作業場」のような固い面であることを強調しつつ、さらに、様々なデータが記入される「受容器(レセプタ)」でもあると指摘する。
垂直のスクリーンから、水平の作業面へ。視覚による自然の体験ではなく、情報の人工的な操作。スタインバーグはそれを「芸術の主題の最もラディカルな移行、つまり自然から文化への移行」であると言っている。
グリーンバーグのモダニズム絵画論批判として書かれた「他の批評基準」が、どんなに抽象化が進んでも消えることのなかったモダニズム絵画の垂直性、人間に向かって世界を表象するという構造を過去のものとし、人間の自然な視覚とは異なる人工的な平台型絵画平面を最も新しい絵画平面として提示するというスタインバーグの戦略は、まさに再現=表象の秩序に潜む近代の欺瞞を糾弾し、その構造を徹底的に解体しようとするポストモダニストの手つきであるだろう。 しかし注意すべきは、どうやらスタインバーグは、再現=表象という原理を完全に捨て去ろうとしたわけではなかった、という点である。
「ふたたび世界を取り入れた画面」という以上、そして、それを成し遂げたことを最大級に評価している以上、それは再現=表象そのものではないにしても、世界を表す絵画という着想を根本から否定するものではないはずだ。少なくとも、ラウシェンバーグ平面作品を「写真と絵画の共謀による絵画それ自体の解体」(ダグラス・クリンプ)であると早合点してしまうような、再現=表象批判しか眼中にない凡庸なポストモダニズム批評では、平台型絵画平面が新たに取り入れた「世界」を記述することはできないだろう。
たとえば、同じく平台型絵画平面の作家に分類されているアンディ・ウォーホルの絵画平面の場合、そこでおこなわれていることはもう少しシンプルである。
マスメディアによってすでに変換され、消費・流通を続けるイメージを、独自の方法で再びイメージにすること。「現実世界から最初に取り出したイメージから後退し続ける」(デヴィッド・アンティン)イメージのイメージ。ここで絵画平面がとらえるイメージは、マスメディアによって媒介され、後退を続けているとはいえ、しばしばウォーホルの作品が「ポップアイコン」という概念によって説明されるように、何重かに間接化された再現=表象のバリエーションとして認知することが可能である。
◾️
「flatbed(フラットベッド)」とはもともと、平台印刷機の原稿台部分を指す技術用語で、いわゆるコピー機やスキャナで印刷する原稿を置く、水平のガラス面のことだ。平台型絵画平面は、まるでフラットベッドのように、あらゆるオブジェやテクスト、イメージを取り込むことができる。それは、直立して世界を見る人間に対応した垂直のスクリーンに、世界を再表象するイメージが投影されるというモダニズムの絵画平面の「垂直性」とはまったく異なる「水平性」である。
スタインバーグは、ロバート・ラウシェンバーグの作品を例に挙げながら、その水平の場が、テーブルの天板やアトリエの床、図面、掲示板といった、その上になんでも貼りつけておける「作業場」のような固い面であることを強調しつつ、さらに、様々なデータが記入される「受容器(レセプタ)」でもあると指摘する。
……情報を載せる平らな文書の面であればどんなものでも、彼の絵画平面に相応しく、またそれと類似するものである──人間の視野と光学的に照応する透明な映写面とは、根底的に異なるのだ。そして折にふれ私が思うのは、ラウシェンバーグの作業面は精神それ自体を表している、ということである。──まるで心の中でする独白のように、イメージが具体的ななにかを示そうとするその作用が、自由な連想にしたがって互いに結びつきあいながら溢れかえる、ごみ捨て場、貯蔵庫、交換所──外部世界をつぎつぎ交換するものとしての精神を、その外部にあって象徴するもの。それは流入してくる未処理のデータを、もはや情報過多となってしまった場にそれでもならべようとして、絶えず摂取し続けているのである[★2]。
垂直のスクリーンから、水平の作業面へ。視覚による自然の体験ではなく、情報の人工的な操作。スタインバーグはそれを「芸術の主題の最もラディカルな移行、つまり自然から文化への移行」であると言っている。
グリーンバーグのモダニズム絵画論批判として書かれた「他の批評基準」が、どんなに抽象化が進んでも消えることのなかったモダニズム絵画の垂直性、人間に向かって世界を表象するという構造を過去のものとし、人間の自然な視覚とは異なる人工的な平台型絵画平面を最も新しい絵画平面として提示するというスタインバーグの戦略は、まさに再現=表象の秩序に潜む近代の欺瞞を糾弾し、その構造を徹底的に解体しようとするポストモダニストの手つきであるだろう。 しかし注意すべきは、どうやらスタインバーグは、再現=表象という原理を完全に捨て去ろうとしたわけではなかった、という点である。
ジャスパー・ジョーンズが、ラウシェンバーグこそピカソ以後今世紀最大の革新をなした男だというのを、私はかつて聞いたことがある。ラウシェンバーグの成した最大の革新、それは私の考えでは、ふたたび世界を取り入れた画面のことである。窓の外の眺めに天気を知る鍵を見つけようとする、ルネサンス人の世界ではない。どこか窓のないブースから電子的に伝えられる、テープに吹き込まれた「今夜の降水確率は十パーセント」というメッセージを聞くために、つまみをひねる人間の世界。ラウシェンバーグの絵画平面は、都市の頭脳にどっぷりと浸かった意識のためにあるのだ[★3]。
「ふたたび世界を取り入れた画面」という以上、そして、それを成し遂げたことを最大級に評価している以上、それは再現=表象そのものではないにしても、世界を表す絵画という着想を根本から否定するものではないはずだ。少なくとも、ラウシェンバーグ平面作品を「写真と絵画の共謀による絵画それ自体の解体」(ダグラス・クリンプ)であると早合点してしまうような、再現=表象批判しか眼中にない凡庸なポストモダニズム批評では、平台型絵画平面が新たに取り入れた「世界」を記述することはできないだろう。
たとえば、同じく平台型絵画平面の作家に分類されているアンディ・ウォーホルの絵画平面の場合、そこでおこなわれていることはもう少しシンプルである。
彼(ウォーホル)の絵はあるイメージのイメージと捉えられている。このような把握の仕方が保証してくれるもの、それは、この絵の提示するものが直ちに世界空間の提示というわけではないだろうということ、そして、にもかかわらずこの絵は、どのような経験でも再現する題材として認めるだろうということである。しかもそれは、技術者としての芸術家と同じく、人間的な関心に満ち満ちた芸術家をももう一度認めてくれるのである[★4]。
マスメディアによってすでに変換され、消費・流通を続けるイメージを、独自の方法で再びイメージにすること。「現実世界から最初に取り出したイメージから後退し続ける」(デヴィッド・アンティン)イメージのイメージ。ここで絵画平面がとらえるイメージは、マスメディアによって媒介され、後退を続けているとはいえ、しばしばウォーホルの作品が「ポップアイコン」という概念によって説明されるように、何重かに間接化された再現=表象のバリエーションとして認知することが可能である。
しかし、ラウシェンバーグがつくりあげたという「ふたたび世界を取り入れた画面」とは一体なんだろうか。すでに確認したように、ラウシェンバーグの平台型絵画平面は、あらゆるオブジェやテクスト、イメージが並ぶ作業面であり、データを記入する「受容器」であるため、そこに再現=表象として統一的な視覚像を結ぶことはない。そのことは、ラウシェンバーグの1950年代のコンバイン・ペインティングでも、1960年代からはじまる写真の転写を用いた作品群でも、一貫して変わらないように見える。にもかかわらず、ラウシェンバーグの絵画平面が「ふたたび世界を取り入れた画面」であるといわれるのはなぜだろうか。
おそらく、最も簡単な解答は、「平台型絵画平面は、それとわかる対象を収容するかぎりは、その対象を、普遍的に親しまれている特徴を具えた人工のものとして提示する」[★5]からである、というスタインバーグの言葉を引くことであろう。再現=表象としてのイメージではなく、人工物そのものが、作業面としての絵画平面に直接貼り付けられている。まさにそれが、ラウシェンバーグの作品でおこなわれていることである。
スタインバーグは、《ベッド》(1955年)や、《三度目の絵画》(1961年)に貼りつけられた時計、あるいは《冬のプール》(1959-60年)の梯子といった、ほとんどそのままの状態で貼りつけられた人工物を、ラウシェンバーグ作品における極めて重要な「象徴」として読み解こうとしている。つまり、抽象表現主義のように世界をすべて平面性に溶かし込もうとする操作を被ることなく、同時に、再現=表象の視覚的イメージとしての描写という「後退」からも逃れ、それでもなお、現実世界に存在する具体的な人工物として絵画平面に侵入し、それがそのまま「象徴」にまで高められる。ラウシェンバーグの作品に貼りつけられた人工物たちは、言ってみれば、様々な「批評基準」の間を綱渡りのように渡り、見事に無傷のまま、絵画平面にまでたどり着いたのである。
◾️
こうして、スタインバーグの提唱した平台型絵画平面は、絵画史における「他の批評基準」を担う新しい概念として提出された。最重要作家として挙げられたラウシェンバーグの絵画平面は、あらゆるものが等価に並べられる作業面としてだけでなく、データを記入する「受容器」という、情報社会以後のアートにおいて、今でもきわめて魅力的なコンセプトを宿していると言ってよいだろう。
しかし、スタインバーグが提示する、このいささか楽観的にも思えるヴィジョンは果たしてどこまで額面どおり受け取ってよいものなのだろうか。先に確認したとおり、ラウシェンバーグの絵画平面において、そのままの人工物やデータが並べられ、出会い、時として「象徴」にまで高められる操作があり得るのはよいとして、ではそのようにしてつくられた絵画平面それ自体は、一体何を表しているのだろうか。このことについて、美術史家の林道郎はスタインバーグのいう平台型絵画平面を、一般論的に現代の情報社会環境に結びつけること、とりわけ、コンピューターのデスクトップと同じように考えてしまうことに対して批判的な見解を述べている。
ラウシェンバーグの絵画平面は、ゴミのようなものたちで溢れている。ベッドにせよ、時計にせよ、梯子にせよ、それらはもはや正常に機能しないゴミたちだ。しかし、当然のことだが、それらははじめからゴミであったわけではない。それらの人工物やデータは、平台型絵画平面へと貼りつけられることによって、本来の機能を果たさないゴミとなったのだ。
平台型絵画平面はたしかに、あらゆるものを取り込むことができる。しかしそれは、取り込まれたものたちが本来の機能を剥奪され、ゴミとなる限りにおいてなのだ。その上になんでも置いておけるような水平な作業面、いくらでもデータを書き込める受容器としての平台型絵画平面は、印刷機やスキャナのフラットベッドのように、取り込んだものをひとつの形式に変換し保存しておけるのではなく、同じ平面の上に異なる対象を並置することによって、それらをゴミに変えてしまう場だったのではないか(印刷機やスキャナのフラットベッドに正しく対応するのはおそらく、平台型絵画平面ではなくマン・レイの「フォトグラム」だろう)。
多様なもの、多元的なものを併存させるヘテロトピア的平面が裏返って、すべての機能が剥奪されゴミになってしまうディストピアへと変わる。平台型絵画平面は、「他の批評基準」において乗り越えたはずだったモダニズム絵画の「貧しさ」とは別種の「貧しさ」を宿命づけられた「貧しい平面」であった。
「貧しい平面」としての平台型絵画平面について、林による賢明な警告を気にかけつつ、あえてもう少しだけ、今日の情報社会的テーマに類比させて考えるとすれば、インターネットにおける「認知限界」(ハーバード・サイモン)や「パーソナライゼーション」などの問題を対応させるべきではないだろうか。カリフォルニアン・イデオロギーの現実的失効を例に出すまでもなく、私たちはすでに、多様な情報が多元的に併存するヘテロトピアとしてのコンピューター、インターネットという幻想を素朴に信じることの許されない現実を生きている。だとすれば、「貧しい平面」としての平台型絵画平面を、ディストピアに反転してしまった情報平面(インターフェイス)の先駆(予言?)として見ることはできないだろうか。しかしそのためには、もっと雑多で大量なデータ(情報)を処理するような絵画平面が登場するのを待たねばならない。
おそらく、最も簡単な解答は、「平台型絵画平面は、それとわかる対象を収容するかぎりは、その対象を、普遍的に親しまれている特徴を具えた人工のものとして提示する」[★5]からである、というスタインバーグの言葉を引くことであろう。再現=表象としてのイメージではなく、人工物そのものが、作業面としての絵画平面に直接貼り付けられている。まさにそれが、ラウシェンバーグの作品でおこなわれていることである。
スタインバーグは、《ベッド》(1955年)や、《三度目の絵画》(1961年)に貼りつけられた時計、あるいは《冬のプール》(1959-60年)の梯子といった、ほとんどそのままの状態で貼りつけられた人工物を、ラウシェンバーグ作品における極めて重要な「象徴」として読み解こうとしている。つまり、抽象表現主義のように世界をすべて平面性に溶かし込もうとする操作を被ることなく、同時に、再現=表象の視覚的イメージとしての描写という「後退」からも逃れ、それでもなお、現実世界に存在する具体的な人工物として絵画平面に侵入し、それがそのまま「象徴」にまで高められる。ラウシェンバーグの作品に貼りつけられた人工物たちは、言ってみれば、様々な「批評基準」の間を綱渡りのように渡り、見事に無傷のまま、絵画平面にまでたどり着いたのである。
こうして、スタインバーグの提唱した平台型絵画平面は、絵画史における「他の批評基準」を担う新しい概念として提出された。最重要作家として挙げられたラウシェンバーグの絵画平面は、あらゆるものが等価に並べられる作業面としてだけでなく、データを記入する「受容器」という、情報社会以後のアートにおいて、今でもきわめて魅力的なコンセプトを宿していると言ってよいだろう。
しかし、スタインバーグが提示する、このいささか楽観的にも思えるヴィジョンは果たしてどこまで額面どおり受け取ってよいものなのだろうか。先に確認したとおり、ラウシェンバーグの絵画平面において、そのままの人工物やデータが並べられ、出会い、時として「象徴」にまで高められる操作があり得るのはよいとして、ではそのようにしてつくられた絵画平面それ自体は、一体何を表しているのだろうか。このことについて、美術史家の林道郎はスタインバーグのいう平台型絵画平面を、一般論的に現代の情報社会環境に結びつけること、とりわけ、コンピューターのデスクトップと同じように考えてしまうことに対して批判的な見解を述べている。
……ラウシェンバーグに典型的に見られるように、そこには都市の廃物がある。すでに使用価値を失ったイメージがある。読むことのできない新聞がある。また、無意味な反復がある。それらは、われわれの消費や加工に応じるコンピューターの画面上の情報とは異なり、むしろ抵抗物として、あるいは欲望の残滓として存在しているといっていい。<中略>その意味で、コンピューターの画面が、モダニズムの絵画が自己完結的なユートピアを追求してきたのに対して、多様な情報が多元的に併存するヘテロトピアだといえるとすれば、平台型絵画平面の重要性は、そのヘテロトピア的な方向というよりはむしろ、記号流通の圏域に必然的に生じる澱みや吹き溜まりといったディストピア的な方向にこそ見出されるべきだと思う[★6]。
ラウシェンバーグの絵画平面は、ゴミのようなものたちで溢れている。ベッドにせよ、時計にせよ、梯子にせよ、それらはもはや正常に機能しないゴミたちだ。しかし、当然のことだが、それらははじめからゴミであったわけではない。それらの人工物やデータは、平台型絵画平面へと貼りつけられることによって、本来の機能を果たさないゴミとなったのだ。
平台型絵画平面はたしかに、あらゆるものを取り込むことができる。しかしそれは、取り込まれたものたちが本来の機能を剥奪され、ゴミとなる限りにおいてなのだ。その上になんでも置いておけるような水平な作業面、いくらでもデータを書き込める受容器としての平台型絵画平面は、印刷機やスキャナのフラットベッドのように、取り込んだものをひとつの形式に変換し保存しておけるのではなく、同じ平面の上に異なる対象を並置することによって、それらをゴミに変えてしまう場だったのではないか(印刷機やスキャナのフラットベッドに正しく対応するのはおそらく、平台型絵画平面ではなくマン・レイの「フォトグラム」だろう)。
多様なもの、多元的なものを併存させるヘテロトピア的平面が裏返って、すべての機能が剥奪されゴミになってしまうディストピアへと変わる。平台型絵画平面は、「他の批評基準」において乗り越えたはずだったモダニズム絵画の「貧しさ」とは別種の「貧しさ」を宿命づけられた「貧しい平面」であった。
「貧しい平面」としての平台型絵画平面について、林による賢明な警告を気にかけつつ、あえてもう少しだけ、今日の情報社会的テーマに類比させて考えるとすれば、インターネットにおける「認知限界」(ハーバード・サイモン)や「パーソナライゼーション」などの問題を対応させるべきではないだろうか。カリフォルニアン・イデオロギーの現実的失効を例に出すまでもなく、私たちはすでに、多様な情報が多元的に併存するヘテロトピアとしてのコンピューター、インターネットという幻想を素朴に信じることの許されない現実を生きている。だとすれば、「貧しい平面」としての平台型絵画平面を、ディストピアに反転してしまった情報平面(インターフェイス)の先駆(予言?)として見ることはできないだろうか。しかしそのためには、もっと雑多で大量なデータ(情報)を処理するような絵画平面が登場するのを待たねばならない。

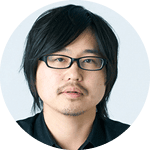
黒瀬陽平
1983年生まれ。美術家、美術評論家。ゲンロン カオス*ラウンジ 新芸術校主任講師。東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。博士(美術)。2010年から梅沢和木、藤城噓らとともにアーティストグループ「カオス*ラウンジ」を結成し、展覧会やイベントなどをキュレーションしている。主なキュレーション作品に「破滅*ラウンジ」(2010年)、「キャラクラッシュ!」(2014年)、瀬戸内国際芸術祭2016「鬼の家」、「カオス*ラウンジ新芸術祭2017 市街劇『百五〇年の孤独』」(2017-18年)、「TOKYO2021 美術展『un/real engine ―― 慰霊のエンジニアリング』」(2019)など。著書に『情報社会の情念』(NHK出版)。



