「ポスト」モダニズムのハード・コア――「貧しい平面」のゆくえ(1)|黒瀬陽平



よく知られているように、《救世観音像》は聖徳太子の等身像と言われ、太子の怒りを怖れるあまり長い間、何人たりともその姿を見ることを許されない秘仏であったが、明治17年(1884年)にフェノロサと岡倉天心によって開扉された。その造形は確かに、太子の怨霊伝説を物語るかのように、アルカイックでミステリアスな雰囲気に満ちている。とはいえ、《救世観音像》の重要性は、そのようなエピソードにのみ帰せられるわけではない。井上によれば、《救世観音像》こそ、古代中国美術に流れる「気」の思想を体現する最高のサンプルであるという。
気の思想とは何か。紀元前2世紀、淮南(わいなん)王劉安が編纂した百科事典『淮南子(えなんじ)』の天文訓には、混沌から虚空が生まれ、虚空から宇宙が生まれるという世界創成のヴィジョンが記されているが、宇宙から生まれるものが気であり、気こそが万物創世において最も重要な因子であると考えられていた。井上は、淮南子の思想を受け継いで展開した北宋時代の程伊川(ていいせん)や、南宋の朱子の理論を参照しながら、次のように要約している。
「気」は万物創成の根源を成す眼に見えない因子で、「気」の多く集積するところに聖なるものが生まれ、凡庸なものには「気」は薄かった。「気」はものの本質であり、眼に見える形は現象であった。霊山、神仏、霊獣、瑞鳥などは、いずれも「気」の密なる集積によって成ったものであり、ひとたび形を成したのちには、新たに「気」を発し、次なる創造に大きく作用する存在であった[★1]。
古代中国美術は、「雲気文」に代表されるような表現として気を視覚化し、独自のボキャブラリーを育んだのである。このような気の思想は、インドから伝わった仏像に対しても適応され、インド風の肉感豊かな造形はやがて、全身から気を発する痩身の像に変わっていったのだ。
《救世観音像》はまさに、最高度に達した気の表現によって生み出された作例にほかならない。透彫金具の宝冠と光背に見られる文様は、C字形と半C字形、S字形を複雑に絡み合わせた雲気文であり、比類なき成熟度を誇っている。外側へ向かって3度巻き上がる両肩の垂髪。鋭く、重力に逆らうように左右へ張り出している天衣。そして、それらのすべてが厳格な左右対称を成す構成は、着衣や領巾を鋭くデフォルメすることによって気の「発散」を暗示する表現技法である。
一方、《釈迦三尊像》の造形はどうだろうか。光背、垂髪、天衣、どれを取っても《救世観音像》に比べると著しく単純化されている。左右の脇侍菩薩立像の光背に見られる文様は、《救世観音像》にも見られる火焔のパターンや、S字形雲気を絡ませた連続文などが模倣されているが、その複雑さは及ぶべくもない。要するに、日本の止利(とり)仏師が作ったことの明らかなこの《釈迦三尊像》には、古代中国からの気の思想と、そのイコノロジーに対する理解が欠落しており、形の模倣にとどまっているのである。
しかし、井上は、《釈迦三尊像》の真価を見極めるためには、別の観点からの分析が必要であると主張する。別の観点とは、「フレームのなかの造形」と名付けられるものである。井上による図解を見れば明らかなように(図3)、まず、中尊本体をすっぽりと納める二等辺三角形があり、その二辺を延長させてゆくと、下座までを納める相似形二等辺三角形が現れる。さらに、この中央の二等辺三角形を軸として、その外側に教示菩薩立像を含む、より大きな二等辺三角形が現れる。このように、《釈迦三尊像》を手がけた仏師止利は、複雑に過ぎる気の表現のかわりに、計算され尽くした幾何学的構成によって造形的調和を獲得しようとしたのである。

〈夢殿観音〉に比較して、顔は迫力と神秘感を弱め、脇尊の「気」の発散を表す垂髪や天衣衣端の撥ねは力弱く、また光背の輪郭も剛直な感じが強く柔らかみを失っている。このように本像が大陸伝来の様式をもとにしてこれに迫りながらも、半歩及ばない点がみられるのに対し、以上に記したフレームによる造形の筋を徹底的に試みることにより、大陸には存在しない止利仏師独自の境地をひらいたことは、賞讃に値する[★2]。
モダニズムとフォーマリズムのサンプルとして、ここで念頭に置いているのはもちろん、20世紀アメリカの美術評論家クレメント・グリーンバーグの芸術論と、それを背景に台頭したアメリカ抽象表現主義である。周知のように、グリーンバーグはモダニズムを、諸芸術が厳然たる自己反省、自己批判の精神によって、自らに固有のメディウムの本質を突きつめ、純粋化してゆくプロセスである、と定義した。
彼がもっとも強調したのは、視覚芸術としての絵画の平面性である。絵画がそれ自身ではないものを表象する三次元的なイリュージョンを徹底的に排除し、自らの平面性のみを純粋化させ、自己充足的に完結した表現を目指さなければならない、と主張したのだ。そして、その絵画がどれほどの自己反省、自己批判的態度を持ち、どれだけ純粋な平面性に肉薄できているかを診断する測定装置として、フォーマリズム批評が誕生したのである。
グリーンバーグのこのようなモダニズム史観とフォーマリズム理論と同期するかのように、まずはジャクソン・ポロックのようなオール・オーバーな抽象絵画が、そして、マーク・ロスコやバーネット・ニューマンのような「カラーフィールド・ペインティング」が、さらには、自己言及的という意味ではほとんどグリーンバーグ理論の戯画であるかのような、フランク・ステラの「ブラックペインティング」シリーズなどが次々と登場し、20世紀のアメリカ現代美術史を彩ってゆくことになる。
もちろん、あまりに極端な純粋化を指向するグリーンバーグのモダニズム史観が、美術史のスタンダードとして登録されるはずもない。70年代以降は、彼の弟子であったロザリンド・クラウスを筆頭にグリーンバーグ批判が盛んに行われ、やがて、グリーンバーグのモダニズム史観があまりに単線的かつ偏狭であったことが認識され、それによって抑圧され、排除されたものの復権を唱える美術批評が隆盛することとなった。
いささか教科書的なおさらいになってしまったが、私にはどうしても、ヨーロッパの壮大な美術史に対して独自のモダニズム史観をでっちあげ、純粋で普遍的なフォーマリズム理論によって、自身の考えるメディウムの本質とは無縁の、「不純な」ノイズたちを振り切ろうと必死になっていたグリーンバーグの姿に、《救世観音像》に表された深遠な気の思想と、そのイコノロジーの膨大な蓄積を前にして、『淮南子』を投げ出すかわりに、その手に定規を握りしめ、大陸の思想哲学に囚われない「普遍的な」幾何学的構成に踏み出すべく図面に線を引きはじめた止利仏師の姿が重なって見えてしまうのである。
グリーンバーグと止利仏師はどちらも、「持たざる国」、あるいは「貧しい国」に住んでいる自らの立ち位置にきわめて自覚的であったように見える。直接に大陸を知らない止利仏師には、気の思想とそのイコノロジーはあまりにも複雑で難解に過ぎた。辺境の国に生まれた仏師として、大陸人と同じ教養を身につけ、表現に昇華してゆくことよりも、「貧しさ」がそのまま「普遍」であるかのような幻影に引き寄せられていったのではないか。たとえば、ヴァシリー・カンディンスキーやピエト・モンドリアンのような抽象表現が、ヨーロッパ人としての自らの身体に刻み込まれた「因習(convention)」としての象徴体系からの自由を志向していたのに比べ、歴史の持たないアメリカに隆盛した抽象表現主義の絵画たちは、あたかも更地に建てられたプレハブ建築のように、その「貧しさ」を抱え込んでいたのではなかったか。
とはいえ、「貧しさ」の受け止め方について言えば、グリーンバーグと止利仏師の間の違いは重要なものに思える。止利仏師における大陸的教養の欠落とフォーマリスティックな幾何学的構成は、ある種の「居直り」を思わせ(もちろん、止利仏師本人がそう考えていたとは言えないわけだが)、椹木野衣の提唱する「悪い場所」論を連想させるのに対し、グリーンバーグのそれは、いささか厄介な屈折がともなっている。美術評論家のレオ・スタインバーグは、1972年に発表された論文(口頭発表は68年)において、諸芸術はモダニズムにおいてはじめて自己反省、自己批判の意識を獲得したのであるというグリーンバーグのモダニズム史観の前提を痛烈に批判している。
……すべての重要な芸術は、少なくとも一三〇〇年代(トレチェント)以降、自己批判に専心している。それがほかにどんなものについてのものであろうと、芸術とはまず芸術についてのものなのだ。すべての独創的な芸術はそれぞれの限界を探るものであるのだから、かつての芸術とモダニズムのそれとの違いは、自己-限定という事実にあるのではなく、この自己-限定がとる方向にある。内容の一部となっているようなこの方向に[★3]。
そしてスタインバーグは、純粋化に向かう自己限定の芸術しか認めようとしないグリーンバーグに対して、「それはある特殊な事例にすぎないものを、ひとつの必然と誤解している」のであると、さらに強い言葉で非難する。
……ある歴史的瞬間において画家たちは、その芸術がどこまで他を合併することができるかを、つまり芸術でありつづけながらなおどこまで反芸術に踏み込むことができるかを、見定めることに関心を寄せるようになった。だが別の時代になると、画家はまったく逆の限界を、つまり商売(ビジネス)であることを維持しながらどれだけのものを棄てることができるかということを、追究した。いずれの場合も変わらないのは、芸術が自らに関わるということであり、自らの作業を問題にするという画家の関心である。精神が自己批判に向かいさえすればそれだけでモダニズムを区分するには十分だというのは、田舎者の偏狭なのである[★4]。
まったくもって正論である。スタインバーグは、レンブラントやミケランジェロらの作品を手さばきよく分析しながら、いかに近代以前の巨匠たちが絵画においてすぐれた自己批判を行い、様々な道行きを開拓してきたのかを力説する。これらの鮮やかな「証拠」の数々を前にして、もはやグリーンバーグの反論の余地はないかのようである。しかし、スタインバーグが最も問題視しているのは、グリーンバーグ自身は、近代以前の巨匠たちの自己批判意識を重々承知していたにもかかわらず、それを隠蔽することによって自らのモダニズム史観を強調しているのではないか、という点なのである。先に述べたグリーンバーグの「厄介な屈折」とは、まさにこのことだ。
……つまり、「写実主義的なイリュージョニズムの芸術はその媒体を隠してきたのであり、芸術を覆い隠すために芸術を用いる」。一方「モダニズムの芸術は、芸術に対する注意を喚起するために芸術を用いたのである」。これではまるで、近代詩が初めて詩それ自体の過程に対して注意を差し向けるように促したのであり、一方ダンテやシェイクスピア、そしてキーツは、ただ物語を語るために押韻や韻律を用いたのだ、と言っているようなものだ。グリーンバーグは、かつての巨匠のイリュージョニズムに取り込まれてしまったことがあったのか。明らかにそれはない。彼は絵画に対する優れた眼をもっているからだ[★5]。
スタインバーグは、このようなグリーンバーグの美術史に対する「隠蔽工作」を「まったく貧しいやり口である」と書きつけている。1960年に発表されたグリーンバーグの論文「モダニズムの絵画」を見れば、ウッチェルロ、ピエロ・デッラ・フランチェスカ、エル・グレコ、ラ・トゥールらの名前を出しながら彼らの芸術とモダニズムが無縁のものではないと指摘し、むしろこの生まれたばかりのアメリカ抽象絵画たちを美術史に接続するような野心を見せていた(それは当時のグリーンバーグにとっての仮想敵であったアメリカ土着の絵画=キッチュなものとの切断を意図していた)とはいえ、その後のグリーンバーグが強調し、そしてその通りに受容されることとなる、自己目的的なモダニズムの純粋化のプロセスと、単線的な史観について言えば、スタインバーグの批判は的を射ていると言わざるをえない。
もしスタインバーグの指摘が正しいとすれば、グリーンバーグのモダニズム理論とフォーマリズム批評、そしてアメリカ抽象表現主義には、歴史を持たない国としての「貧しさ」と、単線的な歴史観を強調するために、あえて西欧絵画史の達成を低く見積もるという、二重の「貧しさ」が刻印されていることになるだろう。
私はここで、二重の「貧しさ」を抱えたグリーンバーグとアメリカ抽象表現主義を糾弾し、「貧しさ」に居直ることによって独自の進化を遂げた「日本美術史」を称揚しようというつもりは微塵もない。抽象表現主義に限らず、デュシャンにせよ、ウォーホルにせよ、村上隆にせよ、ある種の「貧しさ」が現代美術にとって必要不可欠な因子であり、それによって新たな芸術を切り拓いてきたことは間違いのないことである。グリーンバーグと止利仏師のエピソードは、美術史における重要因子としての「貧しさ」が、異なる歴史、文化圏においても存在しかつ、それぞれの文脈において異なる問題を抱えていたということをはっきりと示している。そしておそらく、この「貧しさ」をめぐる問題は、クラウスがグリーンバーグ批判としておこなったような、フロイト―ラカン的な「抑圧されたものの回帰」の図式によって乗り越えられたわけではなく、まして、その「貧しさ」に居直ることによって問題自体を抹消されたわけでもなく、現代的なテーマとして存在し続けている。そうである以上、美術史上に点在する、それぞれに差異を持った「貧しさ」を必要に応じてマッピングし、ひとつの系譜としてたどってみる必要があるのではないか。
次回は、引き続きスタインバーグの言葉に耳を傾けながら、アメリカ抽象表現主義とミニマリズムの「貧しさ」を、もっとも早い段階で相対化し、新たな位相へと導いた、ロバート・ラウシェンバーグの「貧しい平面」をめぐる諸問題について検討してゆこう。

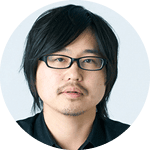
黒瀬陽平




